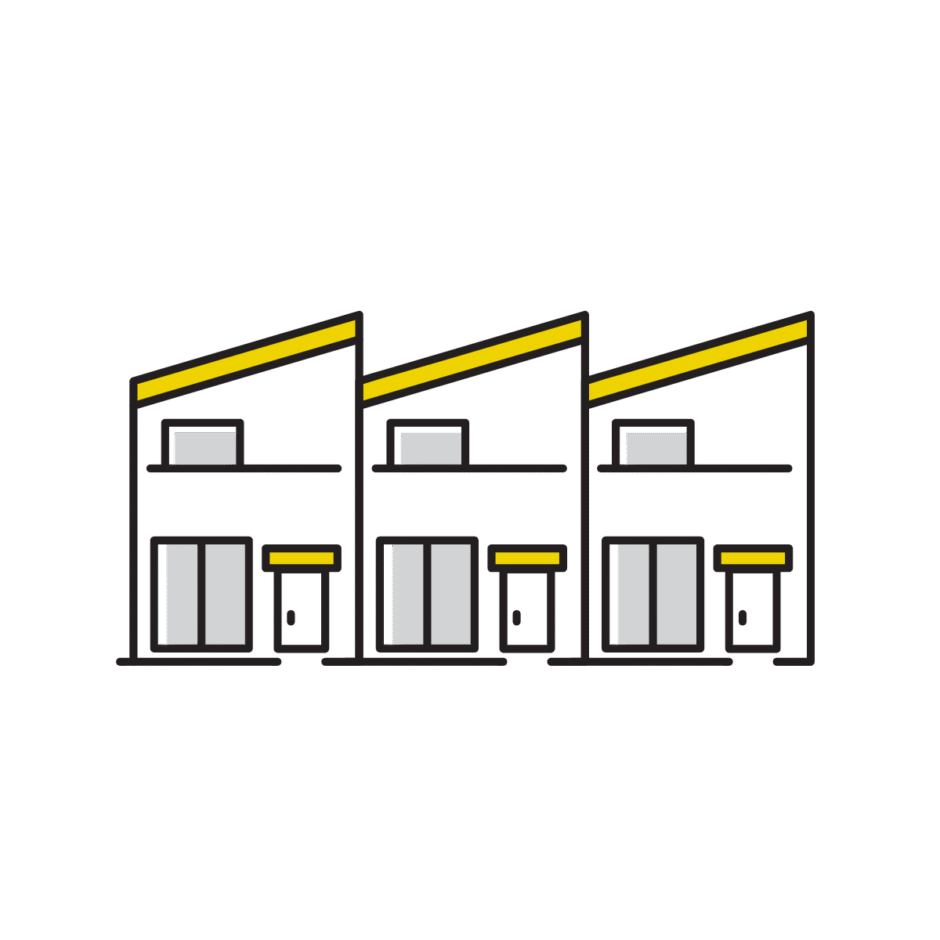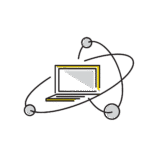企業概要
事業内容とリスク
トラストホールディングス株式会社は、福岡を拠点とする持株会社であり、駐車場事業を中核に、不動産、駐車場等小口化、メディカルサービス、RV(キャンピングカー)、温浴施設・警備など多角的に事業を展開しています。特に駐車場事業は都市部での「遊休地の有効利用」を掲げ、土地オーナーと賃貸契約を結びながら収益性の向上を図っており、同社の収益基盤を支える主力分野です。
不動産事業では「人へ、街へ、次世代へ愛される住まい」を掲げ、新築マンションの企画・開発・販売を中心に展開。不動産市況や金利動向に大きく左右されるリスクが存在します。また、駐車場等小口化事業では不動産特定共同事業法に基づく「トラストパートナーズ」という投資商品を提供し、長期的な資産運用を支援していますが、販売時期や契約比率によって四半期ごとの業績が変動しやすい点が課題です。
さらに、医療機関への賃貸やコンサルティングを担うメディカルサービス事業、キャンピングカー製造・販売を行うRV事業、地域密着型の温浴施設運営など、多角的な収益源を確保しています。ただし、多様な法規制(駐車場法、宅地建物取引業法、警備業法など)への対応が必要であり、規制変更や遵守難によるコスト増のリスクが挙げられます。また、借入依存度の高さ(有利子負債依存度62.1%)は金利上昇局面での収益悪化要因となり得ます。
今までの業績
過去5年間の連結売上高の推移を見ると、2021年6月期の123億円から、2024年6月期には136億円と成長を続けましたが、直近の2025年6月期は128億円とやや減収となっています。一方で、純利益は堅調に推移し、2023年6月期の2億4,000万円から2025年6月期には約3億4,600万円と増加しています。自己資本比率も8.1%から13.9%へと改善しており、財務の安定性は高まっている点が投資家にとって安心材料です。
配当の面では、1株当たり配当額が2021年の16.4円から2025年には19円へと増加しています。特に2025年は上場市場区分変更を記念した特別配当を含む形で株主還元を強化しており、配当性向も44.0%と高水準。配当金で生活を支えたい投資家にとっては注目すべきポイントです。
ただし、セグメント別では駐車場事業で大型契約の解約が影響し、売上がやや減少。不動産事業は安定した新築マンション販売が収益を支えていますが、建築コスト高やローン金利上昇の影響を受けやすい状況です。RV事業はキャンピングカーブームの追い風で改善傾向にあります。
今後の業績
同社は中長期的に「駐車場」「不動産」「駐車場等小口化」の3本柱を中心に収益基盤を強化する方針です。駐車場事業では、新紙幣対応機器の導入や利便性向上に向けた機器リニューアルを進め、収益力の底上げを図ります。また、駐車場不足という社会課題の解決にも資する事業として、長期的な成長余地があります。
不動産事業では、建築コストや金利上昇による逆風がある中でも、地域需要を見極めたマンション開発を進め、安定供給を継続する姿勢です。小口化事業「トラストパートナーズ」では対象不動産を拡充し、販売件数拡大に注力する方針であり、投資家層の広がりが期待できます。
メディカルサービス事業では、財務コンサルティングに加え外部パートナーとの連携を強化し、地域医療の経営安定化を支援することで新たな収益源を模索。RV事業も引き続き市場拡大の追い風を受け、製造から販売・カスタマイズまでの一貫体制を武器に安定収益を目指します。
一方で、地価高騰や人材不足、有利子負債依存度の高さといったリスク要因は今後も注視すべきです。特に金利動向は同社の資金調達コストに直結するため、投資家としては経済環境の変化を踏まえたリスク管理が重要となります。
長期的に見れば、配当政策に積極的で株主還元姿勢が明確な点、財務基盤が着実に強化されている点は魅力的です。配当収入を安定的に得たい個人投資家やFIREを目指す人にとって、今後の成長と還元余力を注視する価値のある企業といえるでしょう。
業種平均の比較分析
指標比較表
以下は、トラストホールディングス株式会社(2025年6月期)の指標と、不動産業(131社平均)との比較表です。差異についても併記し、個人投資家が長期配当投資の観点で判断しやすいよう整理しました。
| 指標 | トラストHD | 業種平均(不動産業) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE, %) | 12.1 | 9.85 | +2.25 |
| 総資産経常利益率(%) | 3.43(計算値:経常利益132,615千円 ÷ 総資産3,870,480千円) | 4.43 | -1.00 |
| 売上高営業利益率(%) | 20.09(計算値:営業利益529,976千円 ÷ 売上高12,887,524千円) | 12.52 | +7.57 |
| 自己資本比率(%) | 36.9 | 32.42 | +4.48 |
| 配当性向(%) | 44.0 | 32.25 | +11.75 |
| 純資産配当率(%) | 1.33(計算値:1株配当19円÷1株純資産1,427円相当) | 3.07 | -1.74 |
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
ROEは12.1%と業種平均9.85%を上回っています。これは株主資本を効率的に活用し利益を生み出していることを意味します。不動産業は資産規模の大きさからROEが低くなりがちですが、同社は駐車場事業やRV事業といったストック性・収益性の高い事業が寄与し、資本効率を高めています。長期的な株主還元を重視する投資家にとっては、プラス評価できる要素です。ただし、ROEが高水準にある一方で有利子負債依存度が62%超と高い点には注意が必要で、今後の金利動向によってはROEが圧迫される可能性があります。
2. 総資産経常利益率
総資産経常利益率は3.43%と業種平均4.43%を下回っています。これは総資産に対する利益効率がやや低いことを示します。要因として、不動産や駐車場用地の仕入資金を借入金で賄っていることが挙げられます。資産を積み増すことで規模を拡大している一方、利払い負担や不採算案件の影響で利益効率が抑えられている可能性があります。この点は、資産を拡大する戦略と利益効率のバランスをどう取るかが今後の課題です。長期投資家にとっては、安定成長を狙ううえでチェックすべき重要指標といえます。
3. 売上高営業利益率
営業利益率は20.09%と、業種平均12.52%を大きく上回っています。不動産業では通常10%前後が多いなかで、この高水準は注目に値します。駐車場事業の安定収益やRV事業の好調さが寄与し、営業段階でしっかり利益を残していることを示しています。営業利益率が高いことは、景気変動やコスト上昇に直面しても一定の利益を確保できる体質を意味し、株主還元の原資が安定的に確保されやすい点でポジティブです。
4. 自己資本比率
自己資本比率は36.9%で、業種平均32.42%を上回っています。財務の安定性という点では評価できますが、依然として借入依存度が高く、資金調達の構造に偏りがあることは事実です。とはいえ、ここ数年で自己資本比率が着実に改善してきた点は明るい材料であり、株主にとってはリスク低下につながります。今後も利益の積み上げや内部留保の活用により、さらに比率を高められるかがポイントとなるでしょう。
5. 配当性向
配当性向は44.0%と業種平均32.25%を大きく上回ります。これは、利益の4割以上を株主還元に充てていることを意味し、株主重視の姿勢が鮮明です。配当で生活設計を考える投資家にとっては魅力的ですが、一方で還元余力を超えた水準に達すると将来の成長投資に制約が生じる懸念もあります。直近では市場区分変更に伴う記念配当も含まれているため、今後は安定的に30~40%台を維持できるかが注目点です。
6. 純資産配当率
純資産配当率は1.33%と業種平均3.07%を下回っています。これは純資産に対してどの程度配当を行っているかを示す指標で、同社の場合は「配当を出しているものの、資本規模に比して還元は控えめ」といえます。配当性向が高い割に純資産配当率が低いのは、純資産が積み上がってきたことが背景です。長期的には、純資産の増加とともに配当水準も引き上げることで、投資家にとってより魅力的な還元指標となる余地があります。
配当方針と今後の展望
トラストホールディングス株式会社の配当方針と今後の展望
配当政策の基本姿勢
トラストホールディングスは「株主への利益還元を経営の重要課題」と明言しており、同時に事業成長のための内部留保とのバランスを重視しています。基本方針として 安定的な配当の継続 を掲げ、毎年「中間配当」と「期末配当」の年2回の剰余金配当を行う体制を定款に明記しています。期末配当は株主総会、中間配当は取締役会決議で実施される仕組みで、株主にとって予見性の高い制度です。
第12期(2025年6月期)の期末配当は1株あたり11円を予定しており、中間配当(8円)と合わせて 年間19円の配当 となります。この19円には、東京証券取引所スタンダード市場および福岡証券取引所本則市場への上場市場区分変更を記念した「記念配当2円」が含まれています。
配当関連の実績と指標
直近数期の配当推移を見ると、1株当たり配当額は2021年16.4円から2025年には19円へと増加。特に2025年は記念配当を含めて株主還元姿勢を強めています。
- 配当性向:44.0%(業種平均32.25%より高い)
- 自己資本比率:36.9%(業種平均32.42%より高い)
- ROE:12.1%(業種平均9.85%を上回る)
これらの指標から、株主への積極的な利益還元姿勢と、安定性のある財務基盤が確認できます。ただし、純資産配当率は1.33%と業種平均3.07%を下回る点が特徴で、資本規模に対する配当の厚みは控えめです。
今後の配当方針の予測
- 安定配当の継続
経営陣は「安定的な配当」を方針に掲げているため、来期以降も年2回配当を維持する可能性が高いと考えられます。記念配当を除いた実力値では年間17円程度の水準が目安になるでしょう。 - 利益連動の柔軟性
配当性向が既に44%と高水準にあるため、急激な増配よりも「業績に応じた緩やかな配当増加」が予想されます。特に主力の駐車場事業や不動産事業の収益が安定する限り、減配の可能性は低いとみられます。 - 内部留保とのバランス
事業拡大や新規投資(駐車場開発、不動産仕入れなど)のために内部留保を厚くする必要があるため、配当性向の上限は50%前後が目処になると予想されます。これ以上の配当性向引き上げは成長投資を阻害するリスクがあるため、現状の水準維持が妥当と考えられます。 - 将来の増配余地
ROEが業種平均を上回っている点、営業利益率が高い点から、中期的にはさらなる増配余地が残されています。特に借入依存度の改善や不動産事業の収益安定が進めば、株主還元強化の余力が増す可能性があります。
投資家への示唆
長期的な配当収入を狙う投資家にとって、トラストホールディングスは以下の点で魅力があります。
- 高い配当性向と安定方針 → FIREを目指す投資家に安心感
- ROE・営業利益率の高さ → 将来的な配当余力の拡大余地
- 純資産配当率の低さ → 現状は控えめ還元、今後改善余地あり
今後の注目点は「借入依存度の低下」と「不動産・駐車場小口化事業の成長」。これらが改善・拡大すれば、内部留保に頼らず配当性向を維持したまま増配できる環境が整うと考えられます。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
トラストホールディングスは、駐車場事業を中核に不動産、駐車場小口化、メディカルサービス、RV事業など幅広い収益源を持つ企業です。配当政策の基本方針として「安定的な配当の継続」を掲げ、年2回配当を制度化している点は、長期投資家にとって安心感のあるポイントです。また、2025年の年間配当19円(うち記念配当2円を含む)は、株主還元の姿勢を強く示しており、配当性向44%という高水準は株主重視のスタンスを裏付けています。
ただし、日本株全体で比較すると、同社の配当利回りは決して突出して高いわけではありません。純資産配当率が業種平均を下回っており、資本規模に対する配当の厚みはやや物足りない印象です。また、有利子負債依存度が6割を超えているため、金利上昇局面では利益や配当余力が圧迫されるリスクも抱えています。こうした点は、安定配当を重視する長期投資家にとって中期的な不安要因となり得ます。
一方で、同社はROE(12.1%)や営業利益率(20%超)が業種平均を上回り、利益創出力の高さを示しています。駐車場事業は景気に左右されにくい安定収益基盤であり、不動産小口化商品「トラストパートナーズ」やRV事業などの成長余地も考慮すれば、長期的には配当を維持・増加させるポテンシャルが存在します。他の日本株と比較しても、「高配当株のような即効性はないが、安定配当+将来の増配期待」というバランス型の魅力が光ります。
総合的に見ると、同社は 高配当銘柄としての突出度はやや弱いが、安定配当と成長余地を兼ね備えた中堅株 と評価できます。配当金で生活設計を狙う投資家にとっては、主力ポートフォリオというよりは、分散投資の一部として組み入れるのが適切です。特に将来の金利環境と借入依存度の改善が配当安定性に直結するため、この点を注視する必要があります。
- プラス要因
・安定配当の継続を掲げており減配リスクは低い
・ROE・営業利益率が業種平均を上回り利益創出力が高い
・成長余地のある駐車場・不動産小口化事業を展開 - マイナス要因
・配当利回りは日本株全体の高配当銘柄と比べると見劣り
・純資産配当率が業種平均以下で、資本効率の還元が控えめ
・有利子負債依存度が高く、金利上昇局面では配当余力が縮小する懸念
結論として、長期安定配当を志向する投資家にとって「補完的に保有する価値はあるが、配当投資の主力銘柄としてはやや物足りない」ため、日本株全体での評価は★★★☆☆としました。