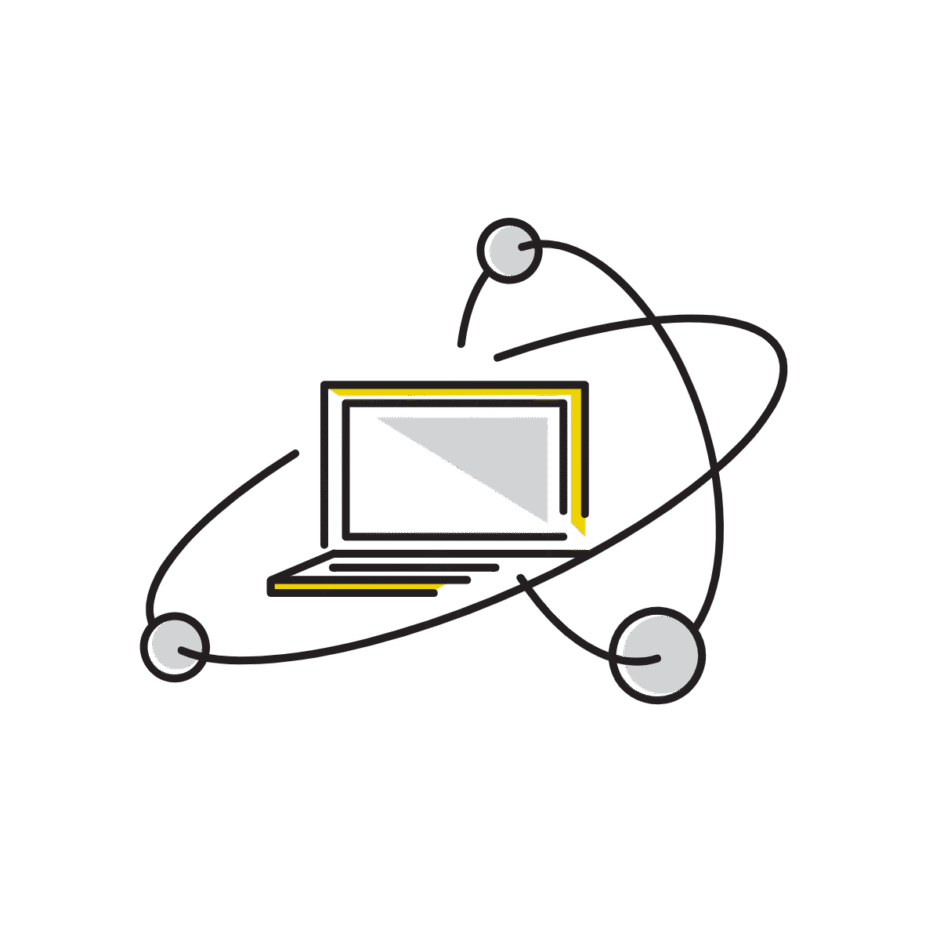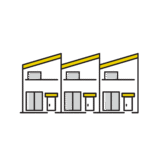企業概要
事業内容とリスク
Zenken株式会社は、教育事業を原点としながらも、現在では「WEBマーケティング」「海外人材」「不動産」という3つのセグメントで事業を展開しています。
WEBマーケティング事業
主力はWEBマーケティングで、特に中小企業向けに「ニッチトップ戦略」を支援している点が特徴です。具体的には、検索エンジン経由で情報収集を行う「意欲あるユーザー」に向けた集客メディアを制作・運営し、効率的に顧客を獲得する仕組みを提供しています。これによりクライアントは営業コストを抑えながら高い確度で成約につなげることができます。
海外人材事業
少子高齢化に伴う日本の労働人口減少という課題に対し、海外のIT・介護人材を日本企業へ紹介する事業を展開。特にインドの大学と提携したIT人材供給、介護福祉士資格を目指す長期教育プログラムなど、持続的な人材供給体制を構築しています。また、外国人向けの日本語教育や留学斡旋事業も展開し、多角的に海外人材をサポートしています。
不動産事業
自社ビル「全研プラザ」や「Zenken Plaza II」を賃貸し、安定収益を確保しています。マーケティングや人材事業が外部環境の変化に左右されやすい中、不動産収益は安定的な収益源となっています。
リスク要因
- 主力であるWEBマーケティング事業の売上が全体の約7割を占めており、検索エンジンのアルゴリズム変更や規制強化の影響を受けやすい。
- 人材事業は海外人材の受け入れ環境や社会的な抵抗感に左右される。特に介護分野では定着率向上が課題。
- 技術革新や競合参入により優位性が損なわれるリスクも存在する。
投資家視点では、成長性のある事業ポートフォリオを持ちながらも、特定事業への依存度が高い点がリスクといえます。
今までの業績
決算数値を見ると、Zenkénは2021年から2025年までの間で売上が6,216百万円から5,536百万円へと減少傾向にあります。特に2023年の子会社サイシード売却による連結除外の影響で、売上が大きく減少しました。ただし、直近の2025年はほぼ横ばいで、事業基盤は安定に向かっていると考えられます。
- 売上高:2022年に7,705百万円を記録した後、2024年には5,627百万円まで減少。しかし2025年は5,536百万円と下げ止まりを示しています。
- 経常利益:2022年に2,349百万円とピークを迎えた後、2024年には390百万円まで減少。2025年は400百万円とわずかな改善が見られます。
- 純利益:2022年に1,584百万円を計上した後、2023年以降は減少。ただし2025年は342百万円と回復基調にあります。
- 財務健全性:自己資本比率は常に80%以上を維持しており、2025年も85.4%と非常に高い水準。財務基盤の安定性は際立っています。
配当については、2021年の記念配当を含む10円から始まり、2022年には20円まで増加しましたが、その後は利益減少に伴い減配が続き、2025年は13円となっています。配当性向は2024年に80%を超える異常値となった後、2025年は47%と落ち着いています。
投資家にとって注目すべきは、「安定的な財務基盤」と「利益の変動に応じた配当方針」です。業績の波はあるものの、潤沢な自己資本が支えとなり、長期投資において致命的なリスクは抑制されている点は安心材料といえます。
今後の業績
Zenkénは2025年8月に発表した中期経営計画「Road to 250」を掲げています。これは、2026年から2030年までの5年間で時価総額250億円を目指す計画です。
成長戦略の柱
- 海外人材事業の拡大
特にITと介護分野を重点領域とし、売上比率を25%から43%へ引き上げる方針。地方自治体との連携も強化し、持続的な需要に応えることで安定収益を確保する狙いがあります。 - WEBマーケティングの進化
AIの進化による環境変化に対応し、国内集客にとどまらず海外集客や成約支援までを視野に入れた「トータルコンサルティング」へ事業を拡大。生成AI活用による生産性向上にも積極的です。 - 株主還元方針
累進配当を基本とし、「DOE2.5%」または「連結配当性向50%」のいずれか高い方を基準とする明確な方針を掲げています。これは長期的に安定配当を求める投資家にとって大きな魅力となります。 - M&A投資
100億円規模のM&A投資枠を設け、成長領域への積極投資を行う方針。
数値目標
- 2030年に売上高130億円、営業利益30億円、純利益20億円を達成する計画。
- 現状の売上約55億円から倍増以上を狙う野心的な計画であり、特に海外人材事業の成長が鍵を握ります。
投資家への示唆
長期投資家にとって魅力的なのは、配当の安定性と事業の成長余地です。特に海外人材市場は社会的課題に直結しており、国策的にも追い風が吹いています。一方で、マーケティング事業の依存度や技術革新リスクが残るため、安定成長が実現するかは事業多角化の成否にかかっています。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | Zenkén株式会社 | 業種平均(情報・通信業) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 2.7% | 10.68% | -7.98pt |
| 総資産経常利益率 | 2.7%(経常利益396,762千円 ÷ 総資産14,457,273千円) | 5.45% | -2.75pt |
| 売上高営業利益率 | 約7.5%(営業利益≒経常利益と近似) | 11.36% | -3.86pt |
| 自己資本比率 | 85.9% | 32.89% | +53.01pt |
| 配当性向 | 47.0% | 37.14% | +9.86pt |
| 純資産配当率(DOE) | 約1.0%(配当総額÷純資産) | 3.45% | -2.45pt |
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
ZenkénのROEは 2.7% と業種平均 10.68% を大きく下回っています。ROEは株主資本をどれだけ効率的に利益に変えているかを示す指標です。低ROEは「株主から預かった資本を十分に活用できていない」ことを意味し、収益力の課題が浮き彫りです。要因としては、過去の子会社売却による売上規模縮小や、海外人材事業がまだ本格的に利益貢献できていない点が挙げられます。長期投資家にとっては、この数値が改善するかが重要な注目ポイントです。
2. 総資産経常利益率
Zenkénの総資産経常利益率は 2.7% で、業種平均 5.45% の半分程度にとどまります。総資産に対してどれだけ利益を生んでいるかを測るこの指標は、企業全体の効率性を表します。Zenkénは自己資本比率が高く財務的には健全ですが、その分、利益を生む力が弱いことが数値に表れています。つまり「守りは強いが攻めが弱い」状態であり、今後の海外人材事業の拡大でどこまで改善できるかが課題です。
3. 売上高営業利益率
Zenkénの売上高営業利益率は 約7.5% と試算され、業種平均の 11.36% を下回ります。売上に対してどれだけ営業利益を残せるかの指標であり、同業他社と比べると収益構造に改善の余地が大きいといえます。マーケティング事業の価格競争やSEO依存リスク、海外人材事業の初期投資負担などが要因と考えられます。長期的には人材事業の黒字化や、不動産事業の安定収益を活かすことで改善余地があると見込まれます。
4. 自己資本比率
Zenkénの自己資本比率は 85.9% と、業種平均 32.89% を大幅に上回ります。これは極めて健全な財務体質を示し、倒産リスクが低いことを意味します。長期配当を重視する投資家にとっては、大きな安心材料といえます。ただし、資本を厚く抱え込みすぎることは「効率的に活用できていない」とも解釈され、低ROEと表裏一体です。今後は余剰資本を成長投資や株主還元に活かせるかが問われます。
5. 配当性向
配当性向は 47.0% と、業種平均 37.14% より高い水準にあります。これは利益の半分近くを株主に還元していることを意味し、株主還元姿勢は強いと評価できます。一方で、利益が大きく減少した場合には減配リスクも高まる点には注意が必要です。過去の実績でも2022年の20円から、2025年には13円まで減配していることから、安定的に増配を続ける企業とは言い切れません。ただし中期経営計画で「累進配当」を掲げており、今後の改善に期待が持てます。
6. 純資産配当率(DOE)
純資産配当率は 約1.0% と、業種平均の 3.45% に比べて低水準です。DOEは企業がどれだけ資本を活かして株主に還元しているかを示す指標であり、ここでも「資本を遊ばせている」状況が浮かび上がります。自己資本比率の高さと裏腹に、株主への還元効率が低いことを意味します。累進配当方針のもとでDOEを意識した還元に転じれば、株主リターンの向上余地は大きいと考えられます。
配当方針と今後の展望
配当方針の概要
Zenkén株式会社は、株主還元を経営の最重要課題の一つと位置づけています。これまでの基本方針は「業績・財務健全性・将来の事業展開に必要な内部留保」を総合的に勘案し、年間配当性向40%程度を基準に安定的な配当を実施するというものでした。
2025年度の期末配当は1株当たり13円(配当性向46.1%)と決定され、内部留保資金は今後の事業展開に備える形で活用されています。
さらに注目すべきは、2026年6月期から適用される新たな配当方針が2025年8月14日の取締役会で決議された点です。
新しい配当方針「累進配当」
新たな方針では、原則として減配は行わず、配当の維持または増配を実施する「累進配当」を基本としています。具体的には以下の基準が示されています。
- DOE(純資産配当率)2.5%
- 連結配当性向50%
このいずれか高い方を基準として配当を行うと明記されています。
また、特別利益や特別損失の影響を除外して配当金額を決定する場合があること、さらに企業買収等で株主資本に大きな変動があれば、配当基準を見直す柔軟性も盛り込まれています。
今後の配当予想
今回の方針変更に伴い、2026年6月期の年間配当予想は1株当たり26円とされています。これは、DOE2.5%を基準とした結果であり、配当性向91.6%という高い水準に相当します。
つまり、Zenkenは「利益の多寡にかかわらず、株主に安定的・積極的に還元する姿勢」を強調したことになります。これまで減配の局面もあった同社にとって、大きな方針転換です。
投資家にとっての意味
- 安定性の向上
「減配しない」という累進配当方針は、配当を生活資金やFIRE戦略に活用する個人投資家にとって安心感を与えます。 - 還元率の強化
DOEと配当性向を基準にすることで、資本効率と利益還元の両面をカバー。特に自己資本比率が高いZenkénにとって、DOE基準の導入は株主還元の拡大につながります。 - リスクへの配慮
特別損益やM&Aなど例外的要因を排除できる仕組みは、配当の安定性を高める工夫といえます。 - 将来性とのバランス
一方で、配当性向91.6%という数字は利益の大半を株主に還元することを意味し、成長投資の原資をどこまで確保できるかという課題も残ります。海外人材事業やM&A投資を柱に掲げる同社にとって、今後は「成長と還元の両立」が大きなテーマになるでしょう。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
Zenken株式会社は、長期投資による長期配当を狙う個人投資家にとって「中立的な選択肢」と位置づけられます。他の日本株と比較すると、安定性と還元姿勢は高く評価できるものの、収益力や成長性の点で課題が残るため、総合評価は★3つとしました。
まずポジティブな側面として、Zenkenは自己資本比率85%超という非常に強固な財務基盤を有しており、日本株全体と比較しても屈指の安定性を誇ります。倒産リスクが極めて低いため、長期投資家にとって「安心して保有できる銘柄」であることは確かです。また、2026年6月期から導入する「累進配当方針」は、原則として減配を行わないことを明言しており、これは配当金を生活資金やFIRE戦略に充てたい個人投資家にとって極めて大きなメリットです。他の日本株でも累進配当を採用する企業は増えていますが、中堅規模の企業でここまで明確に方針を打ち出す例はまだ少なく、株主還元姿勢の強さは高く評価できます。
一方で、懸念点もあります。まず、ROEや売上高営業利益率などの収益性指標が業種平均を大きく下回っている点です。具体的にはROEが2.7%程度にとどまり、情報・通信業の平均である10%超との差は歴然としています。これは「資本を効率的に活用できていない」ことを意味し、株主価値の向上余地が大きい反面、現状では物足りなさが残ります。また、累進配当を掲げながらも、2026年の配当予想は1株当たり26円(配当性向91.6%)と極めて高い還元率に設定されており、利益変動が続けば将来的に成長投資余力を削ぐリスクも懸念されます。例えば、海外人材事業の拡大やM&A戦略に必要な資金をどこまで確保できるかは注視が必要です。
他の日本株、特に大手総合商社や通信大手などと比較すると、Zenkenの配当利回りや方針の明確さは魅力的ですが、利益規模や安定性の点ではまだ劣後します。総じて、「安定した財務+明確な配当方針」という強みと、「低収益性+成長余力不足」という弱みが混在する銘柄であり、リスクとリターンを天秤にかける必要があります。
結論として、Zenkenは「安定配当を重視する投資家」にとって中堅株の中では有力な選択肢の一つですが、日本株全体の中で突出して魅力的かと問われると、現時点では中立的な評価にとどまります。したがって、レーティングは★3つとしました。