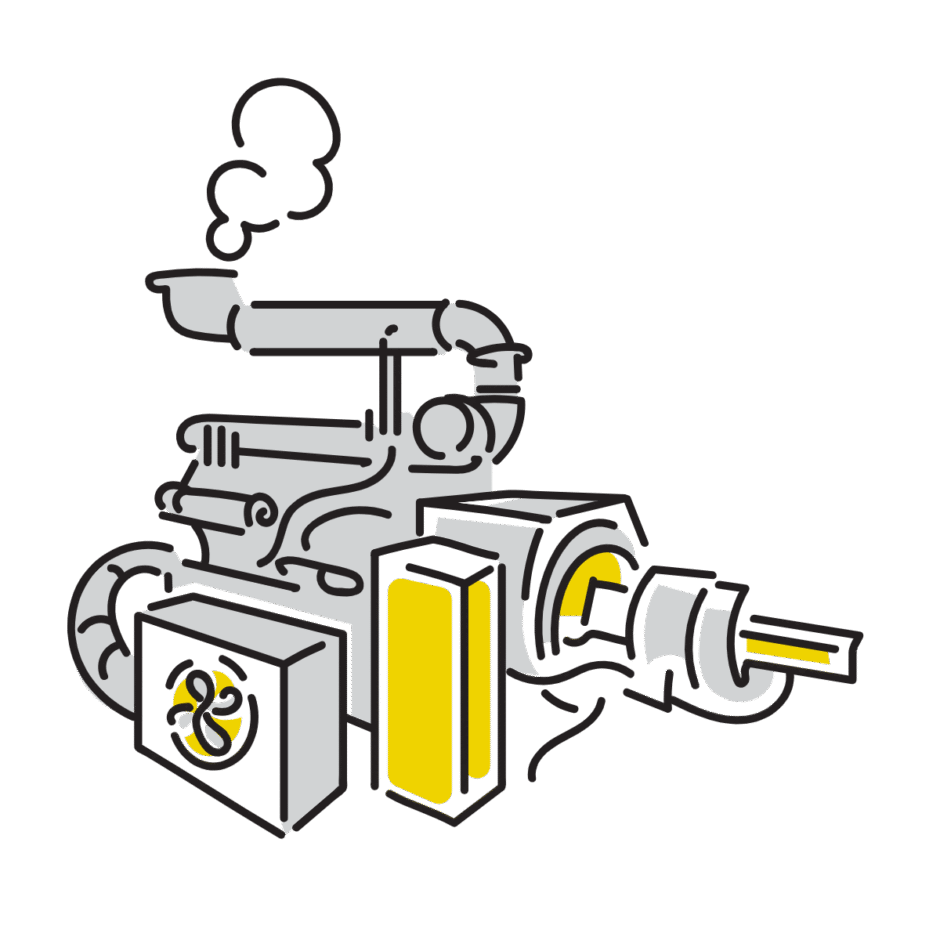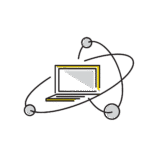企業概要
事業内容とリスク
サムコ株式会社(京都市伏見区)は、半導体および電子部品製造装置を手がける京都発の装置メーカーです。主力は「薄膜技術」に基づく CVD(化学気相成長)装置、エッチング装置、洗浄装置 の3分野で、これらはいずれも半導体チップや電子部品の製造工程で不可欠な役割を果たしています。
主な製品と用途
- CVD装置:反応性ガスを基板上で化学反応させて薄膜を形成する装置で、半導体や電子部品の基礎層形成に利用されます。同社独自の「LS-CVD」では液体原料を使用し、安全性と均一性を両立。また、近年注目される「ALD(原子層堆積装置)」もCVD技術の延長線上で開発しています。
- エッチング装置:薄膜を微細加工する装置。サムコの「トルネードICP」技術により高密度プラズマを安定生成し、高速・高精度な加工を可能にしています。
- 洗浄装置:プラズマやオゾンを用いたドライ洗浄を行う装置で、ウェット洗浄では難しい超精密洗浄を実現。環境にも優しく、同社の「Aqua Plasma」は水蒸気を活用する独自方式で注目されています。
用途面では、化合物半導体(GaN、SiCなど)、シリコン半導体、MEMS・センサー、医療デバイスなど幅広く対応。特に化合物半導体やパワーデバイス分野では、AI・電動車・5Gなどの新産業トレンドとともに成長が見込まれています。
経営理念と方針
同社の理念は「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」。研究開発型企業として、顧客ニーズに応じた製品をタイムリーに供給する直販体制を重視しています。また、ESG委員会を設置し、省エネ設計や温室効果ガス削減など、サステナビリティ経営にも積極的に取り組んでいます。
主なリスク
- 市場変動リスク:半導体業界の設備投資動向に強く影響されるため、需要変動による業績ブレが発生しやすい。
- カントリーリスク:米中関係や地政学リスクによる海外販売の不確実性。
- 部品調達リスク:一部部品は供給元が限られており、災害や倒産による影響を受ける可能性。
- 人材リスク:高度技術人材の採用・育成が業績拡大の鍵。
- 環境・品質リスク:環境法令対応や製品トラブル時の責任リスクにも注意を払っています。
今までの業績
過去5年間のサムコの業績は、安定した右肩上がりの成長を示しています。2025年7月期(第46期)の売上高は約93億円、経常利益は約23億円と、前期比13.9%増・13.6%増を達成しました。以下に主要指標の推移を整理します。
| 決算期 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株配当(円) | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月期 | 5,747 | 1,045 | 756 | 30 | 8.3 |
| 2022年7月期 | 6,402 | 1,481 | 1,053 | 35 | 10.8 |
| 2023年7月期 | 7,831 | 1,927 | 1,366 | 45 | 12.9 |
| 2024年7月期 | 8,203 | 2,089 | 1,472 | 45 | 12.6 |
| 2025年7月期 | 9,342 | 2,373 | 1,697 | 60 | 13.1 |
業績の背景
- エッチング装置の好調:AI・データセンター関連需要の拡大で、化合物半導体やマイクロLED向け販売が伸長。
- CVD装置の堅調:シリコンフォトニクス(光通信技術)向け需要が支え。
- 洗浄装置の復調:医療・ヘルスケア分野での需要増。
- 部品・メンテナンス収益:ストック型収益として安定成長中。
国内売上が前年比30.6%増の57.5億円と大幅に伸びた一方、海外売上はわずかに減少(−5.5%)しましたが、受注残は依然5,000百万円超と高水準。研究開発投資を維持しながらも、高収益体制を確立しています。
また、自己資本比率は76%台と財務の健全性が高く、現金・預金残高は約50億円に達しました。配当も連続増配傾向にあり、2025年は1株あたり60円を予定しています。配当性向は約28%で、余裕を持った還元方針です。
今後の業績
2025年から始まる新中期経営計画(第47期~第49期)では、以下の重点施策が掲げられています。
1. 新プロセス・新装置の開発
AI・電動車・6Gなど、次世代市場の拡大を見据えて、化合物半導体・電子部品向けの新装置を開発。独自の材料やプロセスを活かした差別化を強化します。研究開発費も継続的に増加させる見込み。
2. 生産機販売の強化
これまで研究開発向け装置が中心でしたが、今後は量産ライン向け装置(生産機)に注力。アフターサービス(部品・メンテナンス)とのシナジーで継続的な収益基盤を拡大します。
3. 海外販売比率50%へ
北米・台湾・中国・韓国に加え、欧州・インド市場への進出を計画。現地サービス要員を増強し、海外売上比率を50%以上に引き上げることを目指します。
4. 生産体制・人材投資
2025年9月に新設した「先端技術開発棟」を活用し、製造工程の効率化と研究開発強化を推進。生産能力を増強しながら、人材育成にも注力。特に理系女性・外国籍人材の採用を拡大し、多様性と技術革新の両立を目指します。
5. サステナビリティ経営
ESG委員会を中心に、温室効果ガス削減やエネルギー効率化を進め、装置の小型化・省電力化を実現。環境負荷の少ない製造を通じて、顧客企業の脱炭素化にも貢献します。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標名 | サムコ株式会社(2025年7月期) | 業種平均(機械) | 差異(ポイント) | コメント概要 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 13.1% | 9.22% | +3.88 | 高収益体質。利益率・資本効率ともに業界平均を上回る。 |
| 総資産経常利益率 | 13.4%(推定) | 7.0% | +6.4 | 総資産を効率的に活用しており、設備投資の成果が顕著。 |
| 売上高営業利益率 | 25.1%(経営計画目標)/実績16.1% | 9.68% | +6.4(実績) | 高付加価値製品による利益率の高さが特徴。 |
| 自己資本比率 | 76.3% | 51.76% | +24.54 | 無借金経営に近く、財務の安定性が極めて高い。 |
| 配当性向 | 28.4% | 39.47% | −11.07 | 再投資を重視する健全な水準。増配余地も十分。 |
| 純資産配当率(DOE) | 4.0%(算定値) | 3.52% | +0.48 | 安定した還元を維持しつつ成長性も確保。 |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE) ― 13.1%(業種平均9.22%)
ROEは「株主資本をどれだけ効率的に利益に変えているか」を示す指標であり、一般的に10%を超えると優良企業とされます。サムコのROEは13.1%と、機械業種平均の9.22%を約4ポイント上回っています。
この高いROEの背景には、営業利益率の高さと効率的な経営資本の運用があります。サムコは装置メーカーとしては珍しく、研究開発投資を維持しながらも高い利益率を実現しています。これは、直販体制による顧客対応力や、化合物半導体分野における独自技術による高付加価値ビジネスが寄与していると考えられます。
株主視点では、ROE13%超は安定的な収益性の証左であり、自己資本を過剰に積み上げるのではなく、必要な範囲で投資と還元を両立している健全なバランスといえます。
② 総資産経常利益率 ― 約13.4%(業種平均7.0%)
総資産経常利益率は、会社全体の資産をどれだけ効率的に利益に結びつけているかを示す指標です。業種平均7%に対し、サムコは約13.4%とほぼ倍近い効率性を誇ります。
この背景には、同社の生産体制が「ファブレス(製造委託)」に近い構造であることが挙げられます。自社工場を持たず設計・開発に注力し、製造は協力企業に委託しているため、資産規模のわりに収益効率が高いという特徴があります。また、海外販売網の拡大によって受注残高が安定しており、稼働率の高い生産体制が利益率を押し上げています。
この水準は、装置メーカーとしては非常に高く、業界内でもトップクラスの資産効率といえます。
③ 売上高営業利益率 ― 実績16.1%(業種平均9.68%)
営業利益率とは、売上から本業のコストを差し引いた後の利益率です。サムコは2025年7月期で16.1%を記録し、業種平均の約1.6倍。中期経営計画では「25%超」を目標として掲げており、さらなる改善を狙っています。
装置メーカーの中には価格競争にさらされる企業も多いなか、サムコは独自技術を武器に高付加価値型の受注構造を確立しています。研究用途や少量多品種のカスタム製造に強みを持つため、価格競争力よりも「技術優位性」で利益を確保する戦略が奏功しています。
今後もAI・6G・化合物半導体向けの新装置需要が継続すれば、目標の25%営業利益率も現実味を帯びるでしょう。
④ 自己資本比率 ― 76.3%(業種平均51.76%)
自己資本比率は、総資産のうち自己資本(純資産)が占める割合を示す安全性の指標です。サムコの76.3%は非常に高く、一般的な製造業の水準(40〜50%台)を大きく上回ります。
この水準は、無借金経営に近い財務体質を意味します。実際、同社の総資産約178億円のうち、約136億円が自己資本で構成されており、外部借入に依存しない経営基盤を確立しています。
この安定性は、研究開発型企業としてのリスク耐性を高める一方で、資本効率の観点からはやや保守的とも言えます。ただし、技術開発の長期性や景気循環の影響を受けやすい業界特性を考慮すれば、この「厚い自己資本」はむしろ戦略的な強みといえるでしょう。
⑤ 配当性向 ― 28.4%(業種平均39.47%)
配当性向は「純利益のうち配当に回す割合」を表す指標です。サムコは28.4%と業種平均より約11ポイント低い水準にありますが、これは成長投資を重視する姿勢の表れと見ることができます。
直近5年間で1株あたり配当は30円 → 60円へと倍増しており、株主還元の意識は明確に高まっています。一方で、利益の7割以上を内部留保・研究開発投資に回している点は、研究開発型企業として理にかなった方針です。
特に、次世代装置やAI半導体関連への投資余力を確保しておくことで、中長期的な企業価値向上につながると考えられます。
⑥ 純資産配当率(DOE) ― 約4.0%(業種平均3.52%)
DOEは株主資本に対する配当額の割合で、企業の「配当の安定性」を測る指標です。サムコのDOEは約4.0%で、業種平均をやや上回っています。
配当性向が低めでもDOEが高いのは、同社の純資産が増加し続けているためです。つまり、増益とともに配当も着実に増やしている構造です。2025年7月期には1株60円(前年比15円増配)を予定しており、今後も持続的な増配が期待されます。
ROE13%・DOE4%のバランスは、成長企業としては理想的な水準といえます。利益の一部を株主還元に回しつつ、残りを再投資して将来の成長を支えるという、長期的な経営の安定性を示しています。
配当方針と今後の展望
現行の配当方針の特徴
同社の配当方針には、次の3つの特徴が見られます。
- 安定配当の維持
設備投資や研究開発に必要な内部留保を確保しながらも、株主への安定的な還元を継続するという方針を明示しています。半導体装置メーカーという技術集約型産業では景気の波に影響を受けやすいものの、利益水準に応じて柔軟に対応できる仕組みをとっています。 - 業績連動型の考え方を併用
「余剰資金については業績連動的な配当の考え方を取り入れている」と明記されており、業績が好調な年度には積極的な配当増額を行う姿勢を示しています。実際、2025年7月期の配当は前期比で15円増配の1株60円とされ、好調な収益を背景に還元強化が行われています。 - 期末配当を基本としつつ中間配当も検討
これまでサムコは年1回の期末配当を基本としてきましたが、「取締役会の決議により毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる」と定款に定めており、利益水準が安定すれば中間配当の実施を視野に入れている点も特徴です。
過去数年間の配当推移
| 決算期 | 1株当たり配当金 | 配当総額(千円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年7月期 | 35円 | 約281,000 | 収益拡大局面での増配 |
| 2023年7月期 | 45円 | 361,459 | 前期比+10円の増配 |
| 2024年7月期 | 45円 | 361,459 | 安定配当維持 |
| 2025年7月期 | 60円 | 481,944 | 前期比+15円の大幅増配 |
このように、直近4期で配当は連続して増加または維持されており、配当方針が実際の経営成果と連動していることが確認できます。
内部留保と投資戦略のバランス
同社は報告書の中で、内部留保について「今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える技術・製品開発体制を強化し、グローバル戦略展開のために有効投資していく」と明言しています。
つまり、内部留保は単に資金を蓄える目的ではなく、研究開発や新市場参入に向けた再投資の原資として機能しています。この姿勢により、配当金を確保しながら成長投資を継続する「攻守両立型」の経営方針が形成されています。
財務体質と配当余力
サムコの自己資本比率は76%超と極めて高く、借入依存度が低いのが特徴です。このため、配当を行っても財務の安定性を損なうリスクが少ないといえます。
また、キャッシュ・フロー計算書では、現金および現金同等物の残高が50億円超に達しており、潤沢な流動資金が確保されています。この資金余力が、安定配当の裏づけとなっています。
中期経営計画との整合性
中期経営計画(第47期~第49期)では、「装置製造原価率45%未満」「売上高営業利益率25%以上」を目標としており、収益性のさらなる向上を掲げています。
この計画においても「適切な利益配分により企業価値の向上を目指す」と明記されており、経営方針の一貫として配当政策が位置づけられていることがわかります。
業績改善が続けば、業績連動型配当の方針に基づき、今後も緩やかな増配傾向が期待される構造といえるでしょう。
今後の配当方針の展望(予測)
ここでは、報告書の内容および同社の経営姿勢をもとに、今後の配当方針がどのように推移するかを、一般的な見通しとして整理します。
1. 安定配当を基軸とした「漸進的増配」路線の継続
サムコは、長期にわたる安定配当を重視しており、景気変動の激しい装置産業においても一定の水準を維持する方針を貫いています。今後も「基礎配当を維持し、業績に応じて上乗せする」スタイルが続くと考えられます。
近年の利益成長が継続する限り、1株あたり配当金は60円を基準に据え、70~80円台への段階的上昇が視野に入る可能性があります。
2. DOE(純資産配当率)重視へのシフト
中長期的には、単純な配当性向(純利益に対する割合)だけでなく、株主資本に対してどれだけ還元しているかを示すDOE(純資産配当率)を重視する傾向が強まると予想されます。
自己資本が厚い同社では、ROEとDOEをバランス良く管理することで、「成長性と安定性を両立した株主還元モデル」を構築できる余地があります。
3. 中間配当の実施可能性
同社定款上は中間配当を行うことが可能であり、利益平準化が進めば、年2回配当体制(中間+期末)への移行も選択肢となるでしょう。
特に、AI・電動車・6G通信などの成長市場で収益が安定すれば、早期の実現が期待されます。
4. 自己株式取得の活用
現状、保有自己株式は約1万株と少数ですが、キャッシュ余力を活かした自己株式取得(自社株買い)の可能性もあります。自社株買いは配当とは異なる形で株主価値を高める手段であり、財務余力が十分な同社では有効な選択肢のひとつです。
5. 研究開発・投資との両立
配当水準を上げつつも、同社は「技術革新を止めない」姿勢を明確にしています。特に、化合物半導体装置やMEMS、医療デバイス向けの新技術開発に継続投資することで、中長期的な利益成長を支える基盤が整っています。したがって、配当を増やしながらも企業の成長性を損なわない堅実な政策が維持されると考えられます。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
サムコは、高配当株というより「持続的成長+安定配当」を狙える企業です。
配当性向は28.4%と無理のない水準であり、ROE(自己資本利益率)13%台という高収益体質を維持している点も強みです。
また、研究開発志向の強い企業でありながら、利益の一部を確実に株主に還元するバランス感覚は、他の日本株と比較しても際立っています。
ただし、半導体製造装置という業界特性上、景気循環や海外需要の変動によって利益が上下する可能性がある点は注意が必要です。
それでも、同社は装置の多品種展開とメンテナンス事業によるストック型収益を強化しており、配当維持力では日本株の上位3割程度に位置すると評価できます。
以上を踏まえ、サムコ株式会社は「長期保有で安定配当を得たい投資家」にとって、
星4つ(★★★★☆)の信頼度を持つ中堅優良銘柄といえるでしょう。
(本記事は投資助言を目的としたものではなく、企業方針および財務データに基づく一般的な分析です。)