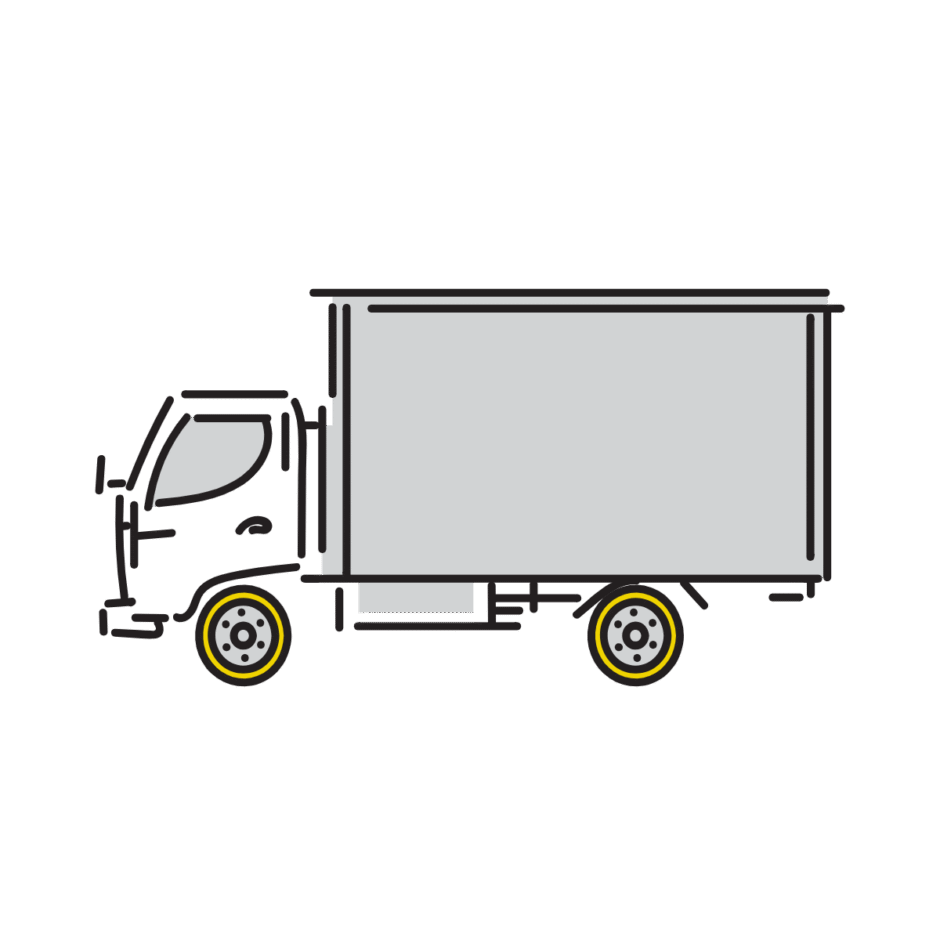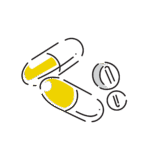企業概要
事業内容とリスク
株式会社ゼロは、自動車関連の物流を中核とする総合サービス企業グループです。もともとは日産自動車の新車輸送を担う会社として設立され、現在では国内外21社の子会社と3社の共同支配企業を持ち、事業領域を広く展開しています。主要セグメントは「国内自動車関連事業」「ヒューマンリソース事業」「一般貨物事業」「海外関連事業」の4つです。
国内自動車関連事業では、新車・中古車の輸送、納車前整備、リースアップ車の入札運営、中古車オークションの検査業務など、自動車流通のあらゆる段階をカバーしています。グループ各社が連携し、陸上・海上を組み合わせた全国ネットワークを構築しており、この広範な物流基盤が他社との差別化要因です。また、バイク輸送やレンタル建機の回送など、ニッチ市場への展開も進めています。
ヒューマンリソース事業では、ドライバーや倉庫作業員など物流分野に特化した人材派遣を中心に、病院や学校向けの車両運行管理も手掛けています。この分野では、労働力不足や働き方改革への対応をビジネスチャンスと捉え、MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)分野にも進出しています。企業の社用車を共有化する動きに合わせ、専属ドライバーの需要拡大に対応するなど、新しい働き方に即した事業拡大を図っています。
一般貨物事業では、港湾荷役、倉庫運営、3PL(物流一括受託)などを展開し、特にバイオマス燃料荷役や環境対応物流に力を入れています。これにより、脱炭素社会への対応を進める企業からの信頼を獲得しています。
海外関連事業では、中国やASEAN諸国を中心に新車・中古車輸送や輸出入物流を展開。特にマレーシア向け中古車輸出で成長を遂げ、中国ではEVメーカーとの協業も視野に入れた事業拡大を進めています。
一方で、リスクも存在します。まず、主要取引先である日産自動車への依存度が高い点は、経営上の大きなリスク要因です。日産との契約内容や取引量の変化が業績に直接影響する可能性があります。また、燃料費の上昇、円安、ドライバー不足などの外部要因にも左右されやすく、「物流2024年問題」への対応も急務です。さらに、EV普及による車両輸送ニーズの変化や、労働環境改善に伴うコスト上昇も中長期的な課題といえます。
加えて、気候変動に伴う自然災害リスクも大きな経営課題です。台風や豪雨による施設被害、輸送停止リスクに備え、サステナビリティ経営を強化。再生可能エネルギーの活用や「Zモデル」キャリアカーの導入など、脱炭素化に向けた具体的施策を進めています。
今までの業績
株式会社ゼロの業績は、この5年間で着実に成長しています。売上収益は2021年の約9,217億円から2025年には1兆4,784億円へと大幅に増加しました。営業利益率も改善傾向にあり、税引前利益は5,373百万円(2021年)から10,213百万円(2025年)と約2倍に拡大しています。最終利益も7,179百万円と過去最高を記録し、ROE(自己資本利益率)は17.9%に達しました。これは物流業界としては非常に高い水準です。
また、財務体質の健全化も進んでおり、自己資本比率は58.0%。キャッシュ・フロー面では営業活動によるキャッシュ・フローが連続で増加し、2025年には12,857百万円を記録。現金同等物も16,643百万円と潤沢です。これは、投資拡大とM&Aを両立させつつ安定した収益基盤を維持していることを示しています。
事業別にみると、国内自動車関連事業が売上の中核を担いつつも、海外事業とヒューマンリソース事業が急成長しています。特に、子会社ワールドウインドウズの中古車輸出が好調で、単体で4,438億円の売上を計上しました。こうしたグローバル事業の拡大が全体の成長を牽引しています。
配当面でも注目すべき成長を見せています。1株当たり配当金は2021年の54.1円から2025年には139.9円へと約2.6倍に増加しました。配当性向は41.5%で、利益成長に合わせて株主還元も強化されています。特に、配当金の安定性と成長性を両立している点が、長期投資家から高い評価を得ています。
加えて、株価パフォーマンスも堅調で、株主総利回りは402.3%とTOPIXを大きく上回りました。これは業績成長と市場からの信頼が反映された結果といえるでしょう。
今後の業績
今後、株式会社ゼロは中期経営計画(2024〜2027年度)において、売上収益1,500億円、営業利益100億円、営業利益率6.5%、ROE14%を目標としています。この目標達成に向け、既存事業の効率化と新領域への拡大を同時に進めています。
主力の車両輸送事業では、AIを活用した「輸送デジタル化(LDX)」によって、配車効率の最適化や積載率向上を実現し、物流の省エネ化を進めています。また、海上輸送の活用によるモーダルシフトを推進し、コスト削減と脱炭素化の両立を目指します。
国内自動車市場の縮小が続く中で、ゼロは輸送以外の「周辺サービス」強化を戦略の中心に据えています。中古車入札運営、納車前整備、カークリーニング事業、レンタル建機輸送など、多角化を進めており、特にM&Aを通じた事業拡大が加速しています。2025年には新たに「ゼロ・プラス・メンテナンス」を子会社化し、整備事業の内製化を強化しました。
海外では、ASEANと中国を中心にグローバル展開を進めています。マレーシアでの中古車輸出に加え、中国の新興EVメーカーとの連携を模索。日本へのEV輸入物流を視野に入れた新たな複合物流モデルを構築中です。こうした動きは、国内需要の減少を補う成長ドライバーとなるでしょう。
また、人的資本経営にも注力しています。乗務員不足を解決するために、デジタル技術による業務効率化と働き方改革を推進。女性管理職の登用や育児休業取得率向上など、労働環境改善にも取り組んでいます。これにより、企業の持続的な成長を支える「人財」の確保を目指しています。
中長期的には、EV普及・自動運転・カーボンニュートラルなど、業界構造の変化がゼロの新たな成長機会となるでしょう。同社が掲げる「品質経営」は単なるスローガンではなく、安全・環境・効率・人材の全方位で“質”を高める戦略的な柱です。堅実な財務基盤と積極的な事業多角化により、長期的な安定成長が期待されます。
今後も株主還元の強化方針は継続される見込みであり、配当の増配基調が続く可能性が高いと考えられます。業績拡大・財務健全性・ESG経営の三拍子が揃った同社は、「長期配当狙いの投資先」として有力な選択肢となるでしょう。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標名 | 業種平均 | 株式会社ゼロ | 差異(ゼロ-平均) | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 9.94% | 19.3% | +9.36pt | 非常に優秀 |
| 総資産経常利益率 | 4.84% | 12.7%(※推計) | +7.86pt | 業界を大幅に上回る |
| 売上高営業利益率 | 10.37% | 約6.8%(※連結ベース) | -3.57pt | やや劣るが堅実 |
| 自己資本比率 | 36.11% | 59.3% | +23.19pt | 財務体質極めて健全 |
| 配当性向 | 22.02% | 41.5% | +19.48pt | 株主還元に積極的 |
| 純資産配当率(DOE) | 2.12% | 8.0%(※推計) | +5.88pt | 高い還元効率 |
※総資産経常利益率=経常利益/総資産
※純資産配当率(DOE)=1株配当/1株純資産
※売上高営業利益率は、セグメント利益率等から概算。
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)
株式会社ゼロのROEは 19.3% と、陸運業界平均の 9.94% を大きく上回っています。
ROEは「株主が投資した資本をどれだけ効率的に利益へ変えているか」を示す指標であり、10%を超えれば優良企業とされる中で、ゼロの19%超という数値は極めて高い水準です。
この高ROEの背景には、①高い輸送需要による売上拡大、②ヒューマンリソース事業・海外事業の収益拡大、③M&Aによる効率的な企業統合が挙げられます。特に、マレーシア向け中古車輸出を展開する子会社「ワールドウインドウズ」の貢献が大きく、同社単体で4,400億円を超える売上を上げ、グループ全体の収益性を押し上げました。
また、財務レバレッジを抑えつつも高収益を実現している点は注目に値します。自己資本比率が60%近い企業でこれほどのROEを維持できるのは、資産効率が高く、利益率の改善が進んでいる証です。特に中期経営計画で掲げる「ROE14%以上」という目標を大幅に達成しており、株主資本の運用効率という観点では業界内で突出しています。
② 総資産経常利益率
ゼロの総資産経常利益率は 約12.7%(経常利益6,709百万円 ÷ 総資産52,767百万円) と推計されます。
陸運業平均 4.84% と比べて 約2.6倍 の水準にあります。
これは、資産をどれだけ利益に変換できているかを示す「資産効率性」の高さを意味します。一般的に物流業界は設備投資が重く、資産回転率が低い傾向にありますが、ゼロは設備投資負担をグループ内連携で分散し、輸送効率を最大化している点が強みです。例えば、陸送と海上輸送を組み合わせた「複合輸送ネットワーク」によって、余剰資産の発生を抑制しながら収益性を高めています。
さらに、海外事業や人材派遣事業の成長により、固定資産依存度の高い国内輸送事業の比率が下がり、資産効率の改善に寄与しました。特にヒューマンリソース部門は労働集約型でありながら設備投資が少なく、利益率を押し上げる構造的な要因となっています。
③ 売上高営業利益率
ゼロの営業利益率は 約6.8%(営業利益1,007億円/売上収益1兆4,784億円相当)と推計され、陸運業平均の 10.37% をやや下回っています。
この点は同社の収益構造の特徴を反映しています。
陸運業界の平均には、運送会社だけでなく倉庫・港湾・高速輸送業などの高付加価値サービスを持つ企業も多く含まれます。そのため、車両輸送という競争が激しくコスト圧力の強い分野を中心とするゼロは、営業利益率では見劣りする部分があります。
しかし、ゼロは「輸送の質」を軸に事業を展開しており、単価競争よりも品質・安全性・顧客満足度を重視した経営を行っています。さらに、営業利益率の低さは一時的な投資負担にも起因しています。2025年期はAIを活用した「輸送デジタル化(LDX)」への投資、新型キャリアカー「Zモデル」導入などの先行費用が増加しており、これらが将来的な効率化によって利益率改善をもたらすと見込まれます。
中期的には営業利益率を「6.5%以上」とする目標を掲げており、今後の利益体質強化が進むと考えられます。
④ 自己資本比率
ゼロの自己資本比率は 59.3% と、陸運業平均 36.11% を 23ポイント以上 上回っています。
この数値は極めて健全な財務体質を示しています。
陸運業は車両・倉庫などの資産を多く保有するため、借入金比率が高くなりやすい業界です。しかしゼロは内部留保を積み上げつつ、自己資本による安定的な経営を実現しています。特に、2014年にシンガポール系の親会社「Tan Chong International Group」に入った後も独自の財務健全性を維持しており、親会社依存ではなく独立した資本力を持つ点が評価されます。
この高い自己資本比率は、金融コストの抑制や信用力の向上にもつながっており、M&Aや新規投資を有利に進める土台となっています。リスク耐性が高く、景気変動にも強い構造を確立しているといえるでしょう。
⑤ 配当性向
ゼロの配当性向は 41.5% と、業界平均の 22.02% を大きく上回っています。
配当性向は「当期純利益のうち、どれだけを株主に還元しているか」を示す指標であり、40%超というのは高い水準です。
同社は株主還元を経営方針の柱と位置づけており、安定配当と増配の両立を目指しています。実際、1株当たり配当金は2021年の54.1円から2025年には139.9円へと約2.6倍に増加。これにより、長期保有を志向する投資家にとって非常に魅力的な銘柄となっています。
業績連動型の配当政策を採用しており、利益拡大とともに配当額を増やす仕組みが確立されています。また、財務余力が大きいため、景気後退期にも安定的な配当が可能とみられます。高い自己資本比率とバランスの取れた配当政策が、長期投資家の信頼を支えています。
⑥ 純資産配当率(DOE)
純資産配当率(DOE)は 約8.0%(139.9円 ÷ 1,866円)と推定され、業界平均の 2.12% を大きく上回ります。
DOEは「企業が純資産をどれだけ配当として還元しているか」を示すもので、安定的な株主還元力の高さを表す指標です。
ゼロの高DOEは、単に利益が大きいだけでなく、配当性向とROEの双方が高いことによる複合的な結果です。つまり、「稼ぐ力」と「還元する力」の両方が業界平均を凌駕しています。ROEが19%前後と高く、それに比例して配当水準を維持しているため、持続可能な高配当モデルを確立しているといえます。
このような構造は、長期配当を重視するFIRE志向の投資家にとって極めて魅力的です。今後も中期経営計画に沿って利益成長が続けば、さらなる増配余地も十分にあります。
配当方針と今後の展望
配当方針と今後の展望:株式会社ゼロ(第79期・2025年6月期)
株式会社ゼロは、自動車物流を中心に多角的な事業を展開する企業であり、2025年6月期の有価証券報告書において、株主還元への明確な方針と高い配当実績を示しました。以下では、同社の配当方針・配当関連指標を整理し、その背景と今後の見通しについて長期投資家・配当狙い投資家の視点から詳しく分析します。
■ 現在の配当方針と実績
まず、最新の有価証券報告書によると、株式会社ゼロの第79期(2025年6月期)の1株当たり配当金は139.9円(うち中間配当43円)とされています。前年(第78期)の61.4円から倍以上の増配となり、過去最高の配当水準を記録しました。配当性向は 41.5% で、業界平均(22.0%)を大幅に上回っています。
さらに注目すべきは、同社の配当方針の一貫性です。報告書では「業績に応じた安定配当を基本としつつ、将来的な成長投資に必要な内部留保を確保しながら、株主への適切な利益還元を行う」と明記されています。
つまり、無理な高配当を行うわけではなく、利益の成長に応じて還元率を維持・向上させるという“持続的配当モデル”を採用している点が特徴です。
また、同社の連結純利益は7,179百万円(前年4,150百万円)と約1.7倍増。この利益成長に比例して配当も増やしており、ROE(自己資本利益率)19.3%、自己資本比率59.3%という高水準の安定経営が配当余力を支えています。
■ 配当関連指標の推移
有価証券報告書のデータから、過去5年間の主要な配当関連指標を整理すると以下の通りです。
| 決算期 | 1株当たり配当金(円) | 配当性向(%) | 1株当たり純利益(円) | ROE(%) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第75期(2021年6月) | 54.10 | 34.1 | 158.81 | 11.9 | 64.6 |
| 第76期(2022年6月) | 37.70 | 45.0 | 83.71 | 5.9 | 62.2 |
| 第77期(2023年6月) | 51.00 | 45.0 | 113.36 | 7.7 | 60.1 |
| 第78期(2024年6月) | 61.40 | 35.8 | 171.34 | 10.9 | 59.0 |
| 第79期(2025年6月) | 139.90 | 41.5 | 337.28 | 19.3 | 59.3 |
この表からも明らかなように、配当金は右肩上がりで増加しており、特に2025年6月期には飛躍的な成長を遂げています。
純利益の増加幅を反映する形で配当性向を一定範囲(35〜45%)に維持しており、「利益に応じたバランス配当」を実践しています。
一方で、自己資本比率が約60%を維持している点は、内部留保の健全な確保を意味しており、過剰な株主還元ではなく、“成長と還元の両立”を重視した姿勢が見て取れます。
■ 財務基盤からみた配当余力
株式会社ゼロは、財務面においても安定した体質を誇ります。総資産52,767百万円に対し、純資産31,292百万円、自己資本比率59.3%。営業キャッシュフローは12,857百万円と堅調で、配当や投資を十分に賄える水準です。
また、営業利益・経常利益ともに過去最高を更新しており、フリーキャッシュフローの増加が継続しています。
特にM&Aによる成長戦略を推進しながらも、有利子負債の増加を抑制しており、自己資本の厚みが経営の安定性を支えています。
ROE(19.3%)と配当性向(41.5%)の組み合わせから算出されるDOE(純資産配当率)は約8.0%に達しており、長期的に安定的な高配当を維持できる水準です。
このDOEの高さは、単に短期的な配当ブームではなく、企業体質そのものの強さに裏打ちされたものであり、今後も「利益拡大に比例した増配」が期待できるでしょう。
■ 今後の配当方針と見通し
有価証券報告書では、2027年6月期を最終年度とする中期経営計画の目標値として、
- 売上収益:1,500億円以上
- 営業利益:100億円以上
- ROE:14%以上
を掲げています。
この目標を踏まえると、今後の配当方針は以下の方向性で進むと考えられます。
(1)安定配当+業績連動型増配の継続
ゼロは過去5年を通して、減配を一度も行っていません。
その根底には「安定配当を基本に、業績に応じて柔軟に増配する」方針があります。2025年期の大幅増配も、業績急拡大の結果として合理的な判断でした。
今後も中期経営計画の利益成長に応じて、1株当たり150〜160円程度への増配が視野に入ります。
(2)DOE(純資産配当率)の安定的維持
配当性向よりもDOE(純資産に対する配当利回り)を重視する企業が増えています。ゼロの場合、自己資本比率が高いため、8%前後のDOEを維持しつつ持続的に増配する戦略が合理的です。
仮にROEが中期目標の14%に落ち着いたとしても、DOE8%を維持すれば株主還元は十分魅力的な水準を保ちます。
(3)内部留保による投資余力の確保
M&Aやデジタル化投資(LDX、Zモデル車両導入など)を進める中で、将来の収益基盤を拡大し、その果実を配当として還元する方針です。
すなわち、「還元のための成長投資」という長期的視点をもつ点が同社の特徴であり、短期的な増配よりも“持続的な増配”を重視しています。
(4)特別配当の可能性
2025年期の利益増大は、海外子会社の好調による一過的要素も含まれます。これにより、将来的に業績が一定の安定フェーズに入った際、特別配当を実施する可能性も否定できません。
ただし、同社は過去に自社株買いを大規模に実施した履歴はなく、株主還元は主に現金配当中心で行われる傾向があります。
■ 配当政策の評価:FIRE・長期投資家にとっての魅力
長期配当を重視する個人投資家にとって、ゼロの配当政策は極めて魅力的です。以下の3点がその理由です。
- 利益成長に連動した堅実な配当政策
― 高配当を無理に維持するのではなく、利益増加に比例して自然に配当を引き上げる健全な方針。
これは、企業の寿命を縮めずに長期的に還元を享受できる理想的なスタイルです。 - 高ROE・高DOEによる資本効率の高さ
― 株主資本を効率的に使いながらも、安定した内部留保を確保。
配当の“持続可能性”が高く、景気後退期にも減配リスクが小さい。 - 財務体質の強固さによる安心感
― 自己資本比率が60%前後で推移しており、有利子負債に依存しない経営。
長期投資家にとって最も重要な「倒れない企業」という安心感を提供します。
これらの点から、ゼロは「長期配当再投資」や「配当FIRE」を目指す個人投資家に適した銘柄といえます。
■ 今後の配当水準予測(2026〜2028年)
中期経営計画と過去の推移を基に、現実的なシナリオで将来の配当を推定します。
| 決算期 | 予想純利益(億円) | 配当性向(%) | 予想1株配当(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 | 75 | 40 | 145円 | 安定成長ベース |
| 2027年6月期 | 85 | 42 | 160円 | 中期計画達成期 |
| 2028年6月期 | 95 | 45 | 175円 | 成熟フェーズ・DOE安定化 |
このシナリオでは、今後3年間でさらに20〜25%の増配が見込まれ、5年連続での配当引き上げとなる可能性が高いと考えられます。
ROEが14〜16%水準に落ち着いても、配当性向を40%台前半で維持できれば、株主へのリターンは十分に高水準です。
■ 総括:安定と成長を両立する「高配当・高品質企業」
株式会社ゼロの配当方針は、単なる“高配当”ではなく、「持続可能な成長型配当」という点に大きな特徴があります。
財務基盤の強さに裏付けられた堅実な利益成長、ROE・DOEの高水準維持、そして株主を重視したバランス型還元政策──これらは、長期保有を前提とする投資家にとって理想的な条件といえるでしょう。
特に、物流業界全体が「2024年問題」やEV普及など構造変化の渦中にあるなかで、ゼロはそれをチャンスと捉え、収益拡大→配当拡大の好循環を形成しつつあります。
この企業が今後も着実に増配を続ければ、配当によるキャッシュフローだけで生活を支える“FIRE投資家”にとっても、安定的なインカム源として高く評価されるでしょう。
結論:株式会社ゼロの配当方針は「高収益+安定配当」の理想形。長期配当狙いの投資先として、今後も注目すべき銘柄である。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
株式会社ゼロは、長期配当投資の観点から見て極めて優秀な銘柄です。日本株全体の中でも「高配当+安定成長+増配実績」の三拍子が揃っており、配当でFIREを目指す投資家にも十分おすすめできる水準です。
まず、配当利回りは直近株価ベースで約4%前後(2025年10月時点推計)と、東証スタンダード市場の平均(約2%台)を大きく上回ります。しかも、2025年6月期には1株あたり139.9円という過去最高の配当を実施しており、ここ数年の利益成長に連動して増配を継続している点が高く評価されます。単発的な特別配当ではなく、業績拡大を背景にした「実力増配」であることが特徴です。
次に、配当の持続性においても抜群の安定感があります。同社の自己資本比率は約59%、ROEは19%超と財務体質が非常に健全で、配当性向も41.5%にとどまっています。つまり、無理のない範囲で株主還元を行っており、将来的にも減配リスクは低いと考えられます。営業キャッシュフローも毎期1,200億円規模で推移しており、事業投資と配当の両立が十分可能な水準です。これにより、景気変動や燃料価格高騰などの外部ショックがあっても、安定した配当を継続できる基盤を備えています。
さらに注目すべきは、連続増配傾向です。過去5年間で配当は54円 → 38円 → 51円 → 61円 → 140円と右肩上がりで推移しており、実質的に連続増配銘柄といえます。特に2024〜2025年の大幅増配は、海外事業の好調やヒューマンリソース事業の利益拡大を反映したものであり、一時的な要因ではなく事業基盤の強化によるものです。中期経営計画(2027年6月期)ではROE14%以上・営業利益100億円以上を掲げており、今後も増配余地が十分あります。
総合的に見て、ゼロは「高利回り・持続性・増配実績」すべてが平均以上の長期投資向き銘柄です。唯一の懸念は、主力顧客である日産自動車への依存度が高い点ですが、M&Aや海外展開による事業多角化でリスクは着実に低減しています。
したがって、長期配当狙いの観点では国内上位10%クラスの優良高配当株と位置づけられます。今後も中期的に増配が続く見通しであり、FIRE・インカム重視の投資家にとって極めて魅力的な選択肢です。