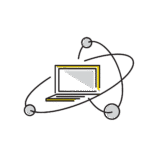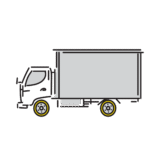企業概要
事業内容とリスク
株式会社ハンズマンは、宮崎県都城市に本社を置くホームセンター企業で、DIY用品・家庭用品・カー・レジャー用品を中心とした商品を取り扱っています。店舗は九州を中心に展開してきましたが、2023年には大阪府松原市に初の本州進出を果たし、今後は大都市圏での出店拡大を見据えています。事業の基本方針は「お客様第一主義」であり、「住まいと暮らしに関するお客様の要望をすべて満たす」ことを掲げています。
一方で、同社が直面するリスクは複数あります。まず、新規出店には「大規模小売店舗立地法」などの法規制があり、地域住民や自治体との調整に時間やコストがかかる可能性があります。また、DIY用品は天候に左右されやすいため、気象条件の悪化が来店客数や売上に影響を与えるリスクも指摘されています。さらに、地震や台風といった自然災害による店舗設備の被害や物流網の途絶も想定されます。固定資産の減損リスクや個人情報流出リスクも、事業継続に対する潜在的な不安要素となっています。
投資家にとって重要なのは、同社が安定したキャッシュフローを維持しつつ、こうしたリスクにどう対応していくかです。特に大都市圏での出店は成長のチャンスである一方で、競争が激化する市場環境において収益性を確保できるかが問われます。
今までの業績
直近5年間の業績をみると、売上高は2021年の340億円から2025年には349億円へと増加しています。大きな伸びはないものの、安定した売上基盤を維持しています。一方で、経常利益は2021年の28億円から2024年には10億円まで落ち込みましたが、2025年には15億円まで回復しました。当期純利益も2024年の7億円から2025年には10億円へと改善しています。
自己資本比率は70%台と非常に健全であり、借入依存度の低さが財務の安定性を示しています。ROE(自己資本利益率)は2024年に4.5%まで低下しましたが、2025年には5.7%まで回復しています。これは依然として投資家から見れば物足りない数値ですが、安定配当を志向する個人投資家にとっては安心材料と言えるでしょう。
配当はここ5期連続で1株あたり30円を維持しており、安定性が際立っています。配当性向は2024年に54%まで上昇しましたが、2025年には40%台に改善しました。これは利益の増加に伴い、内部留保とのバランスを取った結果です。
業績面で注目すべきは、2023年にオープンした松原店の寄与です。同店の売上が全体の成長に貢献し、今後の新規出店の試金石となりました。また、DIYアドバイザー資格を持つ従業員を増やし、接客力を強化する取り組みも利益改善に寄与しています。
今後の業績
今後の業績の鍵は、大都市圏での出店戦略にあります。松原店の成功を皮切りに、本州での出店拡大を計画しており、店舗網の拡充が売上の安定成長を支える見込みです。ただし、都市部では競合他社との競争が激しく、既存店の強みである「品揃えの幅」や「接客力」をいかに差別化要因として打ち出せるかが重要です。
また、同社はサステナビリティにも注力しており、全店舗でのLED照明導入や太陽光パネル設置を進めています。これは中長期的にはコスト削減やブランドイメージ向上につながり、投資家にとっては「ESG経営」を評価できるポイントです。
財務目標としては、ROE10%以上を掲げていますが、現状では5%台にとどまっています。今後の新規出店が利益率の改善に直結すれば、この目標に近づく可能性があります。一方で、過度な設備投資による減損リスクや、消費者の節約志向の強まりといった外部環境要因が収益を圧迫する懸念もあります。
配当政策については、今後も「業績連動型でありながら安定的な配当」を基本方針としています。内部留保は新規出店や既存店改装に活用しつつ、株主還元も継続する姿勢を明示しているため、長期投資を志向する個人投資家にとって魅力的です。2025年も1株30円の配当を実施しており、今後も安定配当が期待できます。
総じて、ハンズマンは大きな成長性よりも「安定性」と「配当継続性」に強みを持つ企業です。FIREを目指す投資家にとっては、株価の急騰を狙うよりも、長期的な安定配当を享受する銘柄として検討する価値があります。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | ハンズマン | 小売業平均 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE, %) | 5.7 | 8.85 | ▲3.15 |
| 総資産経常利益率(%) | 5.9 | 5.79 | +0.11 |
| 売上高営業利益率(%) | 3.5 | 4.89 | ▲1.39 |
| 自己資本比率(%) | 70.5 | 37.84 | +32.66 |
| 配当性向(%) | 40.4 | 37.14 | +3.26 |
| 純資産配当率(%) | 2.3 | 3.08 | ▲0.78 |
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
ハンズマンのROEは5.7%で、業種平均の8.85%を下回っています(差異▲3.15ポイント)。ROEは株主資本に対する純利益の割合を示すため、株主から見た資金効率を測る代表的な指標です。ハンズマンは自己資本比率が高いため、借入に依存せず安定的な経営を実現していますが、その一方でレバレッジ効果が働きにくく、資本効率は平均を下回っています。安定性重視の投資家にとっては安心材料である一方、成長性や資本効率を重視する投資家から見ると物足りなさを感じさせる数値です。長期的な視点では、新規出店による収益拡大や効率的な資本活用がROE改善の鍵となります。
2. 総資産経常利益率
ハンズマンの総資産経常利益率は5.9%で、業種平均の5.79%をわずかに上回っています(差異+0.11ポイント)。総資産全体に対する経常利益の割合であり、企業の総合的な収益力を示します。ここでは業種平均と同等水準を維持しており、資産効率の観点からは小売業界全体の標準的なパフォーマンスを確保できているといえます。特に新規出店した松原店の寄与や、既存店の売上高が堅調に推移したことがプラス要因になっています。資産効率が一定以上を維持できている点は、将来の安定配当余力を示す材料と考えられます。
3. 売上高営業利益率
売上高営業利益率は3.5%と、業種平均の4.89%を下回り、差異は▲1.39ポイントです。これは小売業の中ではやや低い水準といえます。営業利益率が低い理由としては、競争激化による価格維持の難しさ、物流コストや人件費の上昇、また松原店の新規出店に伴う初期費用などが考えられます。ただし、営業利益率が低い一方で経常利益率は平均を上回っているため、金融収支やその他の収益改善で全体の収益力は補完されています。投資家にとっては、コスト削減や効率的な経営改善が中長期的な課題であることを示す指標です。
4. 自己資本比率
自己資本比率は70.5%で、業種平均の37.84%を大きく上回っており、差異は+32.66ポイントです。これは同社の最大の強みといえるでしょう。自己資本比率が高いということは、外部借入に依存せず、内部資金で事業を運営できていることを意味します。財務の健全性が非常に高く、長期投資家にとっては「倒産リスクの低さ」という大きな安心材料となります。ただし、逆にいえば過度に安全性を重視しており、成長投資の積極性に欠ける可能性もあるため、安定配当銘柄としての性格が強いといえます。
5. 配当性向
配当性向は40.4%で、業種平均の37.14%をやや上回っています(差異+3.26ポイント)。配当性向が高いことは、株主還元の姿勢を示す一方、内部留保に回せる資金が制限されることも意味します。ただし、同社は自己資本比率が極めて高いため、過度に内部留保を積み上げる必要性は低いと考えられます。そのため、今後も配当性向40%前後を維持しつつ、安定配当を続ける可能性が高いといえるでしょう。長期的な配当収入を目当てにする投資家にとっては、魅力的な還元姿勢です。
6. 純資産配当率
純資産配当率は2.3%で、業種平均の3.08%を下回っています(差異▲0.78ポイント)。純資産配当率は株主資本に対してどれだけの配当を出しているかを示す指標です。ハンズマンの場合、自己資本比率が高いため、母数となる資本が厚く、その分だけ純資産配当率は相対的に低下しています。つまり、株主資本を厚く維持しているがゆえに、還元効率が抑えられている形です。株主にとっては「資本効率よりも安全性を優先する企業」と映るでしょう。今後は内部留保を活用した成長投資や、さらなる配当還元策の検討が求められるかもしれません。
配当方針と今後の展望
配当政策の基本方針
株式会社ハンズマンの有価証券報告書(第61期、2025年6月期)によると、同社は「業績に応じた配当を行うことを基本としつつ、安定的な配当の維持継続に留意する」という方針を採用しています。この配当方針は、単に業績に連動するだけでなく、企業体質の一層の強化や、将来の積極的な事業展開に備える内部留保とのバランスを重視している点が特徴です。つまり、株主還元と成長投資の両立を掲げており、配当だけでなく、長期的に企業価値を高める戦略の一環として位置付けています。
配当実施の形式は「期末配当を基本」としつつ、定款には「中間配当も可能」と規定されています。ただし、現状は年1回の期末配当を継続しており、投資家にとっては配当の予測可能性が高い仕組みとなっています。
最近の配当実績と配当関連指標
第61期において、ハンズマンは1株あたり30円の期末配当を実施しました。その結果、配当性向は40.4%、純資産配当率は2.3%となっています。配当性向は株主への利益還元割合を示し、純資産配当率は自己資本に対する配当水準を表します。これらの水準を踏まえると、同社は「利益の一定割合を株主へ還元しつつ、残りを内部留保として将来の出店や店舗改装に充てる」という、安定的かつ堅実な配当方針を維持していることがわかります。
直近5年間を振り返っても、ハンズマンは毎年1株あたり30円の配当を続けており、安定性は際立っています。この間、当期純利益は789百万円から1,027百万円へと推移しましたが、配当額は一貫して据え置かれています。すなわち、利益が減少しても配当を減額せず、利益が増加しても大幅に引き上げないという「守りの配当政策」を採っているといえるでしょう。
配当政策に関連する指標の分析
ここで、配当関連の主要指標を整理すると次のようになります。
- 配当性向:40.4%
- 純資産配当率:2.3%
- 自己資本比率:70.5%
- ROE(自己資本利益率):5.7%
これらの数値は、財務の健全性と株主還元のバランスを示しています。特に自己資本比率70.5%という数値は、業種平均(37.8%)を大きく上回っており、財務体質の強固さが際立っています。一方、ROEが5.7%と業種平均の8.85%を下回っているため、資本効率の観点では課題を抱えています。このため、株主還元に積極的でありながらも、大幅な増配には慎重な姿勢が続くと考えられます。
今後の配当方針の予測
今後の配当政策を予測するうえで考慮すべき要素は以下のとおりです。
1. 安定配当の継続性
直近5年間、1株30円の配当を維持してきた実績は、今後も同水準をベースとする可能性が高いことを示しています。配当性向40%前後という数値は、利益変動に応じてある程度の柔軟性を持ちながらも、減配リスクを低く抑える堅実なラインです。FIREを目指す投資家にとっては、配当収入の安定性が最大の魅力となります。
2. 業績連動の可能性
今後の業績拡大、特に本州大都市圏への新規出店が成功すれば、利益増加に伴い増配の余地が生まれるでしょう。ただし、これまでの実績を見る限り、同社は急激な増配には慎重であり、利益の大部分を内部留保に回す傾向が続くと予想されます。従って、増配するとしても「1株あたり数円単位の緩やかな引き上げ」が現実的です。
3. 自己株式取得の活用
第61期には取締役会決議に基づき、自己株式を計450,000株(総額365百万円)取得しました。これは配当以外の株主還元策として位置付けられており、今後も同様の施策が採られる可能性があります。配当と自己株式取得を組み合わせることで、株主還元を柔軟に調整する方針が続くとみられます。
4. ESG・サステナビリティ投資との両立
同社は太陽光発電設備やLED照明への投資など、環境配慮型の設備投資を進めています。これらの投資は中長期的にはコスト削減につながる一方で、短期的には資金負担を伴います。従って、当面は大幅な増配よりも「現行配当+成長投資」のバランス重視の方針が継続するでしょう。
投資家への示唆
配当政策の予測から導かれる投資家への示唆は以下の通りです。
- 安定配当銘柄としての魅力
減配リスクが低く、配当性向も適正水準であるため、長期的に安定した配当収入を狙える銘柄です。FIREを目指す投資家にとって、資産ポートフォリオの安定部分を担う存在として適しています。 - 大幅な増配期待は限定的
ROEの低さや慎重な配当政策から、大幅な増配を期待するのは難しいと考えられます。キャピタルゲイン狙いの投資よりも、インカムゲイン目的の投資に向いた銘柄です。 - 株主還元は配当+自社株買いの二本柱
自己株式取得を積極的に実施している点から、今後も配当と自社株買いを組み合わせた柔軟な株主還元が期待できます。市場環境に応じて還元手法を変えることで、株主価値の最大化を図る戦略といえます。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
株式会社ハンズマンを「長期投資で長期配当を狙う銘柄」として評価すると、レーティングは★★★☆☆(星3つ)が妥当と考えられます。その理由を、日本株全体の水準と比較しながら解説します。
まず、配当利回りの観点から見ると、同社の1株配当は直近5年間連続で30円を維持しており、株価水準(2025年時点で900円前後)から計算すると配当利回りは約3%台前半です。これは日本株全体の平均(2%前後)を上回るものの、高配当株(4~5%以上)と比べると魅力度はやや劣ります。したがって、利回り面では「中位〜やや上位」程度の評価となります。
次に、配当の持続性については、非常に高い評価ができます。自己資本比率70%超という鉄壁の財務体質に支えられ、減配リスクは低水準です。実際、業績が落ち込んだ期でも配当を減額せずに30円を維持してきた実績があり、配当の安定性は小売業の中でも群を抜いています。安定的な配当収入を長期にわたり享受したい投資家にとって、この安心感は大きな魅力です。
一方で、連続増配の観点からは評価を下げざるを得ません。同社は2019年以降、一貫して30円配当を維持しており、減配はないものの増配も行っていません。安定はしているものの、利益が増えても株主還元に即座に反映させる姿勢には乏しく、日本株市場で増配を続ける企業(例えば花王、伊藤忠、オリックスなど)と比べると「成長型配当株」としての魅力は劣ります。投資家からすると、今後も急激な増配は期待しにくい点は注意が必要です。
総合すると、ハンズマンは「減配しない安心感」と「中程度の配当利回り」が強みですが、「増配余地の乏しさ」が弱みです。日本株全体の中では「安定配当株」として中堅レベルの位置付けであり、FIREを目指す投資家にとってはポートフォリオの安定的な基盤として有用ですが、配当成長を重視する場合は他の銘柄との組み合わせが望ましいでしょう。このため、星3つ(中立評価)が最も妥当と判断します。