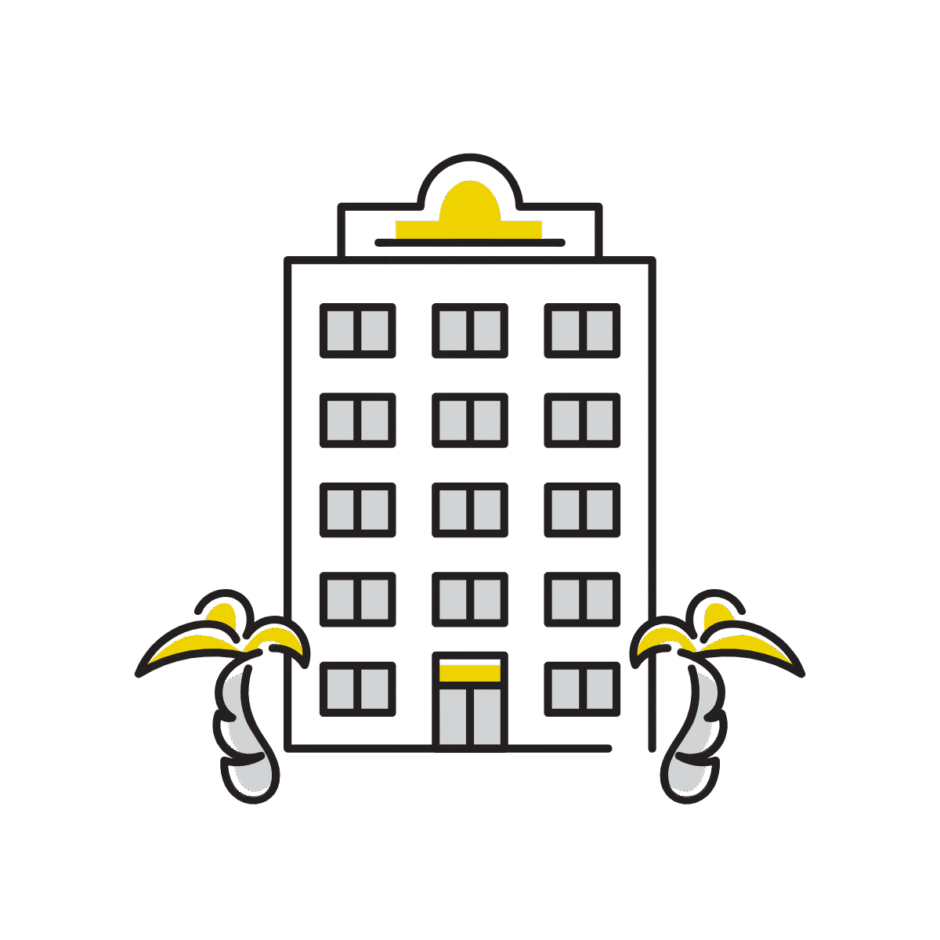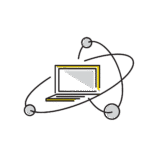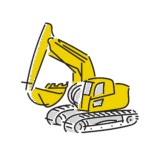企業概要
事業内容とリスク
リファインバースグループは「廃棄物を再資源化し、新しい価値を創造する」というユニークなビジネスモデルを展開しています。グループ企業は4社で構成され、「素材ビジネス」と「資源ビジネス」の2つを柱としています。
- 素材ビジネス
使用済みカーペットタイルや漁網、廃車のエアバッグなどを再資源化し、再生樹脂や再生ナイロン製品として販売しています。これにより、建築資材や自動車部品など幅広い用途で利用されており、SUMINOE・サンゲツなど大手メーカーにも採用されています。
特に「REAMIDE®(リアミド)」や「リファインパウダー」といった製品は環境ラベルを取得しており、環境対応型素材として需要が拡大しています。 - 資源ビジネス
首都圏を中心に建築廃棄物を収集・運搬し、中間処理を行う事業です。東京都内に3つの主要施設を持ち、効率的に廃棄物処理を進めています。処理受託料と再資源化製品の販売という2つの収益源を持つ点が特徴です。 - リスク要因
- 原材料確保の課題:主に使用済みカーペットタイルなど廃棄物の調達量に依存するため、調達不足は業績に直結します。
- 市場動向:オフィス需要や不動産市況に影響されやすく、オフィス供給量や空室率の変化がリサイクル原料の入手に影響します。
- バージン樹脂の価格変動:石油由来の樹脂価格が大きく下落すると、再生樹脂の競争力が弱まる可能性があります。
- 人材確保:特に資源ビジネスでは労働集約的な作業が多いため、安全面を含めた人材確保が課題です。
今までの業績
有価証券報告書によると、直近4期の業績推移は以下の通りです。
- 売上高
第1期:37億円 → 第2期:44億円 → 第3期:38億円 → 第4期:40億円
→ 一時的な減少はあるものの、安定的に40億円前後を維持。 - 経常利益
第1期:2.1億円 → 第2期:1.7億円 → 第3期:0.06億円 → 第4期:1.5億円
→ 直近は黒字に回復し、利益体質の改善が見られます。 - 純利益
第2期に約5億円の赤字を計上したものの、第3期以降は黒字に転じ、第4期は1.4億円の純利益を計上しました。 - 財務基盤
純資産は第2期に大幅に減少しましたが、直近の第4期には27億円まで回復。自己資本比率も1.5%から6.1%に改善しています。 - キャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフローは毎期プラスを維持。特に第4期は約4.6億円のプラスとなり、事業継続に必要な資金は確保できています。
これらの数値から、リファインバースグループは一度赤字に転落したものの、その後の黒字回復と財務基盤の改善により安定性を取り戻しつつあることが分かります。
今後の業績
今後の業績については、以下の成長ドライバーと課題が挙げられます。
成長要因
- 環境対応製品の需要拡大:脱炭素や資源循環の社会的要請が高まり、リファインパウダーやREAMIDE®といった環境配慮型素材の需要は拡大傾向。
- 取引先の広がり:大手カーペットメーカーや建材メーカーへの安定供給に加え、新規取引の開拓も進められています。
- 技術力の高さ:再生ナイロンや廃プラスチック油化技術など、独自技術による製品ラインナップ拡充。三菱ケミカルとの協業も進行中。
- サステナビリティ戦略:CO₂削減への貢献や廃棄物削減への取り組みは、ESG投資の観点からも評価される可能性があります。
課題
- 調達リスク:使用済みカーペットタイルなどの供給が追いつかない場合、製品需要があっても売上に直結しない可能性。
- コスト競争力:設備投資や人件費の増加が進む中で、収益性確保が課題。
- 市場依存:国内オフィス市場や建設需要に影響を受けやすい点は依然としてリスク要因。
中期的な見通し
同社は、再資源化ビジネスを拡大しながら安定した収益基盤を築く方針を示しています。特にケミカルリサイクル分野や新規用途開発によって、今後の売上成長と利益拡大が期待されます。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | 業種平均(サービス業) | リファインバースグループ | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 7.34% | 105.4% | +98.06pt |
| 総資産経常利益率 | 0.89% | 4.36%(経常利益1.5億円 ÷ 総資産34.6億円) | +3.47pt |
| 売上高営業利益率 | 5.75% | 3.7%(営業利益約1.5億円 ÷ 売上高40.7億円) | -2.05pt |
| 自己資本比率 | 6.68% | 6.1% | -0.58pt |
| 配当性向 | 41.33% | 0%(無配) | -41.33pt |
| 純資産配当率 | 2.37% | 0% | -2.37pt |
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
リファインバースグループのROEは105.4%と、業種平均7.34%を大きく上回っています。
これは一見すると非常に高い収益力を意味しますが、背景には「自己資本がまだ小さい」ことが挙げられます。純資産が2.7億円程度と規模が小さいため、純利益1.4億円を計上しただけでもROEが突出して高くなっています。
したがって、ROEの高さを単純に「収益力の高さ」と解釈するのは危険であり、むしろ今後の純資産拡充に伴ってROEが安定的な水準に落ち着くと考えるべきです。
投資家にとっては「短期的な高ROE」よりも、「中長期的にROEを10%前後で安定させられるか」が重要な評価ポイントとなります。
2. 総資産経常利益率
総資産に対する経常利益の割合は4.36%で、業種平均0.89%を大きく上回っています。
これは、資産効率が比較的高いことを示しています。リファインバースグループは資産規模が約34.6億円とまだ小さいため、営業活動で得られる利益が資産に対して相対的に大きく見える構造です。
一方で、廃棄物再資源化事業は設備投資や施設維持コストが不可欠であり、今後資産規模が拡大すれば、この数値は低下していく可能性があります。つまり、現時点での「高効率性」は規模の小ささに起因しており、持続可能かどうかは慎重に見極める必要があります。
3. 売上高営業利益率
売上高営業利益率は3.7%で、業種平均5.75%を下回っています。
この数値は同社が「利益率の低い構造」にあることを示しています。廃棄物の再資源化は社会的意義が大きいものの、処理コストや人件費がかかるため、利益率はどうしても低くなりがちです。
さらに、素材ビジネスにおいては商社を経由した取引もあるため、マージンが削られるケースも存在します。競合企業との差別化要因としては「独自技術によるリサイクル品質の高さ」が挙げられますが、それを価格に転嫁できるかが今後の課題です。
投資家視点では「売上高の伸びよりも利益率改善が進むかどうか」が注目点になります。
4. 自己資本比率
自己資本比率は6.1%で、業種平均6.68%をやや下回っています。
自己資本比率が低いということは、財務基盤がまだ脆弱であることを意味します。特に、2023年には赤字決算を経験しており、自己資本が一時的に大きく毀損した経緯があります。
直近では黒字化によって資本が回復傾向にあるものの、依然として「有事に備える財務余力」は十分ではありません。長期投資を考える上では、この自己資本比率が今後10%以上に安定してくるかどうかを見極める必要があります。
資源循環ビジネスは環境規制や設備投資の影響を受けやすいため、安定配当を実現するにはまず財務体質の強化が不可欠です。
5. 配当性向
業種平均41.33%に対し、リファインバースグループは0%(無配)です。
これは、同社が成長投資や財務基盤強化を優先しているためです。黒字回復した直後の段階で無配当を選択するのは自然な戦略であり、特にグロース市場に上場する企業としては珍しくありません。
しかし、配当を目的とする個人投資家にとっては、この点はマイナス評価となります。将来的に配当開始があるとすれば、自己資本比率の改善と安定的な利益創出が見えてからになるでしょう。
6. 純資産配当率
業種平均2.37%に対し、リファインバースグループは0%です。
純資産配当率は株主資本に対してどれだけ配当を行っているかを示す指標ですが、現時点で同社は株主への利益還元を行っていません。
長期的にFIREを目指す投資家にとって、配当再投資による複利効果を期待できない点は大きなデメリットです。したがって、現時点では「将来の配当開始に期待して株価上昇益を狙う投資」か、「他の配当株との組み合わせでポートフォリオを組む」必要があるといえます。
配当方針と今後の展望
リファインバースグループは株主還元を重要な経営課題のひとつと位置づけています。しかし現在は成長過程にある企業であり、内部留保を充実させて事業拡大や技術開発に投資することこそが「株主にとっての最大の利益還元」だと考えています。
そのため、創業以来これまで一度も配当を実施しておらず、当面は無配を継続する方針です。ただし将来的には、財務状態や経営成績を踏まえたうえで配当を検討する余地を残しています。さらに、配当を実施する場合は「中間配当」と「期末配当」の年2回体制を基本とすることが明記されています。
配当関連指標の現状
1. 配当性向
直近の有価証券報告書では配当性向は0%であり、株主への現金還元は一切行われていません。純利益が計上されても、それを内部留保や成長投資に回す方針です。
2. 純資産配当率
純資産配当率も当然0%です。これは株主資本に対する配当金の比率を示す指標ですが、無配のため評価対象外となっています。
3. 自己資本比率・ROEとの関連
自己資本比率は6.1%とまだ低い水準ですが、ROEは100%を超えるなど特殊な数値を示しています。これは「自己資本が小さいため、黒字化した途端にROEが極端に高くなる」という構造的要因によるものです。内部留保を積み増すことで資本の厚みを増し、今後はROEが安定的に10%前後を維持することが期待されます。これは将来的な配当余力の前提条件となります。
今後の配当方針予測
短期的(今後2〜3年)
- 無配継続の可能性が高い
財務基盤の脆弱さと自己資本比率の低さを踏まえると、直近では引き続き内部留保を優先する可能性が高いです。 - 事業拡大への資金投下
再資源化ビジネスは設備投資が不可欠で、安定的な利益確保には先行投資が必要です。したがって、株主還元より成長投資が優先される局面が続くでしょう。
中期的(3〜5年)
- 黒字の安定化と内部留保拡充
黒字決算が複数年続けば、金融機関からの信用度も上がり、自己資本比率が改善される見込みです。この段階で初めて「配当検討」の具体的な議論が始まる可能性があります。 - 初配当のシナリオ
仮に配当を開始する場合、当初は少額(配当性向10〜20%程度)の水準で、記念的に株主へ利益を還元する形となるでしょう。
長期的(5年以上)
- ESG投資との親和性
同社は「廃棄物を資源化する」という社会的意義の大きい事業を展開しており、ESG投資の観点から株主構成が変わる可能性があります。配当政策の策定はESG投資家へのアピール要素にもなり得ます。 - 安定配当企業への転換
成熟段階に入れば、期末配当+中間配当を年2回行う「安定配当方針」に移行するでしょう。配当性向も業種平均の40%程度に近づくことが予想されます。
投資家にとってのポイント
- 現状は配当を期待できない
長期配当狙いの投資家にとっては、直近では投資妙味に欠ける点は否めません。 - 株価上昇益を狙う段階
配当よりも、環境関連ビジネスの成長による株価上昇益を狙う局面です。 - 配当開始は将来のボーナス要素
財務安定化後に配当を始めた場合、そのタイミングで株価が大きく見直される可能性があります。配当再投資を見込む投資家にとっては、初配当の発表が一つの大きなターニングポイントとなるでしょう。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
リファインバースグループは「廃棄物を資源へと循環させる」という社会的意義の大きいビジネスモデルを持ち、環境対応やESG投資の観点から今後の成長余地は確かに魅力的です。直近では黒字回復を果たし、財務基盤の改善傾向も見え始めています。しかし、長期配当を目的とする投資家にとっては現時点での投資妙味は限定的です。
第一に、同社は創業以来無配を継続しており、現時点で配当実施の予定も明確には示されていません。利益をすべて内部留保や成長投資に充てており、株主への現金還元は「将来的に状況を見て検討」とされています。つまり、配当収入を投資の柱に据える個人投資家にとっては、現段階では配当によるリターンが期待できない状況です。
第二に、財務基盤がまだ脆弱である点も考慮すべきです。自己資本比率は約6%と依然として低く、安定配当を実現するにはさらなる内部留保の積み増しが必要です。業種平均の自己資本比率(約6.7%)と比較すると大差はないように見えますが、大手企業や安定配当を行っている日本株に比べると資本の厚みが不足しています。長期配当を継続的に出すためには最低でも自己資本比率が10〜20%程度に安定する必要があるでしょう。
第三に、日本株全体との比較において、同社は「配当株」としてはまだ立ち位置が確立していません。たとえば、三菱商事やNTTといった高配当株は配当性向40%以上を維持しつつ長期的に増配しており、個人投資家からの支持も厚いです。銀行株や電力株も高配当利回りが見込める一方、リファインバースは配当ゼロであるため、配当狙い投資家にとっての投資対象としては明らかに劣後します。
一方で、ポジティブな要素としては、同社の事業が「循環型社会」「脱炭素」といった成長トレンドに合致しており、将来的には安定収益と配当余力を確立できる可能性がある点です。また、報告書において「将来的に配当を行う場合は中間・期末の年2回を想定している」と明記されており、配当政策の枠組みは既に整備されている点は注目できます。したがって、数年先に初配当が実現する可能性はあります。
結論として、リファインバースグループは「将来の配当株候補」として注目する価値はあるものの、現時点では長期配当目的の投資家にとって優先度は低いと言わざるを得ません。日本株の中には既に高配当・増配を実施している銘柄が多数存在するため、それらと比較すれば「★2つ」の評価が妥当です。今後の財務安定化と初配当のタイミングが訪れれば、レーティングは★3以上へと引き上げられる可能性があります。