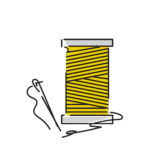企業概要
事業内容とリスク
第一カッター興業株式会社は、1967年の創業以来、ダイヤモンド工法やウォータージェット工法を駆使した「切断・穿孔工事事業」を中心に事業を展開してきました。現在では、連結子会社4社と持分法適用関連会社2社を含むグループ体制を構築し、全国規模で公共事業や民間工事に携わっています。
主力の切断・穿孔工事事業では、橋梁・ダム・港湾といった大規模インフラ工事から、建物解体や耐震補強、鉄道や上下水道施設工事、さらに化学プラントや発電所のメンテナンスまで幅広い分野に対応しています。特に、老朽化したインフラの補修需要や耐震・免震改修の拡大は今後も追い風となるでしょう。一方で、工事の多くは下請け契約であり、公共事業への依存度が高いことから、政府の予算削減や建設投資動向に業績が左右されやすいリスクを抱えています。
また、工事に必要な原材料の約半数近くを旭ダイヤモンド工業に依存しており、特定の仕入先リスクも存在します。さらに、工事現場は高所作業や重機利用が多いため、事故リスクが避けられない点も懸念事項です。協力業者や人材確保への依存度も高く、慢性的な建設業界の人材不足が事業継続に与える影響は無視できません。
こうしたリスクに対応するため、同社は建設業界以外の分野(化学工場や石油プラントのメンテナンスなど)の受注を増やす方針を掲げており、依存度の分散を進めています。また、環境負荷の少ない施工方法の導入や労働時間抑制など、サステナビリティを意識した取り組みも進めています。
今までの業績
直近5年間の業績を振り返ると、売上高は2021年6月期の193億円から2023年6月期には221億円まで成長しましたが、2024年以降は減少傾向に転じ、2025年6月期の売上高は202億円と前期比3.3%減となりました。背景には、高速道路リニューアル工事の受注減少や子会社の連結範囲除外が影響しています。
利益面では、2025年6月期に営業利益が16億円(前年比32.9%減)、経常利益が17億円(前年比36.7%減)と大幅に落ち込みました。純利益も13億円(前年比32.7%減)と減少しています。これは資材価格の高騰や原価経費の増加も要因となっています。
一方で、ビルメンテナンス事業は堅調で、2025年6月期の完成工事高は6億円(前年比18.9%増)、セグメント利益は1.25倍以上増加しました。これは首都圏を中心に大手デベロッパーとの取引が拡大した結果です。切断・穿孔工事事業に比べると規模は小さいですが、安定した収益源としての役割が期待されます。
財務基盤については、自己資本比率が89.4%と高水準を維持しており、配当金の支払いも継続。2025年6月期の1株当たり配当金は40円、配当性向は42.5%と、株主還元の姿勢を示しています。
今後の業績
今後の成長を占う上で、同社は大きく二つの方向性を掲げています。ひとつは既存事業の深化、もうひとつは新市場への展開です。
既存事業では、研究開発や技術者育成を強化し、施工技術力の高度化を進めることで競争力を維持。特に高速道路や鉄道、産業インフラといった長寿命化が不可欠な分野での受注拡大を目指しています。また、ウォータージェット工法をはじめとする環境対応型工法の需要拡大も期待されます。
新市場開拓の面では、エネルギー関連工事や水中施工といったニッチ領域でのシェア拡大を狙っており、将来的には予防保全や新たな付加価値を生む技術を基盤とした新規事業の立ち上げにも取り組む方針です。特に、気候変動への対応として電動車導入や太陽光発電設備活用など、サステナビリティを重視した戦略が打ち出されています。
ただし、資材価格やエネルギー価格の高騰、人材不足といった外部要因は依然として収益の圧迫要因です。そのため、同社の成長が安定的な株主還元につながるかどうかは、技術力の進化と受注の分散化がどこまで進むかにかかっています。
長期配当を狙う個人投資家にとっては、同社の高い自己資本比率と安定した配当実績は魅力です。一方で、業績変動の大きさや建設業界依存というリスクも理解した上で投資判断を行う必要があります。今後、事業多角化と安定収益の確立が進めば、配当による長期リターンを期待できる可能性は高いと言えるでしょう。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | 建設業平均 | 第一カッター興業 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE, %) | 10.26 | 6.8 | -3.46 |
| 総資産経常利益率(%) | 6.19 | 7.3 | +1.11 |
| 売上高営業利益率(%) | 6.62 | 8.1 | +1.48 |
| 自己資本比率(%) | 42.68 | 89.4 | +46.72 |
| 配当性向(%) | 38.87 | 42.5 | +3.63 |
| 純資産配当率(%) | 3.88 | 2.9 | -0.98 |
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
ROEは株主が出資した自己資本に対してどれだけ効率的に利益を生み出したかを示す指標です。建設業平均が10.26%であるのに対し、第一カッター興業は6.8%と3.46ポイント低い数値となっています。
これは利益水準の減少が主因であり、直近決算では資材高騰や工事案件の減少による純利益の縮小が響きました。同社は高い自己資本比率を誇るため財務の安定性は強固ですが、その一方で資本を効率的に利益に変える力は業界平均より劣っていることが分かります。投資家目線では「安定感はあるが成長効率が低い」という評価につながりやすい指標です。
2. 総資産経常利益率
総資産経常利益率は、企業が保有する資産全体からどの程度の利益を生み出しているかを測るものです。建設業平均が6.19%に対して、第一カッター興業は7.3%と1.11ポイント上回っています。
この点は同社の効率性の高さを示しており、保有資産を効果的に運用し、経常的な収益を確保していると言えます。特に公共インフラ関連工事や安定的なビルメンテナンス事業が収益を支えていることが背景にあります。ROEが低い一方でこちらは平均以上という結果は、「資本を厚く持ちすぎてROEが低下しているが、資産効率自体は高い」という財務構造を反映しています。
3. 売上高営業利益率
営業利益率は本業で稼ぐ力を示す指標で、建設業平均の6.62%に対し、第一カッター興業は8.1%と1.48ポイント上回っています。
公共工事や大規模インフラ案件を中心とする安定した受注環境が利益率を底支えしており、さらにビルメンテナンス事業の利益率改善も寄与しました。建設業全体では資材価格上昇が重荷になっていますが、同社は工法の高度化や効率化により収益性を維持している点が評価できます。長期投資家にとっては「景気変動に左右されにくい安定した利益体質」として安心材料と言えるでしょう。
4. 自己資本比率
建設業平均が42.68%であるのに対し、第一カッター興業は驚異的な89.4%を誇ります。差異は+46.72ポイントと突出しています。
自己資本比率が高いということは、借入金に頼らず自己資本で経営を行っていることを意味し、財務の健全性は極めて高いと言えます。景気後退期や突発的な資材高騰にも耐えうる強固な財務基盤は、長期的な配当を狙う投資家にとって非常に魅力的です。ただし、借入を抑えすぎていることでレバレッジ効果を活かせず、成長余地を自ら制限している可能性もあります。ROEの低さとも関連していると考えられます。
5. 配当性向
配当性向は建設業平均の38.87%に対し、第一カッター興業は42.5%とやや高めです(+3.63ポイント)。
近年の業績減速を受けても配当を維持・増配しており、株主還元姿勢が強いことが見て取れます。ただし、配当性向が高止まりすると内部留保が減少し、将来の成長投資に充てられる資金が不足するリスクも出てきます。現状では健全な範囲ですが、今後さらに業績が低迷した場合には「無理な配当維持」と見なされかねない点には注意が必要です。
6. 純資産配当率
純資産配当率は建設業平均の3.88%に対し、第一カッター興業は2.9%と0.98ポイント低くなっています。
純資産が厚いため分母が大きく、相対的に配当利回りが下がってしまっているのが要因です。投資家から見ると「安全性は高いがリターンは抑えめ」という印象を受けやすい指標です。高配当株としての魅力は相対的に弱いものの、財務の安定性を背景に長期で配当を続けられる見込みが高いことは評価できます。
配当方針と今後の展望
配当方針の基本的な考え方
第一カッター興業株式会社は、有価証券報告書において「株主への利益還元を最重要課題の一つ」と明言しています。その一方で、技術開発・設備投資・人材育成といった競争力の維持・強化に必要な投資を行うため、内部留保を確保する方針も併せて掲げています。つまり、「安定的かつ長期的な配当」を基本としながら、成長のための投資も両立させる経営姿勢が示されています。
配当については、配当性向30%以上を目安とし、基本的に年1回の期末配当を実施。必要に応じて取締役会の決議によって中間配当を行うことも可能としています。2025年6月期の配当は1株あたり40円とされ、連結ベースでの配当性向は34.0%でした。
配当実績の推移
- 2023年6月期:1株当たり35円(総額401,929千円)
- 2024年6月期:1株当たり38円(総額436,558千円)
- 2025年6月期:1株当たり40円(総額459,670千円)
直近3年間で配当は35円 → 38円 → 40円と増加傾向にあり、株主還元強化の姿勢が伺えます。
配当関連指標
- 配当性向:42.5%(単体ベース)、34.0%(連結ベース)
- 自己資本比率:89.4%(極めて高い財務健全性)
- 純資産配当率:2.9%(業種平均3.88%を下回る)
自己資本比率の高さから見て、同社は潤沢な資本を背景に安定的な配当を実施可能な体制にあります。一方で、資本効率の観点では配当利回りが抑えめになっている点が課題です。
今後の配当方針の予測
- 安定的な増配路線の継続
過去の実績からも、業績が多少低迷しても配当を増加させており、今後も「減配回避・安定増配」を基本とする可能性が高いです。配当性向30%以上という方針に基づき、業績の回復があればさらに増配が期待できます。 - 内部留保と成長投資のバランス
配当性向はすでに40%前後まで高まっており、これ以上の大幅引き上げは成長投資とのバランスを欠くリスクがあります。したがって、中期的には配当性向35〜40%を維持しつつ、内部留保を活用して技術力強化や人材投資に資金を回すと見込まれます。 - 株主還元策の多様化
直近では自己株式の取得・処分(役員報酬制度への活用)が行われており、将来的には自社株買いによる株主還元強化も視野に入るでしょう。これは1株あたりの価値を高め、配当と並行して株主に利益を還元する有効策です。 - 長期投資家にとっての魅力
高い自己資本比率と安定配当方針から、長期的に減配リスクは低く、配当で安定収入を得たい投資家に適した銘柄です。特にFIREを目指す投資家にとっては、「大きな成長は見込みにくいが、安定した配当収入が期待できる」点で有力な選択肢となるでしょう。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
第一カッター興業株式会社を、長期投資による長期配当を目的とした観点から評価すると、総合的には「★★★☆☆(星3つ)」と位置付けられます。日本株全体と比較した際の相対評価を踏まえて解説します。
まず、同社の大きな強みは極めて高い自己資本比率(約89%)にあります。建設業界の平均自己資本比率が40%台にとどまる中で、第一カッター興業は圧倒的に健全な財務基盤を築いており、倒産リスクや資金繰りリスクが小さい点は投資家にとって大きな安心材料です。また、配当政策についても「配当性向30%以上」を明確に掲げており、過去3年間は35円、38円、40円と着実に増配を続けています。景気変動の影響を受けやすい建設業界にありながらも減配を回避し、株主還元姿勢を堅持している点は評価できます。
一方で、他の日本株と比較した際の課題は「成長性の低さ」と「資本効率の弱さ」です。ROEは6〜7%台にとどまり、建設業平均の10%超や、配当株として人気のある高収益企業(商社株やインフラ関連株)と比べると劣後しています。自己資本が厚すぎるため、資本を有効活用できていない構造的問題もあり、その結果、純資産配当率も業界平均を下回っています。投資家視点では「安定はしているが、配当利回りや株価成長余地は限定的」という評価につながります。
また、同社の事業は公共工事やインフラ工事に依存する割合が高く、政策や景気動向に左右されやすい点もリスク要因です。今後はビルメンテナンスやプラント保守といった安定収益源の拡大がカギになりますが、現時点では事業多角化が十分進んでいるとは言えません。
総合すると、第一カッター興業は「高い財務安定性と安定配当」という長所を持ちながら、「成長性の低さ」「資本効率の悪さ」という短所を抱えています。FIREを目指す投資家にとっては、安定収入を確保するポートフォリオの一部として一定の役割を果たす銘柄ですが、単独で主力配当株とするにはやや力不足です。他の高ROE・高配当利回り銘柄と組み合わせることで、分散投資先として活かすのが望ましいと考えられます。