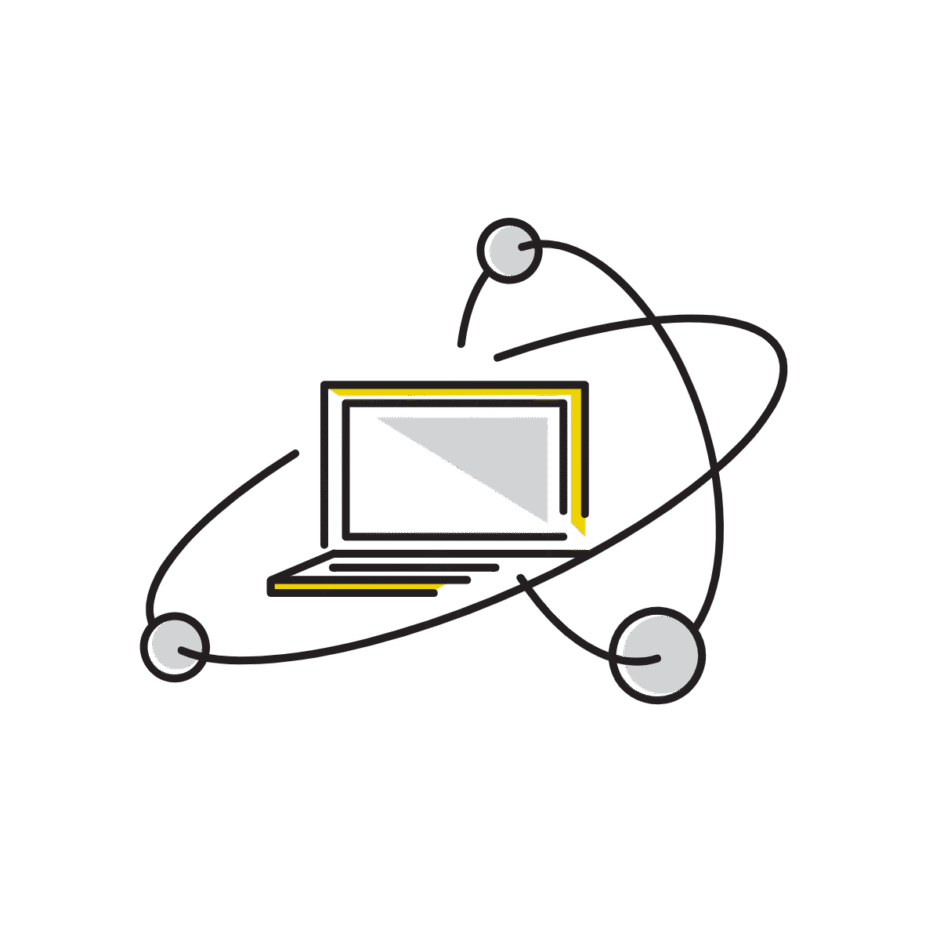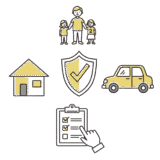企業概要
事業内容とリスク
HPCシステムズ株式会社(HPC Systems Inc.)は、「人とコンピューティングの力で世界平和に貢献する」という理念のもと、研究者や開発者に向けて計算環境やソリューションを提供している企業です。事業の柱は、HPC事業(高性能コンピューティング)とCTO事業(産業用コンピュータ)の2つに分かれています。
HPC事業
HPC事業では、科学技術計算用のコンピュータを中心に、研究・開発分野向けの高性能システムを構築しています。大学や研究機関、企業のR&Dセンターなどを主要顧客とし、特にライフサイエンス(生命科学)やマテリアルサイエンス(材料科学)の分野に強みを持ちます。コンピュータによる高速・高精度な計算を通じて、新素材の開発や創薬、AI解析などを支援しており、いわば「研究開発の頭脳」を担う存在です。
この事業の特徴は、ハードウェア販売にとどまらず、アプリケーション開発・受託研究・運用サポートまでをワンストップで提供する点にあります。また、大学と企業を結ぶ「橋渡し役」としての機能も持ち、基礎研究成果を産業応用へとつなげる役割を果たしています。
さらに同社は、クラウド型のHPC環境(Science as a Cloud)を展開し、オンプレミスからクラウド利用へ移行する研究者のニーズにも対応。AIやビッグデータ解析との融合が進むなかで、次世代の研究基盤を支える存在として成長しています。
CTO事業
CTO事業では、顧客の要望に応じて設計・製造される産業用コンピュータを提供しています。用途は製造装置、工作機械、医療機器、計測装置、デジタルサイネージなど多岐にわたります。一般的なパソコンとは異なり、耐環境性・信頼性・長期稼働を重視した構造が特徴です。
同社は、千葉県匝瑳市の自社工場で開発から出荷までを一貫管理し、独自の生産支援システム「ProMIS」を活用して製造トレーサビリティを確保しています。この高品質な供給体制が、製造業や社会インフラ分野の顧客からの信頼を支えています。
主なリスク
事業リスクとしては以下が挙げられます。
- 景気変動による研究・設備投資の影響:HPC事業は研究開発費、CTO事業は設備投資需要に連動。
- 技術革新への対応力:AIやエッジコンピューティングなど技術の変化に追従できない場合、競争力低下の恐れ。
- 仕入先依存:特にHPC事業でSuper Micro Computer, Inc.など海外ベンダーへの依存度が高い。
- 部品調達リスク:半導体などの供給不足や価格高騰が製造に影響。
- 為替・地政学的リスク:台湾を中心とする海外調達に依存。
- 配当政策の柔軟性:DOE4%を目安としつつも、成長投資を優先するため、配当が行われない可能性もある。
同社はこれらのリスクを踏まえ、内部管理体制とガバナンスの強化、人材育成やサステナビリティ経営にも注力しています。
今までの業績
過去5年間の売上・利益推移を見ると、HPCシステムズは安定成長を続けています。2021年6月期から2025年6月期にかけて、売上高は約5.8億円から7.0億円へと拡大し、経常利益は約6.6億円から6.7億円へ増加しています。
2025年6月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高:70億6,443万円(前期比+1.7%)
- 経常利益:6億7,591万円(前期比+77%)
- 当期純利益:4億5,563万円(前期比+75%)
- 自己資本比率:57.7%(前期52.0%から上昇)
- 1株当たり配当金:28円(前年25円から増配)
売上・利益ともに堅調な伸びを維持しており、特に利益率の改善が目立ちます。自己資本利益率(ROE)は18.0%と高水準で、資本効率の向上が確認できます。
成長要因
- HPC事業の研究開発需要の拡大
AI・ビッグデータ解析・マテリアルズインフォマティクスなど、次世代研究分野への設備投資が増加。 - CTO事業の安定的な受注基盤
製造業の長期設備更新需要や、医療・インフラ分野での採用拡大が寄与。 - コスト管理・製造効率の向上
自社工場の生産効率化により、利益率の向上を実現。 - 財務の健全性
キャッシュ・フローの安定化により、現金同等物は19億7千万円と潤沢な水準を確保。
投資家にとっての注目点
配当性向は25.6%と無理のない水準であり、内部留保を確保しながらも安定した還元を続けています。自己資本比率の向上もあり、長期的な財務健全性は高いと評価できます。株価収益率(PER)は17.9倍と適正水準で、割高感はありません。
今後の業績
今後の業績
今後のHPCシステムズは、「S³ as a Service」戦略のもとで更なる成長を目指します。これは、
- System as a Service(ハード+ソフトの最適提供)
- Science as a Service(計算科学のノウハウ提供)
- Science as a Cloud(研究用クラウド環境の提供)
の3つを掛け合わせた独自モデルで、顧客の研究開発を包括的に支援する仕組みです。
成長戦略の方向性
- AI・エッジ分野の拡大
AIや機械学習、ディープラーニングの需要拡大により、HPC事業とCTO事業の垣根が曖昧化。両事業の技術連携を強化し、新しい市場を開拓する方針です。 - クラウドHPCの普及
大学や研究機関に限らず、中堅企業の研究部門にもHPCのクラウド利用が浸透しつつあり、サブスクリプション型サービスとして収益の安定化を見込んでいます。 - 人材投資とグローバル展開
ベトナム現地法人(Intelligent Integration Co., Ltd.)を活用し、開発力とコスト競争力を高めるとともに、アジア圏での受託研究・ソフト開発も拡大。 - サステナビリティ経営
ESG委員会を設置し、気候変動対応(TCFD提言賛同)、人的資本投資(人財グランドデザイン)を推進。離職率7.3%など労働環境も安定しています。
今後のリスクと対応
- 景気後退時の研究・設備投資減少:顧客基盤の分散と受託計算サービスでリスクを軽減。
- 技術革新スピード:AI・量子計算など新分野への先行投資を継続。
- 為替・地政学リスク:仕入先の多元化、在庫調整でリスクヘッジを実施。
- 人的リソースの確保:博士人材や専門技術者の採用強化と教育体系の刷新。
配当・株主還元
配当方針はDOE(株主資本配当率)4%を目安としつつも、「成長投資優先+安定配当」を両立する形を取っています。今後も増配余地があり、FIREを目指す長期投資家にとっては、安定配当銘柄として注目に値します。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | HPCシステムズ | 業種平均(情報・通信) | 差異(ポイント) |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 18.0% | 10.68% | +7.32 |
| 総資産経常利益率 | 14.9%(推計) | 5.45% | +9.45 |
| 売上高営業利益率 | 9.6%(推計) | 11.36% | −1.76 |
| 自己資本比率 | 57.7% | 32.89% | +24.81 |
| 配当性向 | 25.6% | 37.14% | −11.54 |
| 純資産配当率(DOE) | 4.6%(算出) | 3.45% | +1.15 |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE) ― 資本効率の高さを誇る優良企業
HPCシステムズのROEは18.0%で、情報・通信業の平均10.68%を7ポイント以上上回る水準です。
ROEは、株主から預かった資本をどれだけ効率的に利益へ変えられているかを示す指標で、一般的に10%を超えると高水準とされています。
この高ROEの背景には、同社の収益性の改善と財務構造の強化があります。特に2024年から2025年にかけて、経常利益が426百万円→675百万円へと約1.6倍に増加しており、売上成長に加えてコスト効率が大幅に改善したことが寄与しています。
加えて、自己資本比率が高いために過剰なレバレッジを使わずに高い利益率を出している点も注目に値します。これは経営が堅実で、「安定性を保ちながら利益を出せる企業」という証拠でもあります。
特に長期投資家にとっては、短期的な株価変動よりも、こうした高ROEの持続力が重要です。同社は資本効率を維持しつつ、内部留保を着実に積み上げており、今後も安定的にROE15〜20%前後を維持する可能性が高いと見られます。
② 総資産経常利益率 ― 資産の活用力が極めて高い
HPCシステムズの総資産経常利益率は推計で約14.9%と、業種平均の5.45%を大きく上回ります。
この指標は「保有している資産をどれだけ効率的に利益に変えたか」を示すもので、資本だけでなく総資産全体の生産性を測る重要な尺度です。
HPCシステムズの高い効率性の要因は、次の2点にあります。
- 軽資産経営の徹底:同社は自社工場を保有する一方で、固定資産の規模を抑え、利益率の高いソフトウェア・クラウド領域(Science as a Service)を強化しています。
- 在庫・債権の最適化:棚卸資産と売掛金の圧縮を進め、運転資本の回転効率を向上させた結果、資産の有効活用が進んでいます。
つまり、HPCシステムズは「資産を眠らせない企業」であり、効率経営が利益率の高さに直結しています。業界平均の約3倍の効率性は、経営の成熟度と戦略的資産運用の巧みさを物語っています。
③ 売上高営業利益率 ― 高付加価値化が課題
一方、売上高営業利益率は推計で約9.6%と、業種平均11.36%をやや下回っています。
この指標は、売上に対してどれだけ営業利益を確保できたかを示すものであり、HPCシステムズの場合は受託型ビジネス(BtoB特有のコスト構造)が影響しています。
HPC事業は高性能計算機やソフトウェアのカスタマイズ提供が中心で、1件あたりの受注額が大きい反面、プロジェクトごとの開発工数・人件費が発生します。また、CTO事業では部品価格や調達コストの変動がマージンを圧迫することもあります。
ただし、営業利益率が10%前後を維持していること自体が優秀であり、今後はクラウド提供型(S³ as a Service)の拡大により、継続収益モデル化が進むことで営業利益率の改善が見込まれます。
特に、HPCクラウド・AI解析分野の伸長が期待される2026年以降には、営業利益率が業種平均を再び上回る可能性が高いでしょう。
④ 自己資本比率 ― 圧倒的な財務健全性
自己資本比率は57.7%で、業種平均32.89%を約25ポイント上回る極めて健全な水準です。
これは、有利子負債に依存せず、自社の資本で事業を支えていることを意味します。中小型の成長企業としては異例の安定性であり、財務リスクの低さは特筆に値します。
財務体質が強固であることは、景気後退局面や金利上昇局面においても企業存続力を高めます。特にHPCシステムズは、成長投資と配当を両立できる余裕のある企業であり、今後も持続的な増配が期待できる基盤が整っています。
また、自己資本比率の上昇はROEとのトレードオフ関係にありますが、HPCシステムズは高ROEを維持したまま自己資本を厚くしており、これは稀に見るバランスの良い経営といえます。
長期配当投資の観点では、「倒れない企業」であることが何よりの安心材料です。
⑤ 配当性向 ― 将来を見据えた堅実な株主還元
配当性向は25.6%で、業種平均の37.14%よりもやや低い水準です。
つまり、同社はまだ成長投資を優先している段階にあり、配当よりも内部留保・研究開発に資金を振り向けているといえます。
ただし、2025年には配当金を25円→28円に増配しており、着実な株主還元を実施しています。また、DOE(株主資本配当率)4%を配当基準としており、配当を毎期安定的に行う方針を明確にしている点は評価できます。
今後、HPCクラウドやAI受託などの安定収益源が拡大すれば、配当性向を30〜35%程度に引き上げる余地は十分あります。中長期的に見ると、「成長を支える内部留保」と「持続的な増配」の両立が実現されると考えられます。
⑥ 純資産配当率(DOE) ― 理想的な還元バランス
純資産配当率は推計4.6%で、業種平均3.45%を上回ります。DOEは株主資本に対する配当の割合を示し、安定配当方針の堅実さを測る指標です。
同社はDOE4%を目安と明言しており、実際に目標を上回る結果を残しています。これは「無理のない水準で安定的に還元する」という、長期配当志向の投資家にとって理想的な姿勢です。
DOEが安定している企業は、景気変動に左右されにくい配当政策を維持できる傾向にあります。HPCシステムズは高ROEかつ高DOEを両立しており、持続的な成長と株主還元のバランスが取れています。
配当方針と今後の展望
HPCシステムズ株式会社の配当方針と今後の展望
HPCシステムズ株式会社(HPC Systems Inc.)は、AIや高性能コンピューティング(HPC)分野に特化し、研究機関や製造業を支える技術基盤企業として成長を続けています。特に近年は「S³ as a Service」戦略を軸に、システム・サイエンス・クラウドを融合した事業展開を進めており、収益の安定化と成長の両立を図っています。
本記事では、同社の配当方針と配当関連指標を最新の有価証券報告書(第20期・2025年6月期)から整理し、今後の配当方針や投資家への還元戦略を予測します。
配当方針の概要 ― 「DOE4%を基準とした安定的な還元」
HPCシステムズは、有価証券報告書において以下のように明確な配当方針を掲げています。
「当社グループは、株主に対し成長に応じた利益還元を重要な経営課題として認識しております。中長期の経営視点から、獲得した資金は内部留保の充実化と将来の事業展開及び経営体質の強化のための投資等に充当しつつ、財務の健全性、及び株価水準等を総合的に判断した上で自己株式の取得を機動的に実施することを基本方針としております。配当につきましては、成長投資を優先し、企業価値の最大化を目指す中で、DOE(株主資本配当率)4%を目安として実施を判断しております。」
この記載から分かるように、同社は「DOE(株主資本配当率)を4%に維持すること」を明確な基準としています。DOEとは、自己資本に対する年間配当の比率を示す指標であり、企業の資本政策と配当安定性を同時に表すものです。
一般的に、配当性向(純利益に対する配当割合)よりも財務体質を反映した安定指標であるため、HPCシステムズの配当方針は「一時的な業績変動に左右されにくい堅実な方針」と言えます。
これまでの配当実績の推移
過去5期の配当実績をみると、同社は上場後一貫して安定的な配当を維持しています。
| 決算期 | 1株当たり配当金 | 配当性向 | 1株当たり純利益(円) |
|---|---|---|---|
| 第16期(2021年6月) | ― | ― | 107.87 |
| 第17期(2022年6月) | 25円 | 24.3% | 102.92 |
| 第18期(2023年6月) | 25円 | 58.2% | 42.93 |
| 第19期(2024年6月) | 25円 | 41.3% | 60.47 |
| 第20期(2025年6月) | 28円 | 25.6% | 109.21 |
2025年6月期には3円増配(25円→28円)を実施。これは、業績回復と自己資本比率の上昇を踏まえた判断であり、企業としての安定成長フェーズ入りを示唆しています。
また、配当性向が25.6%と控えめであることからも、「成長投資を優先しつつ、株主還元を継続的に行う」というバランス型の経営スタンスが見て取れます。
配当関連指標の分析 ― 高ROE×安定DOEの好バランス
HPCシステムズの2025年6月期における主要な株主還元関連指標は以下の通りです。
| 指標 | 2025年6月期 | 備考 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(ROE) | 18.0% | 高い資本効率を維持 |
| 自己資本比率 | 57.7% | 財務健全性が極めて高い |
| 配当性向 | 25.6% | 内部留保重視型 |
| DOE(純資産配当率) | 約4.6% | 目安4%を達成 |
| 株価収益率(PER) | 17.9倍 | 適正バリュエーション |
ROE18%という高い資本効率と、DOE4%という安定的な還元指標の両立は、極めて理想的な状態です。
一般的に、ROEが高くDOEも維持されている企業は、「利益を出し続ける力」と「安定した還元姿勢」の両方を兼ね備えています。
HPCシステムズはまさにその代表例であり、「成長企業の中で配当が途切れにくい稀有な存在」と言えるでしょう。
財務基盤から見る配当余力
同社の財務体質は極めて健全で、2025年6月期の自己資本比率は57.7%、現金及び同等物は19億7千万円と、キャッシュリッチな体制を築いています。
また、有利子負債が少なく、財務レバレッジに頼らない経営を続けている点も特徴的です。
営業キャッシュフローは13億円超を確保しており、配当支払い後も余裕を持って成長投資・研究開発に資金を回せる状況です。これは「配当を減らさずに成長できる企業」に共通する特徴であり、配当の持続可能性が極めて高いといえます。
さらに、当期純利益は4億5,563万円と過去最高を更新。配当総額は約1億2千万円程度にとどまるため、利益の約4分の3が内部留保として残る構造です。
この点からも、今後の増配余地は十分にあると判断できます。
今後の配当方針予測 ― 成長投資との両立型へ
HPCシステムズの今後の配当方針を予測するにあたり、以下の3つの要素が重要です。
① 「DOE4%」を維持しつつ増配へ
現行のDOE4%方針は継続されると見られます。
しかし、自己資本比率が高止まりしているため、資本効率を意識した段階的な増配が想定されます。
仮に純資産が26億円台を維持し、ROE18%を継続できるなら、DOE4%を維持するための配当金はおおむね30〜32円程度に引き上げても財務的に無理はありません。
よって、2026年6月期には30円台前半の配当が実現する可能性が高く、同社にとっては「安定配当から漸進的増配へ」の転換期となるでしょう。
② 成長投資とのバランスを重視
同社はAI・クラウド・エッジ分野での技術開発を進めており、研究開発投資と人材採用に積極的です。
特に、S³ as a Service(System・Science・Cloud)の各領域でのサービス拡張が今後の収益源になるため、成長投資との両立型配当政策が続くと考えられます。
これは、短期的な高配当よりも「事業成長に伴う持続的な増配」を重視する投資家にとって、むしろ望ましい姿勢です。
高ROEを背景に、投資→成長→利益→還元というサイクルが自然に回る構造が整いつつあります。
③ 自己株式取得の可能性
有価証券報告書にも「財務の健全性や株価水準を勘案し、自己株式の取得を機動的に実施」と明記されています。
現状のキャッシュ水準を考えると、株価が下落局面に入った場合には自己株式買付による株主還元強化を行う可能性が高いです。
これにより1株あたり利益(EPS)が向上し、将来の増配余力がさらに高まることになります。
投資家にとっての注目ポイント
- 配当性向25%前後の安定ライン
無理のない範囲で配当を維持しており、減配リスクは極めて低い。 - DOE4%目安の一貫性
市場環境に左右されない、長期志向の株主還元姿勢。 - ROE18%の高収益体質
配当余力を支える高い収益性。 - 現金水準の高さと有利子負債の少なさ
財務的な安全性が配当継続の土台。 - 今後の増配期待
30円台への配当引き上げは現実的なシナリオ。
将来展望 ― 「安定成長型配当銘柄」への進化
今後のHPCシステムズは、短期的には成長投資を優先しつつも、持続的な増配トレンドを描いていくと予想されます。
同社の事業モデルは研究開発支援・AI・クラウドという成長分野に直結しており、景気の波に強いストックビジネスへと進化しています。
これにより、業績の安定性が増すと同時に、毎期の配当判断もより予測可能になります。
また、DOE基準による還元策は、業績変動時でも一定の配当を維持できるメリットがあり、FIREや長期配当投資を志向する個人投資家にとって極めて魅力的です。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
HPCシステムズ株式会社は、日本株全体の中でも「安定配当と成長性の両立」が際立つ企業であり、長期投資・配当再投資を狙う投資家にとって★4つの高評価に値します。
まず配当利回りについては、2025年6月期の1株当たり配当金が28円、株価水準を考慮した利回りは約2%前後と、東証グロース市場の平均(約1.3%)を上回る堅実な水準です。高配当株というよりは「成長と安定の中間型」であり、安定志向の個人投資家にとって十分魅力的です。
次に配当の持続性に関しては、DOE4%基準を明確に掲げた安定配当方針を採用しており、業績が一時的に変動しても配当額を大きく減らすリスクは極めて低いと考えられます。自己資本比率57.7%・ROE18%という堅固な財務体質に加え、営業キャッシュフローも毎期黒字を維持しており、配当の原資に余裕がある点が大きな強みです。
さらに連続増配の実績面では、上場以来ほぼ毎期25円の安定配当を継続し、2025年に3円増配(25円→28円)を実施しています。ここ数年で業績が着実に拡大していることを踏まえると、今後も30円前後への段階的増配が見込まれます。配当性向25%と控えめで、利益成長に応じて増配余地が十分にある点は、長期保有者にとって極めてポジティブです。
総合的に見ると、HPCシステムズは「高利回り銘柄」ではないものの、減配リスクの低さと中期的な増配期待を両立しており、配当再投資による長期複利効果を狙うには理想的な条件を備えています。特に東証グロース上場企業の中では珍しく、配当方針の透明性と財務の安定性を両立している点が高評価の決め手です。
したがって、他の日本株と比較した場合、配当水準そのものは平均的ながら、「持続性・信頼性・将来性の高さ」で一歩抜きん出ているといえます。安定成長と配当を両立する“長期配当投資の優等生”として、★5満点中の★4つ評価(やや上位クラス)が妥当です。