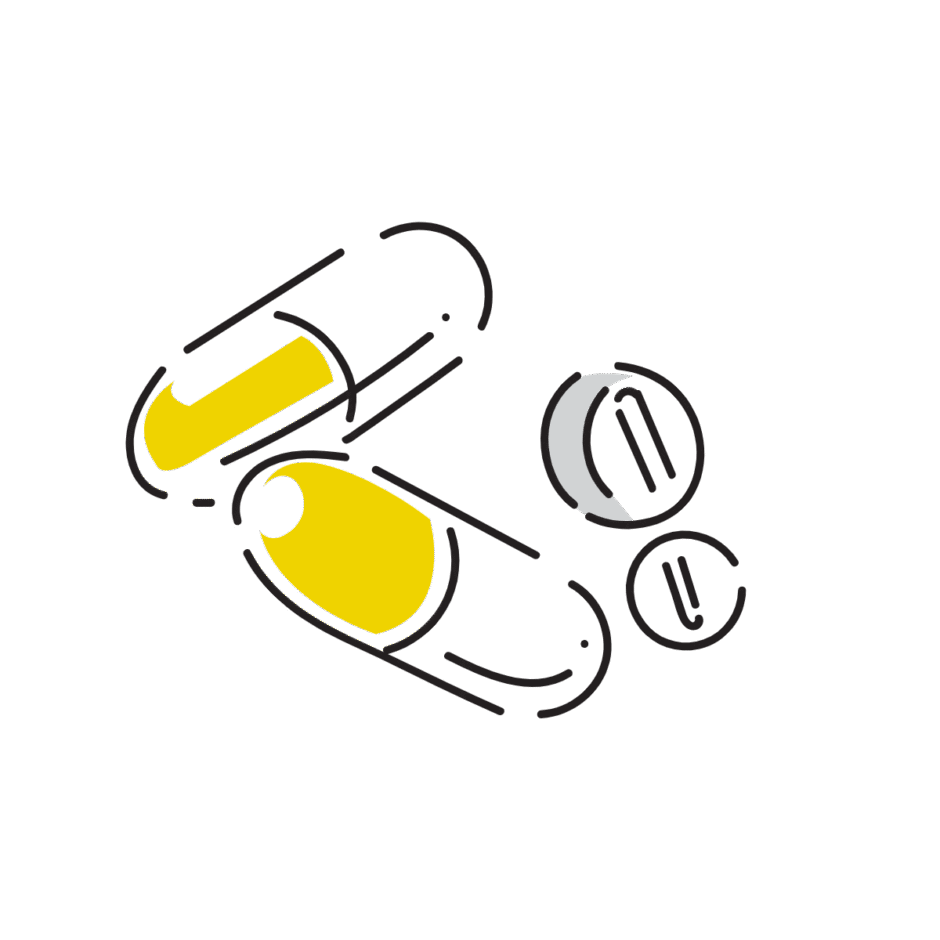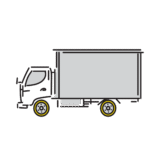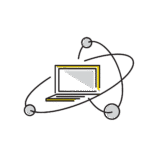企業概要
事業内容とリスク
株式会社キャンバス(CanBas Co., Ltd.)は、がん治療に特化した創薬ベンチャー企業です。独自の「創薬エンジン」と呼ばれる技術基盤を活かし、抗がん剤の研究・開発を一貫して行っています。主な研究領域は、がん細胞の分裂や免疫応答の仕組みに着目した抗がん剤であり、自社での基礎研究から臨床試験、さらには新薬承認を目指す後期臨床開発までを担っています。
同社の主力パイプラインは、以下の2つです。
- CBP501:がん細胞内のカルモジュリンというタンパク質の機能を調整し、免疫系抗がん剤の効果を高める「免疫着火剤」として開発中です。特に免疫チェックポイント阻害抗体との併用による膵臓がん治療で、第2相試験を終え、次段階の臨床試験準備を進めています。
- CBS9106:がん細胞の核外輸送に関わるCRM1(XPO1)を可逆的に阻害する化合物で、米Stemline社とのライセンス契約を経て、2025年6月に全権利を再取得しました。今後は基礎研究成果や財務状況を踏まえて再開発方針を検討しています。
さらに、次世代候補として「CBT005」「CBP-A08」「IDO/TDO阻害剤」などの前臨床試験準備も進行中であり、これらが将来の成長を支える柱となります。
ただし、創薬事業には大きなリスクも伴います。医薬品開発は平均15年・数百億円の資金が必要とされる長期プロジェクトであり、成功確率は低いのが現実です。臨床試験の結果次第では開発中止の可能性もあり、また法規制や医療保険制度の変動、競合他社の技術革新によって計画が影響を受ける可能性もあります。同社は複数の候補化合物を同時開発することでリスク分散を図っていますが、資金繰りや臨床試験の遅延は依然として最大の課題といえるでしょう。
今までの業績
過去5年間の業績推移を見ると、同社は一貫して赤字経営を続けています。2021年から2025年までの期間、営業収益はほとんどなく、経常損失は毎期1億円前後、純損失も1億円を超えています。これは、製品販売による収益がまだない段階であり、研究開発費用が先行しているためです。
とはいえ、注目すべきは財務基盤の強化と安定化です。資本金は2021年の約4.9億円から2025年には約8.4億円へと増加し、純資産も約2.9億円まで積み上げています。自己資本比率は95%を超えており、極めて健全な財務構造を維持している点が特徴です。これは継続的な資本増強と市場からの資金調達が成功していることを示しており、創薬企業としての長期戦略を支える基盤となっています。
また、営業キャッシュフローは依然としてマイナスですが、その赤字幅は2024年度以降縮小傾向にあり、開発プロジェクトの効率化が進んでいると考えられます。2025年度には期末現金残高が約28億円と、過去最高水準に達しており、今後数年間の臨床試験資金を十分に確保しています。
株式市場での評価も興味深い動きを見せています。キャンバスの株価は、東京証券取引所グロース市場に上場して以来、2023年に最高値2,975円をつけた後、一時的な調整を経て2025年には1,500円前後で推移しています。これは、主要パイプラインCBP501の臨床進捗に対する期待感が投資家心理を支えているためとみられます。
今後の業績
今後の焦点は、CBP501の「第2b相試験」の成功と承認取得にあります。2024年2月には米国FDAから臨床試験の承認を受けており、膵臓がんという治療ニーズの高い領域で成果を上げられるかが企業価値を大きく左右します。臨床試験の結果次第では、製薬企業との提携によるロイヤルティ収入、または独自販売による初の営業黒字化が見えてくる可能性があります。
また、Stemline社からCBS9106の全権利を取り戻したことは、今後のパイプライン拡充に向けた柔軟な戦略展開を可能にします。自社主導で臨床試験を進めるか、新たな提携先を探すかは、財務体力と市場環境を見極めたうえでの判断になるでしょう。
資金面では、直近の有価証券報告書でも「直接金融による継続的な資金調達」を明記しており、必要に応じて公募増資や新株発行を行う方針です。これは株主希薄化のリスクを伴う一方で、同社のように研究開発を主軸とする企業にとっては避けて通れないプロセスです。
長期的には、「CBP501」「CBS9106」の2本柱に加え、前臨床段階の「CBT005」などの新規候補化合物が中期的な成長エンジンになると見込まれます。また、がん免疫・がん幹細胞など新しい作用機序への研究拡張により、既存抗がん剤との差別化を強化する方針です。
一方で、創薬企業としての宿命である「開発失敗リスク」「法規制変更」「競合の技術進展」などの外部要因は依然として存在します。これに対して同社は、研究開発における外部機関との連携(東京大学医学部附属病院、静岡県立大学など)を通じて、科学的検証とリスク分散を図っています。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | 業種平均(医薬品) | 株式会社キャンバス | 差異(キャンバス-業種平均) | コメント概要 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 7.97% | – | -7.97pt | 赤字継続のためROE算出不可(実質的にマイナス) |
| 総資産経常利益率 | 5.67% | -37.9%(推計) | -43.57pt | 収益ゼロ・費用先行構造による低収益性 |
| 売上高営業利益率 | 13.08% | ―(売上なし) | -13.08pt | 売上未計上のため営業利益率は算出不能 |
| 自己資本比率 | 58.08% | 95.4% | +37.32pt | 業界トップ水準の超高自己資本比率 |
| 配当性向 | 59.92% | 0% | -59.92pt | 無配継続。再投資優先方針による |
| 純資産配当率 | 4.74% | 0% | -4.74pt | 利益剰余金の蓄積段階のため未配当 |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)
医薬品業界の平均ROEは7.97%と、資本効率の高さを示しています。これは、特許品や医薬品販売による高収益構造が背景にあります。一方、キャンバスは創薬段階のため当期純損失が続いておりROEは実質的にマイナスです。
2025年6月期の純損失は約1.16億円(前期比▲4%改善)ですが、営業収益が未計上のため、資本効率を評価する段階には達していません。
ROEが低い(あるいはマイナス)理由は、長期の研究開発投資による「先行赤字構造」にあります。創薬企業は製品上市まで10年以上の時間を要し、開発費を積み重ねながらも当面は収益を生まないため、資本の回転効率は著しく低下します。
しかし、ROEの低さが必ずしも「経営効率の悪化」を意味するわけではありません。キャンバスは継続的な増資により資本を積み上げ、将来の大型収益(新薬ライセンス収入・ロイヤルティ)を見越した長期的な構造を採用しています。したがって現時点では「収益性」よりも「研究継続能力」が重視されるフェーズといえるでしょう。
② 総資産経常利益率(ROA)
業界平均の総資産経常利益率は5.67%であり、製薬大手では研究投資を吸収しても安定的な利益を出せる体質を持っています。
一方で、キャンバスのROAは約-37.9%(経常損失11.5億円/総資産30.5億円)と大幅なマイナスです。これは典型的な創薬ベンチャーの構造であり、総資産の多くが現金・預金(約28億円)と研究開発資産に偏っているためです。
つまり、同社はまだ資産を「利益を生む装置」として活用していない段階にあります。今後、CBP501の臨床成功やライセンス契約が進展すれば、保有資産が収益を生み出す「生産資産」へと転換し、ROAは急回復する可能性があります。
投資家の視点から見ると、現在のROAマイナスは「収益ゼロ期の研究型企業としての宿命」であり、短期的な収益性ではなく将来のキャッシュイン(提携金・上市収入)に期待を置くべきフェーズです。
③ 売上高営業利益率
医薬品業界の平均営業利益率は13.08%で、これは産業全体でも高水準です。特許期間中の医薬品は高い利益率を確保できるためです。
一方、キャンバスは営業収益がほぼゼロのため、この指標は算出不能です。したがって現時点では「利益率」ではなく、「研究開発進捗率」で事業パフォーマンスを評価するのが適切です。
ただし、創薬ベンチャーの場合、第2相・第3相臨床試験の成功後に製薬企業との提携が成立すれば、一時的に数十億円単位の契約一時金(アップフロント収入)が発生し、単年度の営業利益率が跳ね上がることがあります。
そのため将来的には、「黒字転換→営業利益率大幅上昇」という急変動型の財務構造が予想されます。
現段階では赤字であっても、CBP501の臨床成功・提携実現によって業績構造が一変する「爆発的収益化ポテンシャル」を内包している点が、創薬型ベンチャーの最大の魅力といえます。
④ 自己資本比率
ここがキャンバス最大の強みです。自己資本比率は95.4%と業界平均(58.08%)を大きく上回り、ほぼ無借金経営を実現しています。創薬企業では一般的に資金繰りリスクを抱えるケースが多い中、同社は複数回の増資で資本を厚く積み上げ、安定した研究継続体制を確保しています。
自己資本比率が高いことは、資金調達コストの低減だけでなく、投資家に対する「倒産リスクの低さ」を示します。特に、CBP501などの臨床試験が長期化した場合でも、資金ショートの可能性が低く、開発中断リスクを最小化できる点は評価ポイントです。
他方で、高自己資本比率=資本効率の低下を意味する側面もあります。今後の課題は、調達した資本をどのように収益化につなげるか、すなわち「資本を利益に変える仕組みづくり」です。臨床データの成果をもとにした提携契約の獲得が、まさにこの転換点となるでしょう。
⑤ 配当性向
医薬品業界全体の平均配当性向は59.92%と高く、製薬大手は安定したキャッシュフローを背景に株主還元を重視しています。
しかし、キャンバスは創業以来一度も配当を実施していません(配当性向0%)。これは企業戦略上当然の判断です。現時点での利益はゼロ、むしろ開発費用が先行しており、得られる資金はすべて研究開発と臨床試験に再投資されています。
創薬企業にとって最初の黒字転換までに10年以上を要するのは一般的であり、配当よりもまず「価値の創造=新薬承認」が優先されます。将来的にCBP501が承認・販売に至れば、ロイヤルティ収入を財源に初配当が期待されます。その時点での配当性向は、一般製薬企業の平均(約60%)に近づく可能性もあります。
現段階では「無配」ではあるものの、これは株主還元の欠如ではなく、価値創出前の長期投資期間にある企業特有の合理的判断といえます。
⑥ 純資産配当率
業界平均4.74%に対し、キャンバスは0%。純資産配当率(株主資本に対する配当金の割合)は株主リターンの指標ですが、赤字企業では当然ゼロとなります。
現状では、株主還元よりも「株主価値の増大=株価上昇」を通じたリターンが中心です。実際、キャンバスの株価は2023年に一時2,975円まで上昇し、創薬パイプラインへの期待感が株主リターンを形成してきました。
将来的に配当を実施する場合、純資産の増加ペースが大きいため、少額配当でも配当率が低く見える可能性があります。したがって、投資家は「配当」よりも「時価総額成長」によるリターンを重視するのが現実的です。
配当方針と今後の展望
配当方針と今後の見通し
現在の配当方針
株式会社キャンバス(CanBas Co., Ltd.)の有価証券報告書(第26期・2025年6月期)によると、同社の配当方針は次のように明示されています。
「配当に関しては年1回の期末配当ならびに業績に応じて中間配当を行うことを基本方針としていますが、当社の現時点での事業ステージは、研究開発における先行投資の段階にあるため、創業以来、株主に対する利益配当および剰余金配当を実施していません。また、今後も当面は、資金を企業体質の強化および研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針ですが、株主への利益還元も重要な経営課題と認識しており、今後の経営成績および財政状態を勘案し、配当についても検討していきます。」
つまり、キャンバスは「配当を出さない=無配」方針を継続中です。その理由は明確で、現在は「研究開発先行型の成長段階」にあり、利益を出すよりもまず医薬品の開発と企業基盤の強化を優先しているためです。
また、定款上は以下のように規定されています。
「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会とされています。
これは、制度上は「配当実施が可能な体制」を整えていることを意味します。つまり、「配当を出す準備」はすでに社内制度として整っているものの、実際の財務状況がまだその段階に達していない、というのが現状です。
配当関連指標の現状
2025年6月期時点でのキャンバスの主要財務指標は以下の通りです。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 当期純損失 | △1億1,579万円 |
| 資本金 | 約8億4,679万円 |
| 自己資本比率 | 約95.4% |
| 配当性向 | 0%(無配) |
| 純資産配当率 | 0%(無配) |
これらの数字が示す通り、キャンバスは利益をまだ生み出しておらず、剰余金の配当余地も存在しない状態です。
一方で、自己資本比率が95%を超える超健全な財務体質を維持しており、増資によって研究資金を安定的に確保しています。つまり、短期的な配当余力はないものの、倒産リスクや資金枯渇リスクは極めて低いといえます。
今後の配当方針の見通し
キャンバスの配当方針を考える上で、最も重要なカギを握るのが「開発パイプラインの商業化」です。
現在、同社の主力プロジェクトであるCBP501は膵臓がん向けの臨床試験(第2b相)段階にあり、免疫チェックポイント阻害剤との併用効果が注目されています。この治験が成功し、製薬大手との提携またはライセンス契約が実現すれば、一時金(アップフロント収入)やロイヤルティ収入が発生し、黒字転換と同時に配当実施の可能性が現実味を帯びてきます。
ここで想定される配当方針の変化シナリオを3段階で整理します。
【フェーズ1:研究集中期(~2026年)】
- 現状の無配継続。
- 研究費(R&D費)は年間約10億円規模で、資金はすべて開発に投入。
- 2025年度末時点の現金・預金は約28億円あり、今後2〜3年の開発資金は十分確保済み。
- この間は「配当ではなく企業価値向上への再投資」が最優先方針。
⇒ 配当実施の可能性:0%
【フェーズ2:黒字化前夜(2026〜2028年)】
- CBP501の臨床結果次第でライセンス収入が発生。
- 黒字転換期を迎える場合、配当実施を「検討」段階へ移行。
- ただし、他のパイプライン(CBS9106やCBT005)への再投資が優先される可能性大。
- 仮に黒字化しても、当初は内部留保(研究資金確保)を優先する見込み。
⇒ 配当実施の可能性:30〜40%
【フェーズ3:商業化・安定収益期(2028年以降)】
- 自社販売または提携企業経由でロイヤルティ収入が安定化。
- この段階で初の期末配当実施が期待される。
- 剰余金の範囲内で中間配当の実施も制度的に可能。
- 製薬業界平均の配当性向(約60%)を目指す可能性もあり。
⇒ 配当実施の可能性:70〜80%
長期投資家への示唆
個人投資家や配当金によるFIREを目指す層にとって、キャンバス株は「短期的な配当収益」よりも「中長期的な資本利益(キャピタルゲイン)」を狙うタイプの銘柄です。
現時点では無配ですが、将来の新薬承認・収益化によって株価上昇と配当の両立が見込まれる可能性があります。
また、同社は定款上、株主総会による期末配当決議に加えて取締役会による中間配当の実施も可能であり、黒字転換後の「柔軟な還元政策」を設計できる体制を持っています。
他の創薬ベンチャー(例:オンコリスバイオファーマやペプチドリーム)を参考にすると、黒字化後3〜5年以内に初配当を実施するケースが多く見られます。キャンバスの場合も、2028〜2030年頃に初配当が検討される可能性があります。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
株式会社キャンバス(CanBas Co., Ltd.)は、長期配当狙いの投資先としては「現時点ではおすすめできない」部類に入ります。その理由を、日本株全体の平均的な配当水準と比較しながら解説します。
まず、配当利回りの観点から見ると、キャンバスは創業以来無配を継続しており、現時点での配当利回りは0%です。東証プライム上場企業の平均配当利回りが約2.0〜2.5%、高配当銘柄では4〜5%を超えることを踏まえると、配当収益を目的とする投資家にとっては明確なマイナス要素です。
同社は現在も臨床開発段階にあり、売上を伴う商業活動がまだ始まっていないため、配当を出せる利益構造が存在しません。利益剰余金もほぼゼロであり、仮に黒字化したとしても当面は研究開発資金や内部留保の強化に充当される可能性が高いと考えられます。
次に、配当の持続性という観点では、キャンバスの将来性を一定程度評価する余地があります。同社は自己資本比率が約95%と非常に高く、現金・預金も約28億円を保有するなど、財務の健全性は極めて良好です。これは「資金ショートによる経営破綻リスクが低い」ことを意味し、黒字化さえ達成できれば安定配当へ移行する体力はあります。ただし、それが実現するまでに少なくとも3〜5年、あるいは10年単位の時間がかかる可能性があり、短中期の配当狙いには不向きです。
最後に、連続増配という観点では、比較対象となる実績が存在しません。例えば、武田薬品工業や花王などは20年以上連続で安定的な配当を実施しているのに対し、キャンバスはまだ配当を始めてもいない段階です。そのため、現時点で「連続増配銘柄」としての信頼性を語ることはできません。
総合的に見ると、キャンバスは将来的な成長余力は大きいが、現段階では配当投資銘柄としての魅力は皆無に等しいといえます。CBP501などのパイプラインが承認・上市されれば、数年後に黒字化・初配当というシナリオも描けますが、それまでは「高リスク・無配株」という位置づけになります。
したがって、配当利回りや増配実績を重視する長期投資家にとっては、現時点で★1つの評価が妥当です。今後の臨床成功による業績転換が確認できた段階で、改めて投資対象として再評価するのが現実的でしょう。