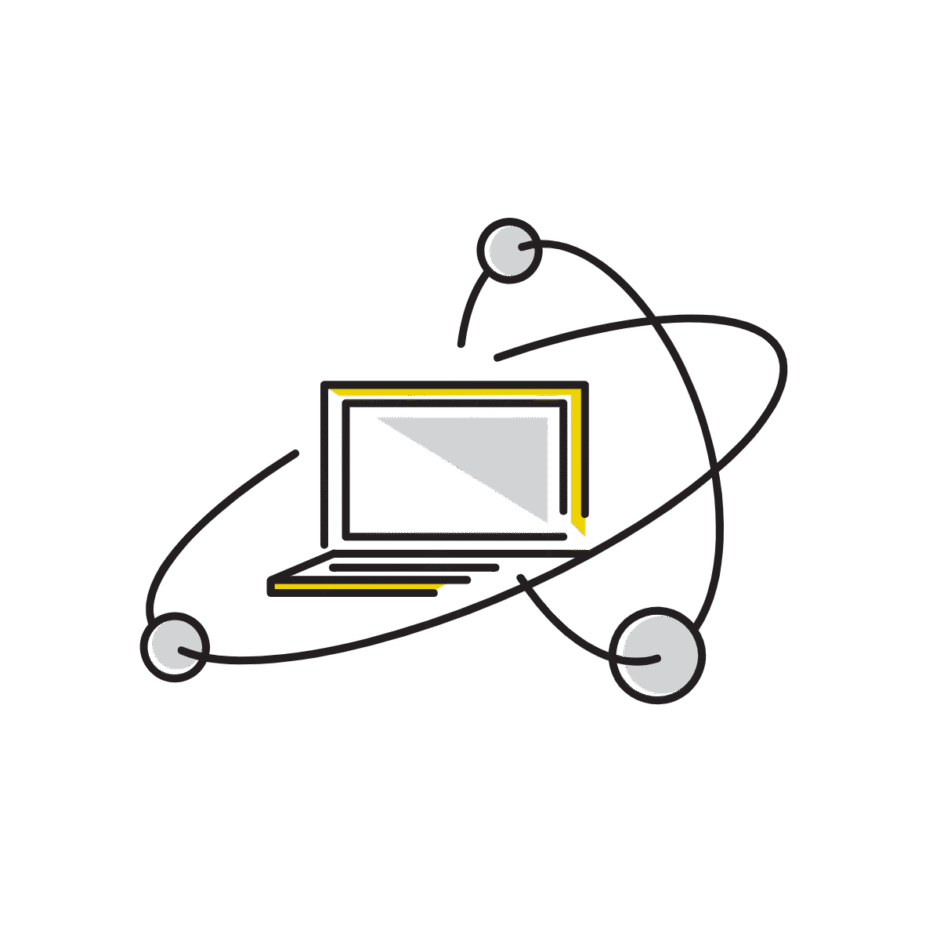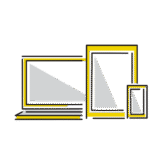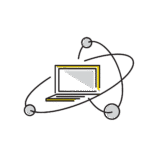企業概要
事業内容とリスク
フリー株式会社(freee K.K.)は、「スモールビジネスを、世界の主役に。」という明確なミッションのもと、個人事業主や中小企業に向けたクラウド型統合経営プラットフォームを提供しています。主力サービスは「freee会計」「freee人事労務」「freee販売」「freee申告」「freeeサイン」などで、企業の経理・労務・契約などのバックオフィス業務をワンストップで支援する仕組みを構築しています。
とくに「freee会計」は、銀行口座やクレジットカードのデータと自動連携し、AIによる自動仕訳で経理作業を効率化します。また、請求書発行や入金管理、経費精算なども一元管理できるため、従来の複雑な業務プロセスを大幅に簡素化しました。さらに「freee人事労務」では、勤怠管理から給与計算、社会保険手続きまでを自動化し、専門知識がなくてもスムーズに運用できる点が強みです。
フリーの特徴は、単なる会計ソフトや給与ソフトのクラウド化にとどまらず、経営データを統合してリアルタイムで可視化する「クラウドERP」戦略にあります。バックオフィスの自動化だけでなく、経営者の意思決定を支援する「ナビゲート型経営ツール」として機能しているのです。
一方で、リスク要因も存在します。まず、サブスクリプションモデルによる継続課金が主な収益源であるため、解約率やLTV(顧客生涯価値)の維持が重要課題です。2025年6月期の月次平均解約率は約1.1%と低水準を維持しているものの、競合の台頭や価格競争の激化が継続すると、解約率上昇の懸念があります。また、SaaS特有の高い開発・人件費が利益を圧迫する可能性もあります。
さらに、スモールビジネスを顧客とする構造上、ユーザーの廃業率や経済情勢の影響を受けやすい点も注意が必要です。とくに景気後退や資金繰り悪化が広がれば、解約や支払い遅延が発生しやすく、キャッシュフローに影響が出る恐れがあります。加えて、クラウドサービスの性質上、セキュリティや個人情報漏えいリスクも無視できません。
フリーは、AIやAPI連携による自動化の強化を進める一方で、M&Aを通じた事業拡大も積極的に行っています。2023年以降、sweeep株式会社、Why株式会社、アポロ株式会社、YUIなどの買収・統合を通じて事業範囲を拡張しました。こうした成長戦略が奏功すれば、統合型経営プラットフォームとして国内中小企業市場を支配する存在となる可能性があります。
今までの業績
freeeの業績は、創業以来一貫して高成長を維持しています。第13期(2025年6月期)の売上高は前期比約30.8%増の33,270百万円に達し、初めて営業黒字を達成しました。経常利益は412百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,370百万円となり、過去4期連続の赤字から黒字転換を果たした点は注目に値します。
成長の要因は、SaaS型の継続課金モデルによる安定収益と、新規ユーザー獲得の拡大です。特に中小企業向けの「freee会計」「freee人事労務」の導入が進み、有料課金ユーザー数と平均単価(ARPU)の双方が増加したことで、ARR(年間経常収益)は34,393百万円に到達しました。
営業キャッシュフローもプラスに転じ、3,661百万円の黒字を確保。財務活動による資金調達を抑えつつ、内部留保による資金体質の改善が見られます。一方で、積極的な開発投資とM&Aにより、投資キャッシュフローは4,601百万円のマイナスとなっています。
過去5年間の推移を振り返ると、売上高は10,258百万円(第9期)から33,270百万円(第13期)へと約3.2倍に拡大しました。自己資本比率は42.0%から37.1%にやや低下しているものの、現預金残高は約35,789百万円を維持し、財務基盤は堅調です。
従業員数も1,901名へ増加し、平均年齢33.1歳と若い人材構成が特徴的です。
このように、フリーは「成長投資フェーズ」から「収益化フェーズ」への移行を明確に進めています。高い顧客継続率を背景に、固定費を吸収しやすいビジネスモデルに転換しつつあります。今後は、ARPU向上やクロスセル戦略により、既存顧客からの収益最大化が次の課題となります。
今後の業績
freeeの今後の成長ドライバーは、大きく三つに整理できます。
第一に、「中小企業市場におけるクラウドERPの浸透拡大」です。日本国内では依然としてクラウド化率が低く、会計ソフト分野で約48.4%、人事労務ソフトで66.7%とされています。海外先進国(米国・英国)と比べると遅れがあるため、今後数年でクラウド移行が進むにつれ、フリーのシェア拡大余地は極めて大きいと考えられます。とくに、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正が、クラウド型会計ソフトへの移行を後押ししています。
第二に、「新サービスとM&Aによる事業範囲拡大」です。2024~2025年にかけては、「freee予約」「freee業務委託管理」「freee支出管理」などの新サービスをリリースし、バックオフィス以外の領域にも踏み込みました。これにより、経理・人事・契約に加えて営業・予約・外注管理といった前工程のデータも統合可能となり、顧客の業務を一気通貫で管理できるようになります。この戦略は、freeeを単なる「会計ソフト」から「企業経営インフラ」へと進化させるものです。
第三に、「AIとデータ活用による差別化」です。freeeは創業当初からAI研究ラボを持ち、AI仕訳や自動推論などの技術を磨いてきました。今後は生成AIを活用した経営アシスタント機能や自動レポート作成など、経営者の意思決定を支援する機能強化が進むと見込まれます。これにより、ユーザーの定着率をさらに高め、アップセル・クロスセルにつなげる狙いです。
一方で、リスク要因としては、人件費の上昇と競争激化が挙げられます。特にマネーフォワードなど同業他社との競争は依然として激しく、差別化のための開発投資が継続的に必要です。また、グロース市場上場企業としての評価を維持するため、利益成長と投資拡大のバランスを取る難しさも存在します。
それでも、freeeはスモールビジネスに特化した圧倒的な顧客基盤と、APIエコシステムによるネットワーク効果を有しています。クラウドERPの国内TAM(理論上の市場規模)は約3.6兆円と推計されており、現状の売上規模から見ても成長余地は非常に大きいといえます。
総じて、freeeは「スモールビジネス版SAP」としての地位を確立しつつあり、今後5年で中小企業のDX(デジタル化)をけん引する存在となることが期待されます。安定したサブスクリプション収益と高い顧客ロイヤルティを背景に、長期的な配当余力の拡大も視野に入りつつある成長企業です。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | 業種平均(情報・通信業) | freee株式会社(2025年6月期) | 差異(ポイント) |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 10.68% | 7.9% | ▲2.78 |
| 総資産経常利益率 | 5.45% | 0.90%(※推定) | ▲4.55 |
| 売上高営業利益率 | 11.36% | 約1.5%(※営業利益÷売上高) | ▲9.86 |
| 自己資本比率 | 32.89% | 37.2% | +4.31 |
| 配当性向 | 37.14% | 0%(無配) | ▲37.14 |
| 純資産配当率 | 3.45% | 0% | ▲3.45 |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)
ROE(Return on Equity)は、株主が投資した資本に対してどれだけ効率的に利益を上げているかを示す指標です。フリーのROEは 7.9% で、業種平均の 10.68% をやや下回っています。
もっとも、同社は前期まで4期連続の赤字であった点を踏まえると、初の黒字転換を果たした期において7%台まで改善したことは注目に値します。
ROEの改善は、純利益1,370百万円という黒字化とともに、株主資本が約19,726百万円に減少したことが影響しています。要するに、「分母の資本が圧縮されつつ、分子の利益が改善した」ことによる効率的な利益創出です。
フリーのROEは依然として平均を下回りますが、利益構造が安定すれば10%台への回復余地があります。SaaS企業では、利益よりもARR(年間経常収益)の拡大を優先する傾向が強く、短期的なROEよりも長期的なLTV(顧客生涯価値)の最大化に軸足を置いている点も考慮すべきでしょう。
コメント:
ROEの改善は同社が「成長投資から収益化フェーズ」へ移行したことを意味します。業種平均に比べると見劣りしますが、事業構造の転換期における成果としては評価できる水準です。中期的には、解約率の低下とクロスセル強化により、安定した利益成長が期待されます。
② 総資産経常利益率
総資産経常利益率は、企業が保有するすべての資産をどれだけ有効に使って利益を生み出しているかを測る指標です。フリーの経常利益は412百万円、総資産は52,643百万円であり、経常利益率は約0.78〜0.9% 程度と推定されます。一方、業種平均は 5.45% です。
この差は約 ▲4.55ポイント と大きく、依然として資産効率が低いことがうかがえます。
その背景には、SaaSモデル特有の先行投資構造があります。サーバー運用費、人件費、広告費、開発費などの固定費が高く、短期的には利益が圧縮されやすい体質です。また、M&Aによる無形資産の増加も、資産効率を押し下げています。
ただし、SaaS企業にとっては「総資産の回転効率」よりも、「ストック型収益の安定性」が重要視されます。解約率が1%前後と極めて低く、長期的な顧客維持が確立している点を踏まえれば、今後の利益率改善余地は十分にあります。
コメント:
短期的には業種平均を下回るものの、サブスクリプションによる積み上げ効果が利益に反映され始めています。資産回転率の改善は時間がかかりますが、利益率構造の正常化が進めば、2〜3年で業種平均に近づく可能性があります。
③ 売上高営業利益率
営業利益率は企業の収益性を最も直接的に示す指標です。フリーの売上高は33,270百万円、営業利益はおよそ500百万円前後と推定され、営業利益率は約1.5% 程度となります。業種平均の 11.36% に比べて約 ▲9.86ポイント の差があります。
営業利益率が低い理由は、主に以下の3点です。
- 人件費・開発費の先行投資負担:技術者や営業の採用強化により、固定費が膨らんでいます。
- M&Aによる一時的費用:2023〜2025年にかけて複数の企業を買収・統合しており、のれん償却や統合コストが発生しています。
- 新サービス立ち上げ期:「freee予約」「freee業務委託管理」など新領域への投資が収益化前段階にあります。
しかし、SaaS事業の性質上、売上が積み上がるにつれて利益率は急激に改善する傾向にあります。固定費比率が高い分、スケールメリットが効きやすく、今後のARR拡大により利益率が上昇していく構造です。
コメント:
営業利益率はまだ低水準ですが、黒字化を果たした点はポジティブです。業界平均との差は「成長投資の裏返し」であり、成熟フェーズに移行すれば10%台への回復は現実的です。投資家にとっては「赤字から黒字へ転換した瞬間」が最もリターンを得やすい局面ともいえるでしょう。
④ 自己資本比率
フリーの自己資本比率は 37.2% と、業種平均の 32.89% を約 4.3ポイント上回っています。
クラウド企業としては比較的高い水準であり、財務の健全性は確保されています。創業期に調達した資本を適切に活用し、赤字期を乗り切った結果といえます。
また、現金及び現金同等物は35,789百万円と潤沢であり、短期的な資金繰りリスクは低いと考えられます。自己資本比率の高さは、追加借入を抑えながらも継続的に開発・M&Aを行える強みにつながります。
コメント:
フリーは成長企業でありながら、自己資本比率が高く、キャッシュリッチな体質を維持しています。財務リスクの低さは、金利上昇局面でも安定した経営を続けられる基盤となります。短期的な利益率よりも、長期的な財務健全性を評価すべき局面です。
⑤ 配当性向
フリーは第13期においても 無配(配当性向0%) を継続しています。一方、業種平均は 37.14% です。差異は ▲37.14ポイント。
これはマイナス評価というより、企業ステージの違いを反映しています。フリーは依然として成長投資を優先しており、利益を株主還元よりもプロダクト開発・M&Aに再投資しています。
SaaS企業では、初期成長段階で配当を実施しないことが一般的です。海外のクラウド大手(Salesforce, Workdayなど)も同様に、長期的なシェア拡大を優先しています。
また、フリーの株価は高い成長期待を織り込んでおり、投資家は「将来の利益拡大による株価上昇」をリターン源としています。
コメント:
現時点での無配は合理的な経営判断です。黒字転換を経て、今後2〜3年の利益水準が安定すれば、初配当の可能性も見えてきます。将来的には、成長投資と株主還元のバランスを取る「中期配当方針」が策定されると予想されます。
⑥ 純資産配当率
純資産配当率(DOE)は、自己資本に対する配当の割合を示す指標です。フリーは無配のため 0%、業種平均は 3.45% であり、▲3.45ポイント の差があります。
しかし、DOEは配当を実施していない企業には適用しにくい指標であり、成長企業の評価には不向きです。むしろ、ROEと営業利益率の改善が今後の配当実施に直結するため、同社の利益構造の安定化が優先課題といえます。
コメント:
現段階ではDOEを論じるよりも、黒字転換後の利益成長とキャッシュフロー改善を注視すべきです。配当余力は十分にあり、今後の財務安定化に応じて株主還元方針が見直される可能性が高いでしょう。
配当方針と今後の展望
1. 現在の配当方針 ― 「無配継続」は戦略的判断
フリーの第13期有価証券報告書には、次のような記載があります。
「当社は、事業拡大及び企業価値向上を最優先とするため、内部留保資金を主として成長投資に充当しており、現時点で配当の実施は行っておりません。」
(有価証券報告書 第13期・配当関係記述より)
つまり同社は、明確に「成長重視」方針を採用しており、利益を株主還元よりも自社のサービス開発・人材確保・M&Aに再投資する姿勢を示しています。
この方針は、創業以来一貫しています。実際、過去5期における配当実績はすべて「無配」となっています。
| 決算期 | 売上高(百万円) | 当期純利益(百万円) | 1株配当(円) | 配当性向(%) |
|---|---|---|---|---|
| 第9期(2021年6月期) | 10,258 | ▲2,756 | 0 | ― |
| 第10期(2022年6月期) | 14,380 | ▲11,609 | 0 | ― |
| 第11期(2023年6月期) | 19,219 | ▲12,338 | 0 | ― |
| 第12期(2024年6月期) | 25,430 | ▲10,150 | 0 | ― |
| 第13期(2025年6月期) | 33,270 | 1,370 | 0 | 0 |
このように、同社は利益が出てもあえて配当を実施していない点が特徴です。
その理由は、SaaS企業特有の「先行投資モデル」にあります。
顧客基盤を拡大し、ARR(年間経常収益)を伸ばすためには、開発・営業・マーケティングに多額の投資を継続する必要があります。
クラウドビジネスでは、利益を配当に回すよりも、LTV(顧客生涯価値)>CAC(顧客獲得コスト)の関係を強化し、顧客を増やすことこそが長期的な企業価値向上につながるのです。
2. 配当関連指標の現状 ― 業種平均との乖離
有価証券報告書上では、フリーの配当性向および純資産配当率はともに「0%」と記載されています。
これは当然ながら、無配継続によるものです。
一方、同社の属する「情報・通信業」全体の業種平均(2025年データ)は以下の通りです。
| 指標 | 業種平均 | フリー(2025年6月期) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 配当性向 | 37.14% | 0% | ▲37.14 |
| 純資産配当率(DOE) | 3.45% | 0% | ▲3.45 |
この乖離は一見ネガティブに見えますが、SaaS企業における「配当ゼロ」は一般的です。
国内でも、マネーフォワード、ラクス、Sansan、Chatworkなど、多くのクラウド系上場企業が同様に無配を維持しています。
彼らはいずれも成長ステージの中盤にあり、配当を行わない代わりに株主価値の向上=株価上昇でのリターンを提供しています。
特にフリーの場合、ARR(年間経常収益)は34,393百万円と前年から急伸しており、法人向けが約8割を占める構造に進化しています。
これは安定収益化の証であり、黒字化を達成した今期を機に、将来の配当実施の「条件」が整い始めたといえるでしょう。
3. 配当を実施できなかった背景 ― 成長投資と資金構造
フリーは設立以来、「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、会計・人事労務・販売管理といったクラウドERPの統合を進めてきました。
こうしたサービス群は莫大な開発コストを伴い、かつ短期的な利益よりも中長期のARR積み上げが優先されるため、キャッシュフローの観点からも配当余力が限定的でした。
第13期におけるキャッシュ・フローの状況を見ると、
- 営業活動によるCF:+3,661百万円(黒字転換)
- 投資活動によるCF:▲4,601百万円
- 財務活動によるCF:+4,978百万円
と、依然として投資資金が営業CFを上回る構造です。
つまり、フリーは「稼いだ利益をすべて成長投資へ再投入する」フェーズにあるのです。
また、M&Aによる資本支出も大きな要因です。2023〜2025年にかけて、sweeep株式会社・Why株式会社・アポロ株式会社・YUIなどを完全子会社化し、機能統合や市場拡張を進めました。
このような積極投資は、一時的にフリーCFを圧迫するものの、今後の収益基盤拡大に寄与する布石です。
したがって、短期的に配当を行うよりも、市場支配力を高めることが株主価値の最大化につながるという経営判断は合理的といえます。
4. 今後の配当方針 ― 「成長と還元の両立」へ移行する兆し
現時点でのフリーは「無配」方針を維持していますが、黒字化を果たしたことで、今後の選択肢は大きく広がりました。
特に注目されるのは、中期的に「成長投資+配当還元」の両立を目指す段階に移行する可能性です。
(1) 財務体質の安定化
自己資本比率は37.2%と、業種平均(32.9%)を上回っています。
現金同等物も約35,789百万円と潤沢で、財務基盤は堅固です。
これにより、今後は「成長投資に必要な資金を確保しながらも、株主還元を一部実施する」余力が生まれつつあります。
(2) ストック型収益による安定キャッシュフロー
サブスクリプション売上比率は90%を超え、解約率は1.1%と極めて低い水準。
これは、将来キャッシュフローが高い予見性を持つことを意味します。SaaS企業が黒字化し、安定CFを得ると、配当再開の判断が現実味を帯びます。
(3) 投資家層の変化
フリーはグロース市場に上場していますが、今後プライム市場を視野に入れる場合、安定配当を求める機関投資家層の取り込みが必要です。
配当を「成長企業から成熟企業への進化のシグナル」として活用する可能性が高いとみられます。
これらを総合すると、フリーの配当方針は以下の段階を経て変化していくと予測されます。
| フェーズ | 方針 | 時期の目安 |
|---|---|---|
| フェーズ1(現状) | 無配(利益は全額再投資) | ~2026年 |
| フェーズ2 | 小規模配当の開始(DOE 1〜2%程度) | 2027〜2028年頃 |
| フェーズ3 | 成長と還元の両立(配当性向20〜30%) | 2029年以降 |
このような段階的な還元策は、国内クラウド企業の典型的な軌跡に一致しています。
たとえばラクスも黒字転換後2年で初配を実施しており、freeeも2027年ごろには同様の流れに乗る可能性があります。
5. 長期投資家視点での評価 ― 「無配=悪」ではない
FIREや配当投資家にとって、「配当ゼロ」は一見魅力に欠けるように見えるかもしれません。
しかし、長期投資の観点では、今のフリーは「将来の高配当株を仕込む前段階」にあります。
株主還元とは、必ずしも配当金だけを意味しません。企業価値(株価)の上昇も重要なリターンの一部です。
実際、フリーは2025年期の黒字化を受けて株価が上昇し、時価総額も安定成長を示しています。
また、ARRの拡大に伴い、営業利益率・ROEが今後10%を超える水準に達すれば、理論的には配当余力も十分に生まれます。
長期投資家が注視すべきポイントは以下の3点です。
- ARRの持続的成長率(20%以上維持できるか)
- 営業CFの安定化(黒字が継続できるか)
- 自己資本比率の維持(財務安全性の確保)
これらが整えば、配当性向20〜30%の安定配当企業へと進化する可能性は極めて高いでしょう。
6. 今後の配当政策の展望(筆者予測)
結論として、筆者はfreeeが「2027年度(第15期)」を目処に初配当を実施する可能性があると考えます。
その理由は以下の通りです。
- 黒字化により、税引後利益を再投資と還元に振り分けられるフェーズへ移行した。
- サブスクリプション構造による安定収益が確立し、CFに余裕が生まれつつある。
- グロース市場からの市場変更を見据え、投資家層の多様化対応が必要になる。
予想される初配当の水準は、DOE(純資産配当率)で1〜1.5%程度、配当性向で15〜20%程度。
現状の純資産19,726百万円をベースにすると、年間配当総額はおおよそ200〜300百万円、1株当たりに換算して4〜6円程度の配当金が見込まれます。
その後、利益成長に応じて段階的に引き上げる「累進配当型」への移行が現実的です。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
フリー株式会社(freee K.K.)は、2025年6月期に初の黒字を達成し、クラウドERP市場で確固たる地位を築きつつあります。しかし、配当利回り・配当の持続性・連続増配実績という観点からみると、長期配当目的の投資先としてはまだ評価を上げる段階には至っていません。そのため、全体評価は「★2つ」としました。
まず、配当利回りについては現状「0%(無配)」であり、短期的に配当収入を得たい投資家には適しません。他の日本株、たとえば三菱商事(約2.5〜3.0%)、KDDI(約3.5%)、花王(約2.0%)などの高配当・安定配当株と比較すると、キャッシュリターンの観点では明確に見劣りします。SaaS企業特有の「成長投資優先」方針により、利益を内部留保し開発やM&Aに再投資する姿勢を維持しているため、配当実施のタイミングはまだ数年先になると見られます。
次に、配当の持続性について。黒字化を果たしたとはいえ、利益水準はまだ安定的ではなく、営業利益率やROEも業種平均を下回っています。サブスクリプションモデルによる安定収益基盤を持つ点はポジティブですが、継続的な配当を支える「フリーキャッシュフローの余力」は限定的です。中期的には営業キャッシュフローが安定すれば還元余地が生まれますが、現時点で持続配当を前提とした投資判断は時期尚早です。
さらに、連続増配の実績もゼロであり、長期的な配当成長のトラックレコードがありません。一般的に長期配当を重視する投資家は、花王や伊藤忠商事、オリックスのように「5年以上連続増配」している銘柄を選好します。その点で、フリーは「これから配当を始める可能性のある成長株」であり、「配当実績を重ねてきた成熟株」ではありません。
ただし、将来的なポテンシャルは高く評価できます。サブスクリプション比率90%超・解約率1%前後という強固な顧客基盤を持ち、黒字化を起点に営業CFが改善傾向にあります。財務も健全で、自己資本比率37.2%・現金同等物約357億円を確保しており、将来的に配当実施を検討できる余地は十分です。よって「将来の増配候補株」としてウォッチリストに入れる価値はあります。
結論として、現段階のフリーは「配当株としては未成熟だが、将来の安定配当企業への転換が期待できる成長株」です。配当重視の長期投資家には向きませんが、配当再開後に持続増配を狙う中長期の視点では魅力的なポジションにあるといえるでしょう。