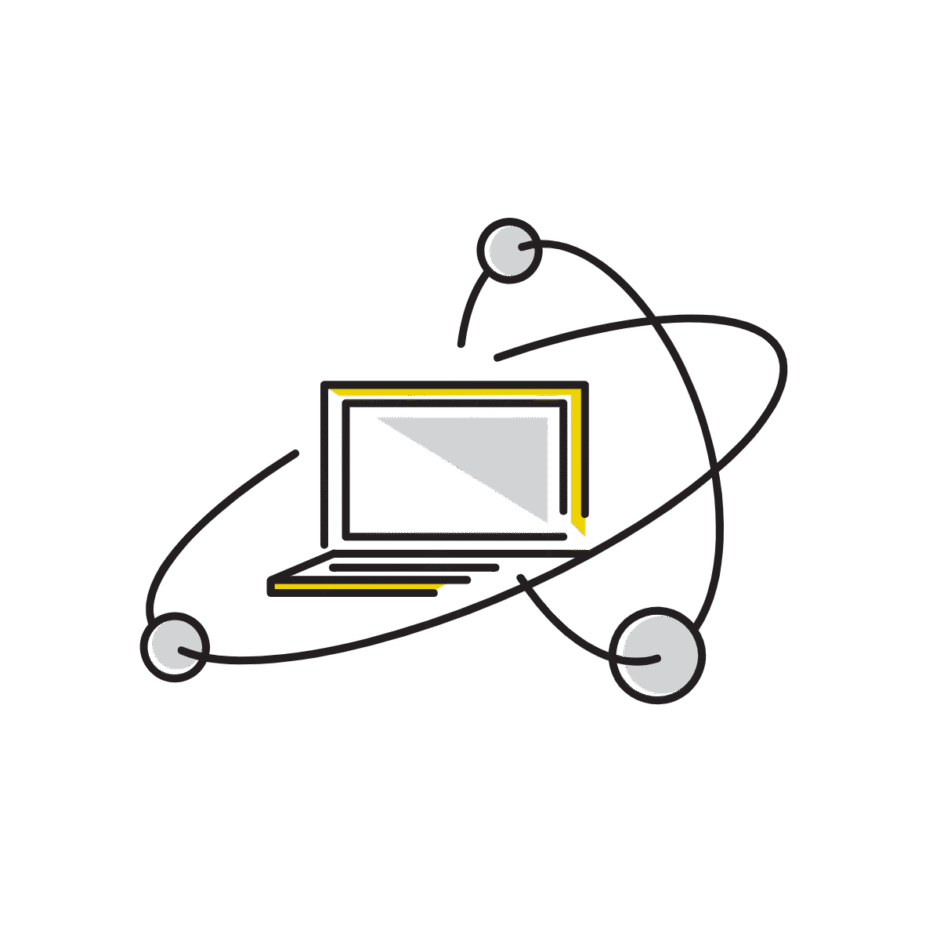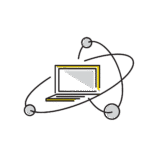企業概要
事業内容とリスク
株式会社ブレインパッド(BrainPad Inc.)は、2004年創業のデータ活用専門企業です。設立当初から「データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる」というパーパスを掲げ、AI・DX・ビッグデータの黎明期から企業の経営改善を支援してきました。累計支援実績は1,300社を超え、金融・小売・製造・サービスなど幅広い業種にデータ活用を根付かせてきた実績があります。
ブレインパッドの事業は大きく「プロフェッショナルサービス事業」と「プロダクト事業」の2本柱です。
プロフェッショナルサービス事業では、データ分析やシステム開発、AI導入コンサルティングなどを通じ、顧客企業の課題解決と内製化支援を行っています。生成AIを活用した業務効率化、データ分析人材の教育、組織全体のデータ活用文化の醸成まで一貫して支援できる点が特徴です。
プロダクト事業では、同社独自のSaaS製品群を展開しています。代表的なものに、高精度レコメンドエンジン「Rtoaster」、自然言語検索が可能な「Rtoaster GenAI」、LINE特化型マーケティング自動化ツール「Ligla」、そしてマーケティングオートメーションプラットフォーム「Probance」などがあります。これらは企業の顧客データを統合・分析し、パーソナライズドな顧客体験を提供するための基盤を構築するツール群です。
リスク要因としては、主に以下の3点が挙げられます。
- 人材確保リスク
データサイエンスやAIエンジニアリング人材は市場全体で不足しており、採用・育成の遅れが業績に影響する可能性があります。同社は教育体系「BrainPad HR Synapse Initiative」を整備し、データ分析力・哲学的思考力・実践力を兼ね備えた人材育成を進めています。 - 技術変化と競争の激化
生成AIや新しいアルゴリズムの台頭により、従来の分析支援やレコメンドサービスが陳腐化するリスクがあります。これに対し、AIエージェント事業や新製品Rtoaster GenAIなど、AI時代に対応した製品ポートフォリオの拡張を進めています。 - 個人情報保護とシステムリスク
プロダクト事業ではCookie規制やデータ保護法改正への対応が求められます。また、SaaS型製品のシステム障害リスクも存在します。ブレインパッドはISMSおよびプライバシーマーク認証を維持し、データ管理体制を強化しています。
同社はこれらのリスクを認識した上で、構造改革期(2024〜2026年度)を掲げ、経営モデルを高利益体質へと転換するフェーズにあります。
今までの業績
過去5年間の業績推移を見ると、ブレインパッドは着実に成長を遂げています。
| 決算期 | 売上高(千円) | 経常利益(千円) | 当期純利益(千円) | ROE(%) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年6月期 | 7,098,397 | 888,862 | 537,829 | 12.2 | 80.9 |
| 2022年6月期 | 8,561,311 | 1,166,580 | 803,246 | 16.9 | 78.8 |
| 2023年6月期 | 9,477,711 | 830,203 | 596,495 | 12.1 | 77.0 |
| 2024年6月期 | 10,022,389 | 1,336,282 | 949,787 | 17.9 | 78.3 |
| 2025年6月期 | 11,085,684 | 1,510,719 | 1,032,753 | 17.9 | 78.2 |
このデータから読み取れるのは、2023年に一時的な減益があったものの、2024年以降に利益率を回復し、堅実な成長軌道に戻っている点です。2025年6月期には、売上高が前年同期比10.6%増の約110億円、当期純利益も1億円を超えています。ROE(自己資本利益率)は17.9%と高水準で推移しており、資本効率の高さが際立ちます。
セグメント別では、以下のような特徴が見られます。
- プロフェッショナルサービス事業
データ分析やAIコンサルティング領域が堅調で、売上高8,336,984千円(前年比13.0%増)、セグメント利益は3,565,818千円(同22.5%増)と大幅な増益を達成しました。リーダー層の育成とプロジェクト管理の改善が利益率向上につながっています。 - プロダクト事業
LINEマーケティングツール「Ligla」やRtoasterシリーズの売上が伸長。売上高3,435,870千円(前年比7.9%増)、セグメント利益は870,457千円(同13.2%増)と安定的に成長しています。
キャッシュフロー面でも、営業活動によるCFは1,350,975千円と高水準を維持し、財務活動によるCFはマイナス870,740千円。自己資本比率は約78%と財務体質は堅牢です。配当は1株当たり8円を継続しており、配当性向は16.5%と控えめながら安定しています。
このように、収益性・成長性・財務健全性のバランスが取れた経営が続いており、長期的な配当狙いの投資対象として信頼性が高い企業といえます。
今後の業績
ブレインパッドの中期経営計画(2024〜2026年度)は「構造改革期」と位置づけられています。その狙いは「組織拡大による成長」から「利益重視の経営」への転換です。
計画の主なポイントは以下の通りです。
- EBITDAマージンの向上と高利益体質化
売上高の拡大以上に、利益率(EBITDAマージン)の改善を重視しています。プロジェクト管理手法の標準化や生成AI活用による業務効率化を通じて、人的サービス事業の利益率を引き上げます。 - AIエージェント事業の立ち上げ
2025年3月に新設した子会社「BrainPad AAA」を中心に、生成AIやエージェント技術を活用した自動化ソリューションの早期収益化を目指しています。また、「Rtoaster GenAI」は既に複数企業で導入が進み、検索やレコメンド分野で新たな需要を獲得中です。 - M&Aによる非連続成長
2025年8月には「株式会社アクティブコア」を子会社化し、プロダクト事業の拡大を加速させています。今後もデータプラットフォーム・AI関連企業とのM&Aを通じて、売上140億円超を目指す計画です。 - 人的資本の強化と組織文化の刷新
人材戦略「Synapse Initiative」を軸に、社員のエンゲージメントと育成に注力。経営陣との対話や社内公募制度を活用し、データ人材の自律的成長を促しています。これにより離職率の低下と採用競争力の向上を狙います。
市場環境としても、AI・DX分野は中長期的に成長が見込まれます。国内企業のデータ内製化ニーズの高まり、生成AIによる業務変革需要、政府によるDX推進政策などが追い風となっています。一方で、人材確保や競合環境の激化といったリスクは引き続き注視が必要です。
総合的に見ると、ブレインパッドは「安定した財務基盤×高成長領域での展開」という構図を持ち、長期投資に向く企業です。特に、今後の成長エンジンとして期待される生成AI関連製品とM&A戦略が軌道に乗れば、利益と配当の両面で持続的な向上が見込めます。
投資家視点では、短期的な値動きよりも中期的な企業価値向上に注目すべき局面です。2026年度以降にはさらなる増配の可能性もあり、長期配当重視型ポートフォリオにおいて魅力的な選択肢といえるでしょう。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | ブレインパッド(2025年6月期) | 業種平均(情報・通信業) | 差異(ブレインパッド-業種平均) |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 17.9% | 10.68% | +7.22pt |
| 総資産経常利益率 | 21.6%(※1) | 5.45% | +16.15pt |
| 売上高営業利益率 | 13.4%(※2) | 11.36% | +2.04pt |
| 自己資本比率 | 78.2% | 32.89% | +45.31pt |
| 配当性向 | 16.5% | 37.14% | -20.64pt |
| 純資産配当率 | 2.95%(※3) | 3.45% | -0.50pt |
※1 経常利益1,510,719千円 ÷ 総資産7,487,931千円 ×100
※2 営業利益1,575,749千円 ÷ 売上高11,772,254千円 ×100
※3 1株配当8円 ÷ 1株純資産280.32円 ×100(単体ベース)
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)― 「資本効率の高さが際立つ優等生」
ブレインパッドのROEは 17.9% と、業種平均10.68%を大きく上回っています(+7.22ポイント)。ROEとは自己資本に対してどれだけの利益を上げられたかを示す指標であり、企業の収益性・経営効率を測る最重要指標のひとつです。
情報・通信業界では10%を超えれば優良水準とされますが、ブレインパッドはそれをはるかに超える数値を維持しており、「高利益率体質が定着した企業」と評価できます。
この背景には、2023年以降に実施された中期経営計画による構造改革が挙げられます。ブレインパッドはこれまでの「事業拡大重視」から「利益重視経営」へと舵を切り、EBITDAマージンの改善を重点方針に掲げました。その結果、プロフェッショナルサービス事業におけるプロジェクト収支の見直しや生成AI活用による生産性向上が功を奏し、収益率が急上昇しました。
ROEの高さは、単なる営業利益率の高さだけでなく、自己資本を過度に積み上げず、効率的に活用している財務構造にも起因しています。自己資本比率78.2%という盤石な安全性を保ちながらも、資本を眠らせることなく利益創出に結びつけている点は、経営の成熟度を物語っています。
長期配当狙いの投資家にとっては、安定かつ高効率な利益循環を維持できる企業として非常に魅力的です。
② 総資産経常利益率 ― 「資産効率が異例の高さ」
ブレインパッドの総資産経常利益率は 約21.6% と、業種平均5.45%をはるかに上回っています(+16.15ポイント)。この数値は、企業が保有する総資産をどれだけ効率的に活用して経常利益を稼いでいるかを表します。一般的に10%を超えれば極めて優良ですが、同社はその2倍以上の水準に達しています。
同社の特徴は「無借金経営」に近い高い自己資本比率と、軽資産モデルによる高回転構造にあります。AIコンサルティングやSaaSビジネスといった設備投資をほとんど必要としない事業モデルを採用しているため、固定資産への投資負担が少なく、総資産に占める収益性の比率が高くなっています。
さらに、プロダクト事業で展開する「Rtoaster」や「Ligla」などの自社開発ソフトウェアは、開発完了後の追加コストが少なく、スケーラブルな収益モデルとして機能しています。クラウド型SaaSの利益構造が安定しているため、景気変動にも比較的強い点も評価ポイントです。
資産効率の高さは、企業が「小さな資産で大きく稼ぐ」ことを意味します。投資家視点では、リターンを上げるための原資が効率的に循環している企業であることを示しており、長期的な資本リターンの高さが期待されます。
③ 売上高営業利益率 ― 「サービス産業でありながら2桁を維持」
営業利益率は 13.4% と、業種平均11.36%を上回る水準(+2.04ポイント)です。情報・通信業の多くは人件費や開発コストの比率が高く、10%を超える企業は限られます。その中でブレインパッドが安定的に2桁台を維持できているのは、高付加価値なデータ分析支援とソフトウェア販売のストック収益が両輪で成長しているためです。
プロフェッショナルサービス事業では、単価の高い生成AIコンサルティング案件が増加。プロダクト事業では、自社開発SaaSの契約継続率が高く、解約率の低下が利益率の改善に寄与しました。また、利益率の低かった旧製品を終了し、リソースを利益貢献度の高いプロダクトへ再配分したことも奏功しています。
このように、労働集約型の課題を脱却し、知的資産集約型企業へと進化している点が特徴です。長期的には生成AIやAIエージェント事業の拡大により、営業利益率15%超も視野に入ると考えられます。
④ 自己資本比率 ― 「極めて健全な財務体質」
自己資本比率は 78.2% と、業種平均32.89%の倍以上(+45.31ポイント)に達しています。
自己資本比率は財務の安全性を示す指標であり、一般的に40%を超えれば健全とされますが、ブレインパッドはその約2倍に位置します。これは、同社が外部借入に依存せず、自社の資金で成長を賄っていることを意味します。
この堅牢な財務基盤は、景気変動や金利上昇の影響を受けにくく、配当や投資においても長期的な安定を保証する強力な後ろ盾となります。特に、M&Aや新規事業投資を積極的に進めながらも高比率を維持している点は、キャッシュフロー管理の巧みさを示しています。
投資家にとっては「倒産リスクが極めて低い企業」であり、長期配当銘柄としての信頼性を高める要素となります。
⑤ 配当性向 ― 「成長余力を残した堅実な配当政策」
ブレインパッドの配当性向は 16.5% と、業種平均37.14%を大きく下回ります(-20.64ポイント)。
一見すると「配当還元が少ない」とも取れますが、これは同社が成長投資を優先するフェーズにあることを反映しています。
同社は中期経営計画で、生成AI搭載製品「Rtoaster GenAI」やAIエージェント事業への大型投資を打ち出しており、M&Aにも積極的です。これらの投資によって将来的な収益基盤を拡大し、持続的な配当成長を可能にする土台作りを進めています。
また、過去3年間で配当を据え置き(8円→8円→8円)としつつも、純利益の増加により配当性向は低下しており、これは「利益成長に対して配当が追いついていない」=増配余地が大きいことを意味します。
今後の利益拡大に応じて、安定配当から連続増配へ移行する可能性が高く、長期投資家にとって魅力的な上昇余地が残されています。
⑥ 純資産配当率 ― 「低水準だが上昇余地あり」
純資産配当率は 2.95% と、業種平均3.45%をやや下回っています(-0.50ポイント)。
この指標は株主資本に対してどれだけの配当を出しているかを示し、ROEと並んで「株主リターンの実効性」を測るものです。
現時点では控えめな数値ですが、これは高自己資本比率ゆえに分母が大きいことも影響しています。つまり、「安全性を維持しつつ株主還元を拡充できる余地が十分にある」という解釈ができます。
企業としては、安定的なキャッシュフローと内部留保を活かし、今後の業績次第でさらなる還元策(増配・自己株式取得)を打ち出す可能性があります。特に生成AI関連事業の収益化が進めば、純資産配当率3.5〜4%台への引き上げも十分視野に入ります。
配当方針と今後の展望
配当の現状と方針
ブレインパッドの有価証券報告書によると、2025年6月期の1株当たり配当金は8円で、配当性向は16.5%でした。これは前年度(2024年6月期)と同額で、過去3期連続の据え置きとなっています。
同社の配当関連指標を整理すると以下の通りです。
| 項目 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金 | 8円 | 8円 | 8円 |
| 1株当たり純利益 | 27.47円 | 44.12円 | 48.35円 |
| 配当性向 | 29.1% | 18.1% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 77.0% | 78.3% | 78.2% |
| 純資産配当率 | 約2.9% | 約2.9% | 約3.0% |
配当額が据え置かれているにもかかわらず、配当性向が年々低下しているのは、純利益が順調に増加しているためです。つまり、同社は利益の成長分を再投資や内部留保に充てていることを意味します。
ブレインパッドの基本方針としては、有価証券報告書内で次のように明記されています。
「当社は、持続的な企業価値の向上を目的に、成長投資と株主還元のバランスを重視する。業績の成長に応じた配当を実施しつつ、今後の成長のための投資資金を確保することを基本方針とする。」
この方針からも分かるように、現時点では“成長重視型の安定配当政策”を採用しています。無理な増配を行うよりも、AI・データ分析という高成長市場において積極的に投資を行うことで、将来的な利益拡大と還元余力の増大を狙う姿勢が明確です。
財務体質と配当余力
ブレインパッドの2025年6月期における自己資本比率は78.2%と非常に高く、業界平均(32.89%)を大きく上回っています。借入依存度が低く、実質的に無借金経営に近い堅牢な財務基盤を維持しています。
また、営業キャッシュフローは13億円超と安定しており、現金・現金同等物の期末残高も約33億円と潤沢です。
つまり、「配当を継続できる余力」は十分にあり、業績が悪化しない限り減配のリスクはほぼ皆無といえます。
一方で、配当性向が16%台という水準は、再投資を優先する成長企業としてのスタンスを示しています。ブレインパッドが注力するAI・データ分析領域は技術進化のスピードが速く、継続的な研究開発やM&Aが成長の鍵を握ります。そのため、当面は利益の大部分を成長投資へ回す戦略が想定されます。
特筆すべきは、同社が中期経営計画(2024〜2026年度)において「構造改革期」と位置づけている点です。この期間は利益率向上と事業ポートフォリオの再編に重点を置いており、特に生成AI分野への投資が増加しています。
よって、配当よりも利益再投資による企業価値向上を優先するフェーズにあるといえます。
配当政策の背景 ― 成長戦略と投資優先
ブレインパッドが成長投資を優先している理由は明確です。
それは、生成AIやAIエージェントなどの新領域で競争優位を確立するためです。
2024年12月には、自然言語で検索できるAI搭載レコメンドエンジン「Rtoaster GenAI」を発表。2025年3月にはAIエージェント事業を担う子会社「BrainPad AAA」を設立しました。さらに、2025年8月には「株式会社アクティブコア」を買収し、マーケティングAIプラットフォームのラインナップを強化しています。
これらの事業はまだ初期投資段階にあり、短期的には利益圧迫要因となるものの、中長期的には高収益の柱となる可能性が高いです。AI業界では先行投資がリターンを生むまでに時間がかかるため、現時点での増配よりも事業基盤強化を優先する経営判断は合理的といえます。
また、同社は「EBITDAマージン(営業利益+減価償却費)」の向上を中期目標に掲げています。これは将来的なフリーキャッシュフロー拡大を見据えたものであり、「将来の配当原資を着実に増やすための仕組みづくり」と位置づけられます。
今後の配当方針の展望
現状の8円配当を維持しつつ、2026年度以降には段階的な増配フェーズに移行する可能性が高いと考えられます。その根拠を以下に整理します。
- 利益成長の持続性
2024〜2025年にかけて経常利益・純利益ともに前年比2桁増を達成。ROEは17.9%と業界トップクラス。中期経営計画最終年度(2026年6月期)には売上140億円超を目指しており、利益成長が続く限り配当余力はさらに拡大します。 - キャッシュフローの強さ
営業キャッシュフローは継続的にプラスで、設備投資が少ないビジネスモデルのためフリーキャッシュフローが潤沢。M&Aを実施しても手元資金が30億円超あり、財務余力が十分に残っています。 - 株主還元への意識の高まり
同社は近年、人的資本経営やESG開示を積極化しており、サステナビリティ経営と株主還元の両立を掲げています。取締役会の監督体制にもサステナビリティ専門委員会を設置しており、今後は「中長期的な株主還元率向上」が議論の中心になる可能性が高いです。 - 業界平均との乖離
情報・通信業界の平均配当性向(約37%)に対して、ブレインパッドは16.5%と依然低水準。この差を徐々に埋める方向で、今後数年のうちに20〜25%程度への引き上げが見込まれます。
仮に純利益が今後年率10%で成長し、配当性向が25%まで上昇した場合、2027年時点での予想配当金は12〜13円程度に達する可能性があります。これは現在の水準から約50%の増配に相当します。
同社が増配余力を「温存している」という点で、長期保有のリターンはむしろ拡大する構造といえます。
長期投資家の視点からみた評価
ブレインパッドの配当政策は、一見すると保守的ですが、長期投資家にとっては極めて合理的な戦略です。
以下の3つの観点から、その魅力を整理します。
- 「守りの強さ」
高い自己資本比率と無借金経営により、景気変動時にも減配リスクが極めて低い。安定配当を維持できる企業体質です。 - 「攻めのポテンシャル」
生成AI・AIエージェント事業など高収益ポテンシャルの新領域に積極投資。利益成長と配当増加の両立が見込めます。 - 「長期的な増配シナリオ」
ROE17.9%という高い収益性が持続する限り、利益の一部を株主還元へ回す余地が大きい。今後の中期経営計画終了後(2027年度以降)には、増配トレンドへの転換が期待されます。
現時点では高配当銘柄ではなく、将来の増配期待銘柄として位置づけるのが妥当でしょう。
長期配当によるFIREを目指す投資家にとっては、「配当の伸びしろ」に着目すべき企業です。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
ブレインパッドは、長期配当を狙う投資家にとって「安定した財務基盤と将来の増配期待を両立した優良銘柄」といえます。評価基準である「配当利回り」「配当の持続性」「連続増配」の3軸で他の日本株と比較すると、総合的には★4つの高評価です。
まず配当利回りについては、2025年6月期時点の予想配当8円、株価(約1,500円前後)ベースで0.5〜0.6%前後と、東証プライム上場企業の平均(約2.1〜2.3%)に比べると低水準です。現時点では「高配当株」とは言えません。しかし、同社の低配当性向(16.5%)と高ROE(17.9%)を考慮すると、今後の増配余地が非常に大きい点が重要です。利益成長と内部留保の蓄積をもとに、数年以内に配当利回りが上昇する可能性があります。つまり、「いまは利回りが低い成長前夜」の段階にあるといえます。
次に配当の持続性ですが、これは極めて高く評価できます。自己資本比率78.2%、実質無借金経営、営業キャッシュフロー13億円超という堅牢な財務体質を持ち、景気変動や金利上昇にも強い構造です。特に、情報・通信業の中ではトップクラスの安全性を誇り、減配リスクがほぼ皆無の企業といってよいでしょう。利益変動の少ないSaaS型収益モデルとコンサルティング契約により、ストック型の収益基盤を確立している点も評価を押し上げます。企業が“成長投資フェーズ”であるにもかかわらず、3期連続で安定配当(8円)を維持しているのは、まさに「守りの強さ」を裏付けています。
最後に連続増配実績ですが、直近3年間は配当金を据え置いており、「増配株」とはまだ言えません。ただし、2022〜2025年の純利益は約2倍に増加しており、現行の配当性向を維持したままでも近い将来に増配へ移行する蓋然性が高いと考えられます。業界平均配当性向(37%)とのギャップも大きく、将来的にはその差を埋める形で段階的に配当を引き上げていく可能性が高いでしょう。
総合すると、ブレインパッドは「いま高配当ではないが、今後10年の配当成長を狙える堅実な成長株」です。持続性は極めて高く、配当方針も慎重かつ誠実。FIREを目指す長期投資家にとって、短期の利回りではなく“将来の複利的な配当成長”を狙う銘柄として十分に推奨できます。
したがって、現時点では★4.0(長期的には★5.0に到達する潜在力あり)という評価が妥当です。