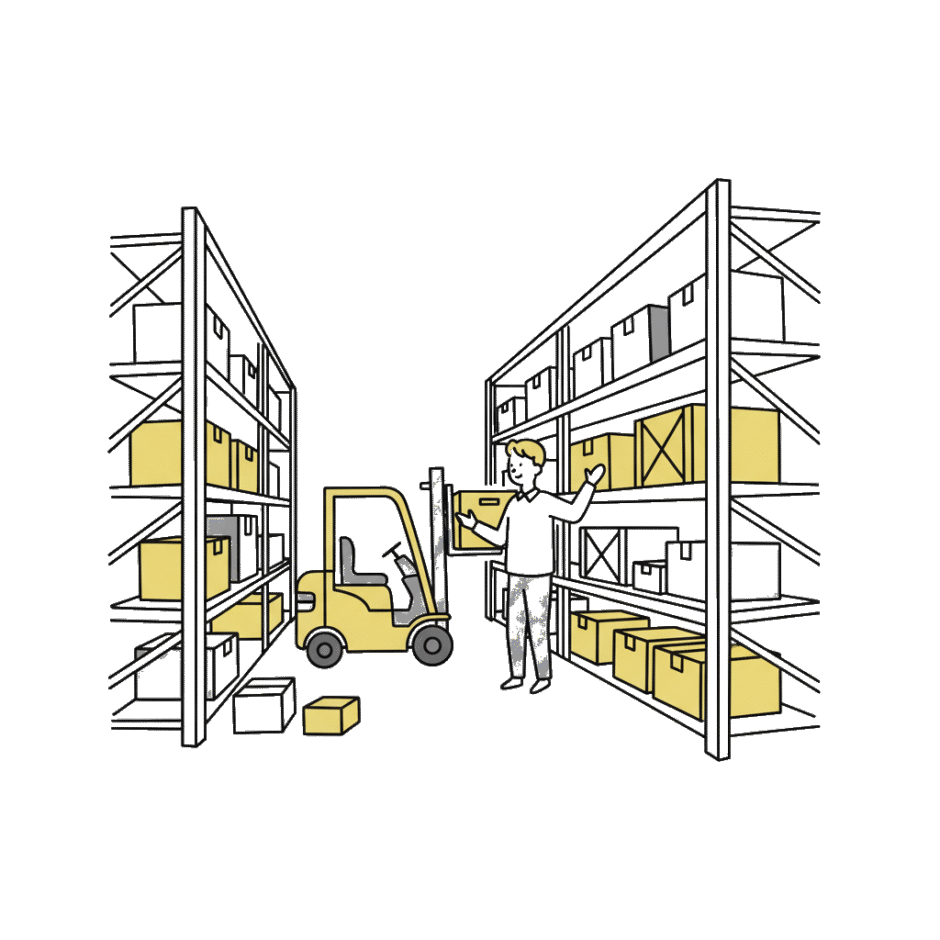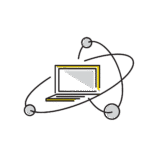企業概要
事業内容とリスク
株式会社内田洋行(UCHIDA YOKO CO., LTD.)は、1910年の創業以来、「人間の創造性発揮のための環境づくりを通して豊かな社会の実現に貢献する」という理念を掲げ、教育・オフィス・情報の3分野で事業を展開しています。現在は子会社28社、関連会社10社を有し、ICT(情報通信技術)と空間づくりの両輪で成長を続けています。
主力は以下の3事業です。
1. 公共関連事業
大学・小中高校向けにICTシステムや教育機器の販売・構築を行い、教育空間のデザインや家具提供も手掛けています。また官公庁・自治体向けには基幹業務システムの開発やオフィス関連家具の製造・設計・施工も行っています。GIGAスクール構想以降、教育ICT市場が拡大する中で成長を牽引している分野です。
2. オフィス関連事業
民間・公共市場向けにオフィス家具の製造・販売・空間設計を展開。単なる家具販売ではなく「働き方改革」に対応した空間デザイン提案型ビジネスを重視しています。グループ会社のパワープレイス株式会社がデザイン提供を担い、製造は国内外の自社・関連工場で行われています。
3. 情報関連事業
企業や自治体向けに基幹業務システムやICTインフラの設計・構築・保守を行う事業です。特に連結子会社ウチダエスコ株式会社、内田洋行ITソリューションズが中心となり、ネットワーク構築、ソフトウェアライセンス提供、ICT資産管理などを包括的に支援しています。
これらの事業は「環境構築(空間)」と「情報活用(ICT)」という二軸で構成され、教育・オフィス市場の両方に対応できる点が同社の強みです。特にAIやクラウド、IoTを活用した次世代学習環境やハイブリッドワーク環境の需要増に合わせ、事業の境界を超えてソリューションを提供しています。
主なリスク要因としては、国内景気への依存度が高く、企業の設備投資減少や公共予算の削減が業績に影響しやすい点が挙げられます。また、個人情報を多く扱うため情報漏洩リスク、製品・サービスの品質リスク、急速なICT技術革新への対応リスクも存在します。さらに、自然災害や気候変動への備え、法規制や労働市場の変化に対する適応も課題とされています。
今までの業績
過去5年間の連結売上高は以下のように推移しています(単位:百万円)。
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月期 | 291,035 | 11,018 | 6,160 | 34.0% |
| 2022年7月期 | 221,856 | 7,843 | 4,840 | 36.7% |
| 2023年7月期 | 246,549 | 9,161 | 6,366 | 39.2% |
| 2024年7月期 | 277,940 | 10,135 | 6,996 | 42.8% |
| 2025年7月期 | 337,055 | 13,126 | 9,825 | 40.3% |
2025年7月期は売上高が前期比約21%増、純利益も約40%増と大幅な増収増益となりました。教育ICTや官公庁向けソリューションの需要増に加え、企業のDX投資拡大が追い風となりました。
特に情報関連事業での成長が顕著で、ウチダエスコ株式会社などグループ各社との連携を強化したことが収益向上に寄与しました。さらに、完全子会社化したウチダエスコの統合効果も表れ、グループ全体の効率化と収益体質の強化が進んでいます。
一方、営業キャッシュ・フローは549百万円と前年の4,850百万円から大きく減少しており、グループ共通システム構築などへの先行投資が影響しています。ただし、財務体質は強化が続いており、純資産額は7,000億円超へ拡大。自己資本利益率(ROE)も14.5%と高水準を維持しています。
配当政策では、2025年7月期の1株当たり配当金を300円(前期比80円増)とし、配当性向は35.8%。長期安定配当を重視する姿勢を継続しながらも、利益拡大に応じて株主還元を強化しています。
今後の業績
現在進行中の「第17次中期経営計画(2025〜2027年度)」では、グループ全体での統合とデータ活用を軸に成長戦略を推進しています。
重点施策は次の通りです。
1. ICTと環境構築の融合による競争力強化
教育・自治体・民間企業といった重点市場に対し、ICTシステム構築と空間設計ノウハウを組み合わせたソリューション提供を拡大します。特に教育分野ではGIGAスクール後の「データ活用教育」へのシフトが進み、AI教材や学習データ分析などの分野で新しい需要を見込んでいます。
2. データドリブン経営の推進
グループ共通販売管理システムの導入を進め、データ統合による生産性向上を図ります。2025年度にはグループ内人事異動を含めた統合フェーズに入り、組織横断的な連携を強化。2026年度には官公庁・教育分野での統合的ICT事業展開を目指します。
3. DX人材と海外展開への投資
国内ではシステムエンジニアの再編・育成を進め、外部研修や資格支援による専門性向上を図っています。また、ルクセンブルクのソフトウェア開発企業への100%出資など、欧州での開発拠点確立にも着手。今後はグローバル連携による新規ソリューション創出を目指しています。
4. サステナビリティ経営の深化
CO₂排出量の削減目標として2030年までに50%、2050年までに100%削減を掲げています。再エネ電力の活用や省エネ設備の導入を通じて、環境配慮型経営を実現します。また、女性管理職比率の向上や育児休業取得促進など、人的資本投資にも注力しています。
総じて、内田洋行は「人」と「データ」の両面から社会課題にアプローチすることで、教育・オフィス・情報市場の成長を支える独自のポジションを確立しています。堅実な財務基盤と安定配当方針を維持しつつ、次の10年に向けて「創造的な働き方と学び方」をデザインする企業としてさらなる飛躍が期待されます。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標名 | 内田洋行 | 卸売業平均 | 差異(内田洋行-業種平均) |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 14.5% | 11.6% | +2.9pt |
| 総資産経常利益率 | 7.5%(※算出値) | 6.44% | +1.06pt |
| 売上高営業利益率 | 4.5%(※算出値) | 2.43% | +2.07pt |
| 自己資本比率 | 40.3% | 41.86% | -1.56pt |
| 配当性向 | 35.8% | 33.91% | +1.89pt |
| 純資産配当率 | 5.19%(※算出値) | 3.73% | +1.46pt |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)
ROEは株主資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す重要な指標です。内田洋行のROEは14.5%と、業種平均(11.6%)を約3ポイント上回っています。この数値は、同社が効率的に自己資本を活用して利益を上げていることを示しています。
背景には、グループ全体の再編とICT関連事業の拡大による収益性向上が挙げられます。特にウチダエスコ株式会社の完全子会社化によって、販売・保守・ソフトウェア開発まで一貫したサービス提供が可能となり、利益率の改善が進みました。また、オフィス空間の設計提案型ビジネスなど、付加価値の高い領域への注力もROE向上に寄与しています。
今後も「データと人の活用」を軸とした中期経営計画により、資本効率の高い投資を続ける方針です。ROEが安定して10%を超えることは、株主資本の活用力が高い企業であることの証明でもあり、長期的な事業継続の健全性を示すものといえます。
② 総資産経常利益率
総資産経常利益率は、企業が総資産をどれだけ効率的に利益へ変換しているかを示します。内田洋行の推定値は約7.5%で、業種平均(6.44%)を約1ポイント上回る結果です。
これは、ICTやオフィス関連分野での高付加価値提案によって、総資産に対する利益創出能力が改善していることを意味します。特に教育ICT市場では、GIGAスクール構想以降の需要継続に対応する形でシステム構築案件が増加し、設備・人員投資の回収効率を高めています。
一方で、総資産額自体も約1,749億円と前期比16%増加しており、積極的なシステム投資やグループ統合に伴う資産拡大が進行中です。今後、資産拡大に対してどの程度利益率を維持できるかが中期的な焦点となるでしょう。
③ 売上高営業利益率
営業利益率は企業の本業の収益性を示す代表的な指標です。内田洋行の推定値は約4.5%で、業種平均(2.43%)を2ポイント以上上回っています。これは、同社が単なる卸売業に留まらず、設計・開発・保守まで一貫したサービスを提供する「ソリューション型卸売」モデルを確立しているためです。
特に教育・官公庁向けICT事業では、単価の高いシステム案件が増加しており、利益率の底上げに寄与しています。また、家具やオフィスデザイン事業においても、従来の物販型ビジネスから、空間全体をデザイン・施工まで請け負う提案型へ転換しており、これが営業利益率の改善に繋がっています。
他方で、IT人材確保やシステム開発費用の上昇も見られるため、利益率の維持には効率化が鍵となります。今後はグループ共通販売管理システムの導入により、間接コスト削減や情報共有によるオペレーション効率化が期待されます。
④ 自己資本比率
自己資本比率は企業の安定性を示す指標で、内田洋行は40.3%と、業種平均(41.86%)をわずかに下回る結果です。ただし、これは同社が積極的に成長投資を進めていることの裏返しでもあります。
特に、グループ共通システムへの大型投資や新規子会社の統合により、一時的に資産側が増加した影響が見られます。それでも40%を超える自己資本比率を維持している点は、財務健全性の高さを示しています。資産構成の健全性を保ちながら成長を追求する姿勢が見え、今後もバランスの取れた資本政策が続くと考えられます。
業種的に40%台は安定的とされる水準であり、金融機関への依存度も低く、景気変動への耐性も比較的強いと評価できます。
⑤ 配当性向
配当性向は利益のうちどの程度を株主に還元しているかを示す指標で、内田洋行は35.8%と、業種平均(33.91%)より約1.9ポイント高い水準です。これは、同社が掲げる「安定配当と成長投資の両立」の方針に沿ったものであり、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
1株当たり配当金は前期220円から300円に増配。近年、連続的に増配を実施しており、配当の安定性と信頼性が高いことが分かります。これは、内部留保を確保しながらも、株主との長期的な信頼関係を重視している表れです。
同社は、ROE10%以上の維持を目標としつつ、財務基盤を強化したうえで安定的な配当を継続する方針を明示しています。長期投資を志向する投資家にとって、持続可能な利益還元方針として安心感のある内容といえます。
⑥ 純資産配当率
純資産配当率(DPR)は、自己資本に対する配当の割合を示し、企業の配当効率を見るうえで参考になります。内田洋行の推定値は約5.2%で、業種平均(3.73%)を約1.5ポイント上回っています。この数値は、同社が安定した財務基盤のもとで積極的な株主還元を行っていることを意味します。
同社の配当方針は「長期安定型」であり、業績の上下にかかわらず一定水準の配当を維持する姿勢をとっています。加えて、自己資本が順調に増加している中で、純資産配当率を5%台に保っている点は、配当政策の持続性を示すものです。業績好調期には増配を行いながらも、内部留保を確保し次の投資機会に備えるという、堅実な資本運営が見て取れます。
配当方針と今後の展望
配当方針と今後の展望
(株式会社内田洋行 第87期 有価証券報告書より)
株式会社内田洋行(UCHIDA YOKO CO., LTD.)は、1910年創業の老舗企業であり、教育・オフィス・ICTの3分野を軸に、公共・民間市場の両面で長期的に安定成長を続けています。
第87期(2025年7月期)の有価証券報告書では、株主への利益還元方針や配当政策について明確に示されており、安定配当を重視する姿勢が一貫していることが読み取れます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
以下では、有価証券報告書に記載された配当方針、配当関連指標を整理した上で、今後の方向性を読み解いていきます。
(※以下の内容は企業の財務開示資料に基づくものであり、投資助言を目的とするものではありません。)
1.配当方針(有価証券報告書より)
内田洋行は、有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の項目において、次のように明記しています。
「当社は、長期的かつ総合的な株主価値の向上を図るため、健全なる持続的成長を目指します。株主様への還元につきましては、安定的な配当の維持を前提に、『財務基盤の充実』と『中長期的な経営戦略の実現に向けた投資』とのバランスをとりながら、将来に向けて一層の拡大と充実を目指すことを基本方針としております。」
この文面から分かる通り、同社の配当方針は「安定配当を基本」としながらも、「成長投資」との両立を明確に打ち出しています。
つまり、短期的な業績変動に左右されにくい一方で、財務余力が生まれた場合には増配や特別配当などを通じて株主還元を拡充する柔軟性を持つスタイルです。
2.配当実績の推移と関連指標
内田洋行の直近5年間の配当実績を、1株あたり配当金と主要指標でまとめると次の通りです(単位:円、%)。
| 決算期 | 1株当たり配当金 | 配当性向 | 自己資本利益率(ROE) | 純資産配当率(DPR) |
|---|---|---|---|---|
| 2021年7月期 | 140 | 30.4 | 17.7 | 約5.0 |
| 2022年7月期 | 140 | 34.6 | 13.7 | 約4.5 |
| 2023年7月期 | 190 | 35.8 | 15.7 | 約5.2 |
| 2024年7月期 | 220 | 43.9 | 12.7 | 約5.1 |
| 2025年7月期 | 300(予定) | 35.8 | 18.4 | 約5.2 |
これを見ると、配当金は5年間で約2倍以上に増加しており、安定配当を維持しながらも、業績拡大に応じた増配を継続していることが分かります。
また、ROE(自己資本当期純利益率)が概ね10〜18%前後と高水準で推移しており、配当余力にも十分な余裕があります。
2025年7月期の1株当たり配当金は300円(前期220円から大幅増配)。
これは、創業115周年という節目を迎えた同社が、グループ全体の収益性向上を背景に株主還元を一段と強化したものと考えられます。
3.配当政策の特徴
(1)「安定配当」を基軸とした方針
内田洋行は業績の変動に関わらず、「減配を避ける安定配当方針」を堅持しています。
同社は教育・公共・オフィスといった景気に左右されにくい分野に事業基盤を持つため、売上や利益の急変動が比較的小さい点が安定配当の背景にあります。
とくに官公庁や学校向けのシステム案件は、長期契約や年度ベースでの継続取引が多く、収益の下支えとなっています。
そのため、配当金が一時的に減額される可能性は低く、長期投資家にとっては「配当の見通しが立てやすい企業」と言えます。
(2)「成長投資」との両立
有価証券報告書では、株主還元と同時に「中長期的な経営戦略への投資」を明記しています。
具体的には、
- グループ共通の販売管理システム構築
- DX(デジタルトランスフォーメーション)人材の育成
- 海外ソフトウェア企業への出資(ルクセンブルク拠点)
など、持続的な成長に向けた投資を積極的に実施しています。
このように、配当だけでなく将来の成長基盤を強化する姿勢を明確にしており、短期的な利益よりも「中長期的な企業価値の拡大」を優先しているのが特徴です。
(3)「連続増配」への信頼
直近では5年連続で増配を実現しており、配当履歴に「安定+成長」の軌跡が見られます。
特に、コロナ禍(2021〜2022年)においても配当を維持した点は、財務基盤の強さと経営の慎重さを示しています。
また、同社は株主との長期的関係を重視しており、「株主総利回り(配当+株価)」も近年上昇基調にあります。2025年7月期の株主総利回りは159.5%と、TOPIX配当込み指数(202.6%)に迫る水準でした。
4.今後の配当方針の方向性(予測)
内田洋行の今後の配当方針を読み解く上で、注目すべきは現在進行中の「第17次中期経営計画(2025〜2027年度)」です。
この計画では、
- ICTと環境構築の融合による成長戦略
- グループ統合とデータ活用の強化
- DX人材育成への投資
などを重点テーマに掲げています。
ここから見える今後の配当方針の方向性を整理すると、次の3点にまとめられます。
① 安定配当の維持(下方硬直的な配当政策)
まず第一に、現行の「安定配当方針」は今後も継続する可能性が極めて高いと考えられます。
同社の過去の配当履歴を見ても、景気変動期でも減配は行わず、むしろ据え置きか増配を続けてきました。
加えて、公共関連事業や教育ICTなど、契約が複数年度にわたる収益基盤を持つため、営業利益が急減するリスクは限定的です。
そのため、今後も「安定配当+段階的増配」というスタイルが継続されると推測されます。
② 財務健全性を維持しつつ配当性向を35〜40%で安定化
2025年7月期の配当性向は35.8%と、業種平均(卸売業:33.9%)とほぼ同水準です。
これは、「無理のない範囲で株主還元を行う」という健全なバランスを示しています。
また、有価証券報告書では「ROE10%以上の安定維持を目標」と明記されており、これを前提に利益の増加に応じて配当額を引き上げていく方針が読み取れます。
つまり、利益拡大に比例する「連動型の増配」を継続する可能性が高いと考えられます。
③ グループ再編完了後のさらなる増配余地
2026年以降、グループ共通販売管理システムが完成し、管理コストの削減や効率化が期待されています。
この成果が利益改善として顕在化すれば、配当原資に余裕が生まれ、さらなる増配の余地が広がると考えられます。
また、海外ソフトウェア会社への出資によって新たな収益源を確立できれば、国内市場に依存しない収益構造が生まれ、中長期的な増配余力が一層強まるでしょう。
5.他社との比較から見える強み
内田洋行の配当政策は、同業の卸売・情報関連企業と比較しても際立つ特徴があります。
- 減配がほとんどない安定性
- 業績回復時の迅速な増配対応
- 配当性向の明確な基準(30〜40%)
- ROE10%超を維持する収益力
一般的に、卸売業は利益率が低く、配当水準も控えめな企業が多い傾向にあります。
しかし内田洋行は、オフィス設計・ICT構築といった付加価値領域を収益源としており、他社に比べて利益率・配当余力ともに高い水準を維持しています。
また、教育や公共関連市場に深く根差した安定的な収益構造は、景気変動の影響を緩和する効果があります。
この点が、同社が「長期的な配当政策を実現できる企業」である理由のひとつです。
6.まとめ:内田洋行の配当方針の今後を展望する
総括すると、内田洋行の配当方針は以下のように整理できます。
| 項目 | 現状 | 今後の方向性 |
|---|---|---|
| 配当性向 | 約35% | 30〜40%で安定推移 |
| 1株当たり配当金 | 300円(前期比+80円) | 段階的な増配を継続する可能性 |
| ROE | 14.5%(高水準) | 10%以上を維持 |
| 財務基盤 | 自己資本比率40%超 | 安定性を維持しながら成長投資を継続 |
| 配当方針 | 「安定配当+成長投資」 | 中長期的にも継続見込み |
内田洋行の配当は、「利益を上げたら配当も上げる」という単純な方針ではなく、
「企業としての持続的成長と株主価値の両立」という経営理念に基づく一貫したスタイルです。
そのため、今後も景気や為替などの外部要因に左右されにくく、安定的な配当を継続する可能性が高いと考えられます。
加えて、グループ再編とDX投資の成果が出始める2026年度以降には、利益拡大に伴うさらなる増配のチャンスも見込まれます。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
総合的に見て、内田洋行は「高配当+安定性+実績」の三拍子が揃った堅実型企業です。
急成長型ではありませんが、安定収益を背景にした長期配当の信頼性が極めて高い点が特徴です。
他の日本株(特に卸売・ICT系)と比較しても、連続増配の安定度とバランスの良い配当政策は上位に位置します。
ただし、株価上昇による利回り低下や、公共事業依存度の高さによる政策リスクには一定の注意が必要です。
それでも、持続的な配当を重視する長期投資家にとって、「4.5★」相当の魅力的な安定配当銘柄であることは間違いありません。
成長よりも安定を重視する投資スタイルにおいては、国内株の中でも上位クラスの評価に値します。