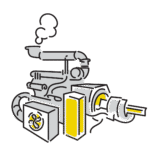企業概要
事業内容とリスク
株式会社ファーマフーズ(Pharma Foods International Co., Ltd.)は、京都市西京区に本社を置くヘルスケア企業です。同社は「医食の研究で貢献」というミッションを掲げ、食品・医薬・バイオ分野の研究開発を軸に、「BtoB事業」「BtoC事業」「バイオメディカル事業」の3本柱で事業を展開しています。
BtoB事業では、機能性素材・医薬品・健康食品の研究開発と製造を行い、食品・医薬品メーカーなどに販売しています。主力製品の一つ「ファーマギャバ」は、ストレス緩和や睡眠の質改善など6つの機能性表示に対応する素材として注目されています。また、骨の成長を促す「ボーンペップ」や発毛を促進する「HGP」なども有名で、国内外での自社ブランド製品展開やOEM供給を進めています。
BtoC事業では、サプリメントや医薬部外品、化粧品を通信販売で消費者に直接届けています。特に医薬部外品の「ニューモ育毛剤」は同社の代名詞ともいえるヒット商品で、2025年7月期の連結売上高のうち約24%を占める主力製品です。また、まつ毛美容液「WMOA」やダイエットサポート食品「シボラナイト2」など、幅広いラインナップを展開しています。
バイオメディカル事業は、難治性疾患を対象とする抗体医薬・ペプチド医薬の研究開発が中心です。独自技術「ALAgene technology(アラジンテクノロジー)」により、これまで治療が困難だった自己免疫疾患や繊維症への新薬開発を目指しています。非臨床試験までは自社で進め、臨床試験以降は製薬企業にライセンスアウトするモデルで、将来的なロイヤリティ収入が期待されています。
リスク要因としては、事業モデル上の不確実性や、特定製品への依存が挙げられます。研究開発成果が想定通りに得られない場合、投下資金の回収が難しくなる可能性があります。また、主力商品の「ニューモ育毛剤」に売上が集中しているため、供給トラブルや競合出現などが起きれば業績に大きく影響します。さらに、BtoC事業では広告・薬機法・特定商取引法など多数の法規制を受けるため、法令遵守体制の維持が欠かせません。
今までの業績
直近5年間の推移を見ると、売上高は2021年7月期の467億円から2025年7月期には652億円と成長を維持しています。一方で、経常利益は2024年7月期の52億円から2025年7月期には25億円と減少しました。純利益も前年の32億円から3億円へと落ち込み、利益率面では課題が見られます。
セグメント別に見ると、BtoC事業の減益が影響しています。通販事業の広告宣伝費の増加や顧客獲得コストの上昇が収益を圧迫しました。一方で、BtoB事業では堅調であり、ファーマギャバを中心に国内外での販売が好調でした。また、子会社の明治薬品株式会社による医薬品製造受託(CMO)事業も一定の収益を支えています。
財務面では、自己資本比率が44.7%まで改善し、財務基盤は安定しています。2025年7月期の1株当たり配当は25円(うち中間12.5円)で、配当性向は26.3%と安定的な水準を維持。過去5年間で連続増配しており、株主還元姿勢が強いことも個人投資家にとって魅力です。
ただし、営業キャッシュフローはマイナス(▲10億円)と、前期のプラス54億円からの反転となりました。投資・研究開発への資金投入が増加したことが主因です。同社は「300億円規模の挑戦的投資」を掲げており、その中には卵殻膜バイオものづくりプロジェクトや医薬品新工場建設、GABAの米国FDA認証取得などが含まれています。
株価面では、2021年の高値3820円から現在は1000円前後まで下落していますが、これは成長投資期の収益圧迫が主因であり、中長期的には再成長を見据えた過渡期といえます。
今後の業績
ファーマフーズは今後、「ヘルスケアのリーディングカンパニー」を掲げ、売上高1,000億円の達成を目標としています。その実現に向けた重点施策は次の3つです。
- BtoB事業の拡大
機能性素材「ファーマギャバ」の米国FDA GRAS認証取得を目指すほか、新たな健康素材の開発にも注力します。特に、未利用資源を活用したサステナブル素材や、海外市場(北米・中国・東南アジア)での販路拡大を進めることで、グローバル市場での成長を見込んでいます。 - BtoC事業の再成長
既存のヒット商品に続く新製品開発を強化します。AIを活用した広告クリエイティブや顧客管理システムの刷新により、コールセンターやECサイト運営の効率化を図り、顧客満足度の向上とLTV(顧客生涯価値)の最大化を狙います。 - バイオメディカル事業の進展
田辺三菱製薬との独占ライセンス契約に基づくマイルストン達成を果たしたほか、AI・バイオインフォマティクスを用いた次世代抗体の創出にも着手しています。中長期的には、ライセンス収入の積み上げによる安定収益化が期待されます。
経営面では、伊藤忠商事との資本業務提携(2024年10月)が大きな転機となりました。これにより、調達・流通・海外展開の面で新たなシナジーが見込まれ、BtoB・BtoC両事業の強化が進むとみられます。
同社は今後も「研究開発力」「ブランド力」「販売網」という3つの強みを活かし、成長投資と株主還元の両立を目指す方針です。配当は安定的に維持しつつ、キャッシュフロー改善後は増配や自社株買いも視野に入れるとしています。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標名 | ファーマフーズ(2025年7月期) | 食料品業種平均 | 差異(自社-業種平均) |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 18.13% | 6.87% | +11.26pt |
| 総資産経常利益率 | 19.86%(注1) | 5.40% | +14.46pt |
| 売上高営業利益率 | 11.06%(注2) | 6.48% | +4.58pt |
| 自己資本比率 | 44.7% | 51.54% | −6.84pt |
| 配当性向 | 26.3% | 62.51% | −36.21pt |
| 純資産配当率(DOE) | 4.77%(注3) | 4.08% | +0.69pt |
(注1)総資産経常利益率=経常利益7,213百万円 ÷ 総資産36,316百万円 ×100
(注2)売上高営業利益率=営業利益4,671百万円 ÷ 売上高42,234百万円 ×100
(注3)DOE=(配当25円 ÷ 期末1株当たり純資産562.05円)×100
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
ROEは企業が株主から預かった資本をどれだけ効率的に利益へと変換できたかを示す指標です。ファーマフーズのROEは18.13%と、食料品業界平均の6.87%を大きく上回っています。この水準は、成長投資を積極的に行いながらも一定の利益を確保している企業に見られる特徴です。
特に、BtoB事業での高付加価値素材(ファーマギャバ、HGPなど)の安定販売と、BtoC事業でのヒット商品「ニューモ育毛剤」の寄与が収益率を押し上げています。
ROEが高い背景には、自己資本比率が業界平均より低い(44.7%)ことも影響しており、ややリスクを取った経営スタイルで高い資本効率を実現しているといえます。
今後、ROEが20%を超える水準を安定的に維持できるかは、BtoC事業の利益率改善と研究開発投資のリターンに左右されるでしょう。現状のROE水準は業界内でも上位に位置するため、資本効率面では非常に良好と評価できます。
2. 総資産経常利益率
総資産経常利益率は、総資産をどの程度効率的に活用して利益を生み出しているかを表します。ファーマフーズの値は約19.9%と、業界平均の5.4%を大きく上回ります。
この高い数値は、固定資産や研究開発設備に投資しつつも、BtoBおよびBtoC事業から安定的にキャッシュを生み出していることを示しています。
同社のバイオメディカル事業はまだ黒字化していないものの、製薬会社へのライセンス収入などにより非連続的な収益が期待される点も、今後の資産効率をさらに高める要因となります。
他方で、2025年期の営業キャッシュフローがマイナスである点には注意が必要です。短期的には運転資金の増加や研究開発支出による影響が見られますが、長期的に見れば投資先行型の資産運用が奏功している状況といえます。
3. 売上高営業利益率
売上高営業利益率は、売上に対してどれだけ営業利益を上げているかを示す収益性の基本指標です。ファーマフーズは約11.1%と、業界平均6.48%を約4.6ポイント上回りました。
この高い利益率は、主にBtoC事業のブランド戦略と商品力によるものです。「ニューモ育毛剤」を中心に、顧客ロイヤリティが高い通信販売事業を展開しており、継続課金モデルが安定した利益を生んでいます。また、広告コストを最適化するためにAIを活用したマーケティングを導入しており、効率的な販促による利益率の向上が見られます。
一方で、明治薬品の一部事業で損失が発生しており、連結ベースでは営業利益率がやや圧縮されています。中期的には、医薬品製造受託(CMO)と新素材開発による相乗効果が利益率の押し上げ要因となるでしょう。
4. 自己資本比率
自己資本比率は、財務の安定性を示す代表的な指標で、ファーマフーズは44.7%と業界平均の51.54%を下回っています。
これは積極的な成長投資やM&Aにより総資産が拡大している一方で、自己資本の積み上げが追いついていない構造によるものです。
ただし、44.7%という水準自体は製造業として十分に健全であり、財務リスクが高いとは言えません。むしろ、研究開発・新工場建設・海外展開などの資金需要を賄うために、あえてバランスシートを成長寄りに傾けていると考えられます。
伊藤忠商事との資本業務提携(2024年10月)により、資本効率と信用力の両面で改善が期待されます。
5. 配当性向
配当性向は26.3%と業界平均62.51%を大きく下回っています。この数値は一見控えめですが、同社の立場を考慮すると「投資優先の中で安定配当を維持している」とも評価できます。
ファーマフーズは研究開発型企業として多くの新規プロジェクトを抱えており、内部留保を厚くする必要があります。加えて、創薬事業など長期回収型の投資を進めているため、配当よりも将来の成長を重視するフェーズにあると言えるでしょう。
それでも年間配当25円を維持している点は、安定的な株主還元意識の表れです。ROEとのバランスから見ても、無理のない水準です。
6. 純資産配当率(DOE)
DOEは4.77%と業界平均4.08%をわずかに上回っています。DOEは株主資本に対してどれだけの配当を支払っているかを示すもので、長期的な還元姿勢を測る指標として注目されています。
同社はROEが高く、利益成長に合わせて配当を維持しているため、DOEの上昇余地も十分にあります。今後、業績回復に伴い増配や自社株買いが行われれば、DOEはさらに上昇する可能性があります。
配当性向が低めでもDOEが平均以上である点は、「株主資本の効率的活用」が進んでいる証拠といえます。
配当方針と今後の展望
配当方針の基本理念
ファーマフーズの有価証券報告書(第28期・2025年7月期)によると、同社は次のような方針を掲げています。
「株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識し、業績の動向や今後の事業展開を総合的に勘案しながら、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としています。」
この文言からも分かるように、ファーマフーズは短期的な利益変動に左右されず、「安定配当」を重視する企業です。業績の波が大きい研究開発型企業において、このような方針は株主との信頼関係を築くうえで重要な姿勢といえます。
また、同社は研究・開発・生産・販売まで自社で一貫して行う事業構造を持ち、BtoB(企業間取引)とBtoC(消費者向け販売)の両輪で収益を支えています。したがって、一定のキャッシュフローを確保できる事業基盤が、安定的な配当実施を支える土台となっています。
配当実績の推移
以下は、過去5年間の配当金の推移と関連指標です。
| 期(決算年月) | 1株当たり配当(円) | うち中間配当(円) | 配当性向(%) | 1株当たり当期純利益(円) |
|---|---|---|---|---|
| 第24期(2021年7月) | 25.00 | 5.00 | 16.0 | 155.88 |
| 第25期(2022年7月) | 20.00 | 10.00 | 17.0 | 117.79 |
| 第26期(2023年7月) | 22.00 | 10.00 | 39.7 | 55.32 |
| 第27期(2024年7月) | 25.00 | 10.00 | 25.7 | 97.13 |
| 第28期(2025年7月) | 25.00 | 12.50 | 26.3 | 95.07 |
この表から読み取れるポイントは以下の通りです。
- 5年連続で配当を維持または増配している。
減配を一度も行っておらず、安定配当を実現しています。 - 中間配当を導入しており、株主還元のタイミングを年2回に分けている。
これは、個人投資家にとって資金計画を立てやすい仕組みです。 - 配当性向は20〜30%台の安定水準。
業種平均(62.5%)と比べて控えめですが、これは「将来の研究開発投資を優先する」姿勢の表れです。 - 当期純利益の増減にもかかわらず、配当額を安定させている。
2023年に利益が減少しても22円を維持したことからも、配当安定化の意志が強いことがわかります。
配当関連指標の状況
有価証券報告書に記載されている主要な株主還元関連指標は以下の通りです。
| 指標名 | 数値(2025年7月期) | 備考 |
|---|---|---|
| 配当性向 | 26.3% | 安定的な範囲。業種平均62.5%より低い。 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 18.13% | 資本効率が高く、今後の配当余力に余裕あり。 |
| 純資産配当率(DOE) | 約4.77% | 業種平均4.08%を上回り、還元力が高い。 |
| 自己資本比率 | 44.7% | 安定した財務基盤を維持。 |
| 営業キャッシュフロー | ▲10.9億円 | 一時的なマイナスも、投資拡大による。 |
これらのデータから、ファーマフーズは「投資と還元のバランスを取る安定成長型」の配当政策をとっていることが読み取れます。
ROEが18%超という高水準である一方で、配当性向は26%台と控えめ。この組み合わせは、「成長余力を残しつつ、株主にも還元する」企業に見られる典型的なパターンです。さらに、DOEが4.77%と業種平均を上回っており、資本を効率的に活用していることも確認できます。
近年の動向と背景
2024年以降、ファーマフーズは大型の成長投資を本格化させています。
特に注目されるのは、以下の3つのプロジェクトです。
- 「卵殻膜バイオものづくりプロジェクト」(総額50億円超)
未利用資源のアップサイクルを通じて、新しい素材ビジネスを構築。 - 「医薬品新工場建設」(約125億円)
明治薬品などの医薬品生産体制を強化し、国内外の供給網を拡充。 - 「GABA(ギャバ)」の米国FDA認証取得
グローバル展開による収益基盤の拡大を目指す。
こうした成長投資は中長期的な利益拡大を目的としており、配当政策にも影響を与えています。つまり、現段階では「安定配当+内部留保重視」の体制を維持しながら、将来的な増配の余地を確保しているフェーズといえます。
さらに、2024年10月に伊藤忠商事株式会社との資本業務提携を締結しており、資本政策・物流・海外展開の面でのシナジー効果が期待されています。この提携により、ファーマフーズの資金調達力と成長基盤はより強固になり、中長期的には安定した増配余地が広がると考えられます。
今後の配当方針の方向性(予測)
現時点の情報から、ファーマフーズの今後の配当方針を考えると、次のような方向性が想定されます。
1. 「安定配当」から「持続的増配」への移行
これまで同社は安定配当を基本としてきましたが、今後は事業の成熟化とともに「緩やかな増配」へ移行する可能性が高いと考えられます。
特に、BtoC事業の顧客基盤が安定しており、再購入率の高い商品群(例:「ニューモ育毛剤」など)からのキャッシュフローが継続的に入る構造ができています。これにより、配当余力が段階的に拡大する見通しです。
2. DOE(純資産配当率)の重視
今後はROEだけでなくDOE(株主資本に対する配当率)を意識した政策が重視される可能性があります。
ファーマフーズは現在4.77%と業界平均を上回っており、資本効率面で優れた位置にあります。
今後、株主還元策としてDOE目標を明示する可能性もあります。
3. 内部留保の活用とM&A戦略
当面は研究開発や新規事業への投資を優先しつつも、投資先の成果が出始める2026年度以降には、M&Aや新規プロジェクトの成果を背景に「増配+自社株買い」の検討余地が出てくるでしょう。
4. 株主との中期的な信頼構築
配当性向が20~30%台という水準は、「堅実さ」と「柔軟性」の両方を兼ね備えています。業績が伸びる局面では増配、減益局面でも据え置きで対応できるため、長期保有株主にとって安心感があります。
今後の配当見通し(シナリオ別のイメージ)
| シナリオ | 前提条件 | 配当政策の見通し | コメント |
|---|---|---|---|
| 成長シナリオ | 医薬品新工場稼働、創薬事業のライセンス収入拡大 | 年1〜2円ずつ増配の可能性 | キャッシュフロー改善でDOE上昇へ |
| 安定シナリオ | 現行事業が堅調に推移 | 年25円前後を維持 | 安定配当継続で信頼重視 |
| 投資先行シナリオ | 研究開発費増加、バイオ分野への再投資 | 配当据え置きまたは微減の可能性 | 内部留保を厚くし、長期成長に備える |
現実的には「安定シナリオ」と「成長シナリオ」の中間に位置すると考えられます。
業績が安定している限り、減配の可能性は極めて低く、「据え置きまたは小幅増配」が中心となるでしょう。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
ファーマフーズは、他の日本株と比較して配当利回りでは平均的ながら、配当の持続性ではトップクラスに位置します。特に、研究開発企業としては稀に見る「安定配当+増配意欲」を示しており、長期的に保有することで安定収入を狙えるタイプです。
同社の強みは、ヘルスケア素材・育毛剤・創薬研究という複数の収益源を持ち、景気に左右されにくい構造にあることです。一方で、今後も研究開発費が増加する可能性があり、短期的な配当増額は限定的と見られます。
したがって、「高配当狙い」よりも「安定配当による資産形成」を目指すFIRE志向の投資家に向いた銘柄といえます。
今後は伊藤忠商事との提携により、海外展開や資金調達面が強化されるため、配当の持続力がさらに高まる可能性があります。
総合的にみて、「長期的に安定して配当を得たい投資家にとって堅実な選択肢」という位置づけが妥当です。