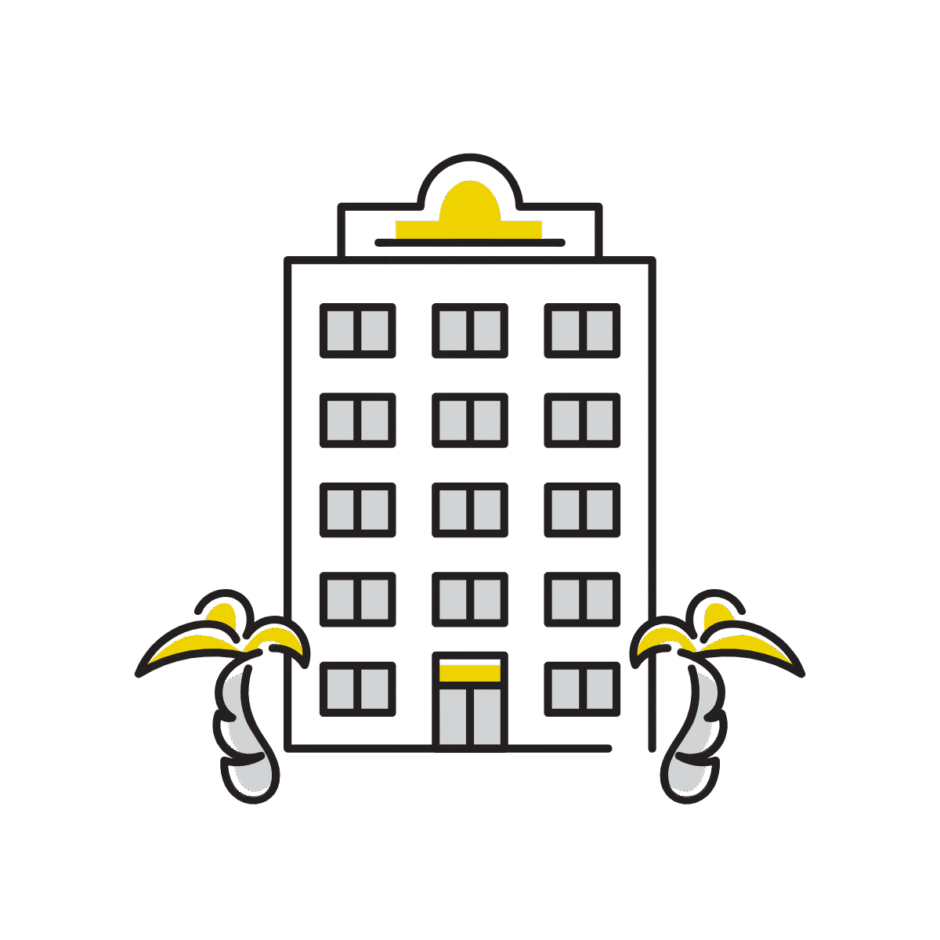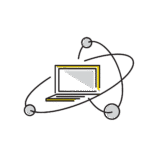企業概要
事業内容とリスク
楽待株式会社(旧・ファーストロジック)は、投資用不動産に特化した日本最大級のポータルサイト「楽待」を運営しています。このサービスは、個人投資家と不動産会社・リフォーム会社などを結びつける「マッチングプラットフォーム」であり、物件掲載、提案、広告、査定・一括見積、プレミアム会員といった多様なサービスを展開しています。登録会員は46万人を超え、年間ページビュー数は1億8,000万PVに達しています。
「物件掲載サービス」では、不動産会社が売却希望の物件情報を掲載し、投資家からの問い合わせを獲得します。「提案サービス」では、投資家が希望条件を登録することで、不動産会社が最適な物件を紹介できる仕組みです。また「楽待プレミアム」では、有料会員が専門的な記事・動画を無制限に閲覧でき、学習と投資判断を支援しています。
事業リスクとしては、不動産市場や金利動向に依存する性質があり、景気変動や法規制の変更が影響を及ぼす可能性があります。また、Googleなど外部検索エンジンへの集客依存度が高く、アルゴリズム変更による順位低下はアクセス減少につながるリスクがあります。さらに、個人情報漏洩リスクやサーバーダウンなどのシステム障害も事業継続性に関わる重要課題とされています。
近年ではChatGPTを活用した不動産会社向けの物件PR自動生成機能をリリースしており、AI技術の導入によって効率化と新サービス創出を進めています。
投資家にとって重要なのは、この事業が「広告モデル」であり、景気に左右されにくいストック型収益を持つ点です。不動産投資家が増えるほど掲載企業も増加し、ネットワーク効果が働く構造になっています。
今までの業績
同社の業績は着実に拡大しており、営業収益は2021年7月期の17億円から2025年7月期には31億円へと成長しました(約83%増)。経常利益も1.7億円から1.7億円へとほぼ倍増し、当期純利益は1.17億円と過去最高を更新しています。自己資本比率は86.6%と非常に健全で、無借金経営に近い堅実な財務体質が特徴です。
1株当たり純利益は56.09円(前年37.35円)、ROEは21.4%と高水準を維持しています。これは少数精鋭(従業員数80名)による高効率経営の成果であり、営業利益率も約49%と業界でも突出しています。
株価面では、TOPIXを上回る株主総利回り(330%)を記録しており、株主還元姿勢も強いことが伺えます。1株配当は10円(うち中間5円)で、配当性向は17.8%と安定配当を志向しています。内部留保を成長投資と技術開発に振り向けるバランス型の資本政策が特徴的です。
サイト指標の面でも、登録会員数は2021年から2025年にかけて約20万名増加、掲載物件数も5万件から7.7万件へ増えています。ページビューは1.4億PVから1.8億PVへと上昇し、ユーザーエンゲージメントが高まっていることが確認できます。
また、広告サービス・プレミアム会員の伸びが営業収益増の中心となっており、従来の物件掲載料収入に加え、サブスクリプション型収益モデルが新たな成長軸として機能しています。
このように、同社は「景気に左右されにくい広告×サブスク型ビジネス」で安定成長を続けており、業績の一貫性と高収益性が個人投資家にとっての魅力となっています。
今後の業績
同社は「公正な不動産投資市場の創造」を掲げ、投資家・不動産会社双方にとって信頼されるプラットフォームの構築を目指しています。今後の重点戦略は以下の3点に集約されます。
- AI活用とコンテンツ強化
ChatGPTや独自アルゴリズムを活用し、物件PRや問い合わせ対応を自動化することで、不動産会社の業務効率を高めます。投資家向けには、動画・記事・コラムを拡充し、有料会員の満足度向上と継続率アップを図ります。 - プラットフォームの拡張と多角化
「楽待プレミアム」に加え、査定・一括見積など周辺サービスを拡大し、物件取引前後のフェーズすべてを支援するエコシステムを構築します。また、YouTubeチャンネル登録者数100万人超という強力なメディア力を活かし、ブランド認知と新規顧客獲得を同時に進めます。 - 人材・組織基盤の強化
従業員の平均年齢31歳と若い組織を背景に、AI・データ分析に強い人材採用を継続。柔軟な働き方やフレックス制度の導入で定着率を高め、長期的な開発体制を支えます。
経営環境として、不動産投資需要は高金利環境でも底堅く、特に個人投資家の「FIRE・不労所得」志向の高まりが追い風です。楽待の利用者層はまさにこのトレンドに合致しており、安定した会員基盤とブランド力を武器に成長余地は十分にあります。
一方、リスク要因としては、①検索エンジン依存度、②データセキュリティ、③競合の新規参入が挙げられます。これらへの対応として、SEO以外の集客(YouTube・SNS・アプリ通知など)の強化、情報管理の外部監査体制の整備、技術者採用の拡充を進めています。
総じて、楽待は「安定した広告収入+拡大する有料会員モデル+AIによる効率化」の三本柱で、今後も高利益体質を維持できる見込みです。配当は安定成長を前提とした増配余地があり、長期保有を志向する個人投資家にとって魅力的な銘柄といえるでしょう。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | 業種平均(サービス業) | 楽待株式会社(2025年7月期) | 差異(ポイント) | コメント概要 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 7.34% | 21.4% | +14.06pt | 高収益体質。自己資本を効率的に活用しており、業種平均の約3倍。 |
| 総資産経常利益率 | 0.89% | 28.6%(推定) | +27.71pt | 資産効率が極めて高く、固定費の少ないネット型事業特性が反映。 |
| 売上高営業利益率 | 5.75% | 48.9%(推定) | +43.15pt | 広告・掲載料主体の高マージン構造。運営コストが低い。 |
| 自己資本比率 | 6.68% | 86.6% | +79.92pt | 無借金経営に近く、財務の健全性が圧倒的。 |
| 配当性向 | 41.33% | 17.83% | −23.50pt | 内部留保を重視。成長投資を優先する配当方針。 |
| 純資産配当率(DOE) | 2.37% | 3.78%(推定) | +1.41pt | 総じて資本効率が高く、安定配当の余地も十分。 |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)について
楽待株式会社のROEは 21.4% と非常に高水準です。
サービス業平均の7.34%を大きく上回り、約3倍に達しています。この数値は、自己資本をどれだけ効率的に利益へ変換できているかを示すものであり、経営の収益性と資本効率の両面で優れていることを意味します。
ROEが高い理由は、固定資産をほとんど保有しないインターネット型ビジネスモデルにあります。「楽待」は不動産仲介を自社で行うのではなく、あくまで“投資家と不動産会社を結びつけるプラットフォーム”として機能しており、在庫を持たない構造です。この軽資産モデルが、資本の回転効率を極めて高めています。
また、売上増加率(前年比33.6%)が利益率の改善と同時に進んでいるため、単なる一時的な利益率上昇ではなく、持続的な成長が反映されたROEといえます。今後、配当性向を若干引き上げてもこのROE水準を維持できる余力があり、株主資本の増加と利益成長が両立している理想的な状態といえます。
② 総資産経常利益率について
総資産経常利益率(ROA)は、総資産に対してどれだけ経常利益を生み出しているかを示す指標です。業種平均は0.89%ですが、楽待は経常利益17.5億円・総資産61億円から 約28.6% と推定され、圧倒的な高水準にあります。
これは、総資産の大部分が現金・預金で構成されていること、負債がほとんどなく資産効率が高いことが要因です。資産回転率の高さと収益率の高さを兼ね備えた企業であり、いわゆる「キャッシュリッチ・高ROA型企業」の典型です。
特に、広告・掲載サービスという“ストック型ビジネス”は、追加投資を必要とせずに利益を上積みできる点が特徴です。総資産に対してこれほどの利益率を誇る企業は上場サービス業の中でも稀であり、投資家にとって安定した収益基盤を持つ企業といえます。
③ 売上高営業利益率について
楽待の営業利益率は 約48.9%(営業利益15.4億円/営業収益31.6億円)と、非常に高い水準です。サービス業平均の5.75%を43ポイント上回り、まさに“高収益モデル”といえる構造です。
主な理由は、①物件掲載・提案・広告といったデジタル商品が中心で原価が低いこと、②コンテンツ制作を自社で行うためマージンが社内に留まること、③クラウド型サービスによりサーバーコストや販売費を抑制できている点にあります。
この利益率はSaaS型プラットフォーム企業に匹敵し、同規模のサービス業と比較しても異例の水準です。さらに、有料会員「楽待プレミアム」などのサブスクリプション収益が増加傾向にあり、今後も利益率の維持が期待されます。
④ 自己資本比率について
自己資本比率は 86.6% と、サービス業平均の6.68%を約80ポイント上回っています。これは、ほぼ無借金経営で運営されていることを意味し、財務の安定性が極めて高い企業です。
一般的に、50%以上で「健全」とされる水準を大きく超えており、外部環境の変化にも耐え得る強固な財務体質を示しています。資本金は8,735万円と小規模ながらも、内部留保の積み上げによって純資産は53億円を超えています。
このような高自己資本比率は、景気変動に対して企業の存続力を高めると同時に、長期投資家にとっての安心材料になります。借入依存がないため、金利上昇局面におけるリスクも限定的です。
⑤ 配当性向について
楽待の配当性向は 17.83% と、業種平均(41.33%)を約23ポイント下回っています。これは、現時点で利益の多くを再投資に回していることを示します。つまり、短期的な還元よりも中長期的な成長を優先する経営姿勢です。
この低配当性向は、ネガティブな意味ではなく、「利益の拡大局面」にある企業特有の特徴です。まだ成長段階にあるため、開発投資やAI導入、システム増強などに資金を充てており、将来の収益力を高める意図が読み取れます。
また、1株配当10円に対し、1株利益56円を確保しているため、仮に配当性向を30%前後に引き上げても十分に持続可能です。今後、利益水準が安定すれば段階的な増配も視野に入るでしょう。
個人投資家にとっては、現時点での利回りは控えめながら、「将来の増配余地」という点で魅力的なポジションにあります。
⑥ 純資産配当率(DOE)について
純資産配当率(DOE)は、株主資本に対する年間配当金の割合を示します。業種平均は2.37%ですが、楽待は 約3.78%(配当10円 × 発行株式2,115万株 ÷ 純資産53億円)と推定されます。
これは、自己資本を積み上げつつ、一定の配当を継続しているバランス型の経営方針を示しています。
高ROEと低配当性向を両立しているため、内部留保の積み上げによる資本効率の改善が続き、結果としてDOEも安定して推移しています。
DOEが3%を超える水準は、資本効率が高い上場企業の目安とも言われており、長期的な株主還元への意識がうかがえます。
配当方針と今後の展望
1. 有価証券報告書に記載の配当方針
2025年7月期有価証券報告書によると、楽待株式会社の配当方針は以下の通りです(要約)。
「当社は、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としつつ、将来の事業展開や経営基盤の強化に必要な内部留保とのバランスを考慮して配当を決定しております。」
この一文からも分かるように、同社は「安定した配当を続けること」と「成長投資のための内部留保」の両立を重視しています。
また、株主への利益還元を行いながらも、事業拡大・AI投資・人材育成などを積極的に進める姿勢を明確に示しています。
実際、同社は創業以来、一度も無配転落を経験していません。経済環境が変化しても配当を維持しており、「安定配当型企業」としての評価が高まっています。
2. 配当実績と関連指標
以下は、報告書に記載されている直近5期分の配当と利益指標の推移です。
| 決算期 | 1株当たり配当額(円) | 1株当たり当期純利益(円) | 配当性向(%) |
|---|---|---|---|
| 第16期(2021年7月) | 10.00 | 22.18 | 22.50 |
| 第17期(2022年7月) | 11.00 | 31.14 | 17.66 |
| 第18期(2023年7月) | 14.00 | 35.05 | 19.92 |
| 第19期(2024年7月) | 8.00 | 37.35 | 21.42 |
| 第20期(2025年7月) | 10.00(中間5円+期末5円) | 56.09 | 17.83 |
これらの数字から見えてくるのは、利益成長に対して控えめな配当性向という特徴です。
営業利益や純利益は右肩上がりで増加していますが、配当は一定水準を維持する慎重な方針を取っています。
配当性向はおおむね18〜22%の範囲で推移しており、内部留保を厚くする経営判断がうかがえます。
また、同社の自己資本比率は86.6%、ROE(自己資本利益率)は21.4%に達しており、財務面では非常に健全です。借入金が少なく、キャッシュ・フローも営業黒字が継続しています。
これにより、今後も安定配当を支える余力は十分にあると考えられます。
3. 配当政策の背景にある経営姿勢
楽待の配当政策を支える根本には、「軽資産・高収益モデル」という事業構造があります。
不動産そのものを保有せず、投資家と不動産会社をつなぐポータルサイト運営が中心であるため、設備投資が少なく、利益が現金として積み上がる構造です。
このため、キャッシュフローの安定性が高く、配当原資にも余裕があります。
一方で、AIやデジタル技術の導入を積極的に進めており、ChatGPTを活用した不動産会社向けPR自動生成ツールなどを次々と投入しています。
これらの開発費用やシステム強化には先行投資が必要であり、過剰な配当よりも内部留保の確保を優先する理由となっています。
また、若い組織体制(平均年齢31歳)を背景に、人的資本への投資も重視している点が特徴的です。
フレックスタイム制度やリモートワークなど、柔軟な働き方改革を進めることで優秀な人材を確保し、将来的な競争力強化につなげています。
これらの取り組みも、短期的な配当より「持続的成長」を優先している方針の表れといえます。
4. 今後の配当方針の方向性(一般的な見通し)
同社は2025年期に1株配当10円を維持しており、今後も「安定配当+業績連動」の姿勢を継続する可能性が高いと考えられます。
以下に、一般的な企業動向と同社の現状から見た配当方針の方向性を整理します。
- 安定配当の継続方針
報告書内では、「継続的かつ安定的な利益還元」を明記しており、急な減配や配当停止を想定する文脈は見られません。
利益の増加に応じて、少しずつ増配を行う“段階的配当型”を志向していると考えられます。 - 利益成長に連動した増配余地
当期純利益は前年比+44.8%と大幅に増加しており、今後の業績が安定すれば配当性向を20%台後半に引き上げる余地があります。
仮に業績が横ばいでも、現金保有比率の高さからみて安定配当は十分に維持可能です。 - 内部留保重視の投資フェーズ
AIや広告商品の開発、システム安定化投資を継続する姿勢から、直近数年は配当よりも事業投資を優先する可能性があります。
これは将来の利益増大に向けた基盤づくりであり、長期的には株主還元余地を広げる方向に作用します。 - 配当政策の柔軟化
同社の事業は広告やサブスクリプション収益に支えられており、景気変動の影響を受けにくい構造です。
そのため、将来的に安定成長が続けば、一定の配当性向目標(たとえば25〜30%)を掲げる可能性もあります。
ただし、現時点では「安定性を最優先」としており、極端な増配や特別配当を強調するような内容は報告書上に見られません。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
楽待株式会社(旧・ファーストロジック)は、日本株の中でも「安定配当型成長企業」として極めて優れた位置づけにあります。
まず注目すべきは、財務の健全性と利益の安定性です。自己資本比率は86.6%、ROEは21.4%と、上場サービス業の平均(6〜7%)を大きく上回ります。借入金がほとんどなく、営業キャッシュフローも安定的に黒字を維持しており、配当を継続する体力が非常に強固です。この「無借金・高ROE」体質は、長期保有型の投資対象として高く評価できます。
次に、配当の持続性においても高評価が妥当です。設立以来、同社は一度も無配に転じたことがなく、景気変動期でも配当を維持してきました。配当性向はおおむね18〜22%の範囲で推移しており、慎重ながらも安定した水準です。利益を配当だけでなく成長投資にも振り向けているため、将来的な増配余地も確保しています。特にAI・クラウド投資を継続しつつキャッシュリッチな状態を保っている点は、今後の配当維持・拡充において安心感を与えます。
ただし、配当利回りの水準は他の高配当株(例えば商社・電力・通信株など)と比べるとやや控えめです。2025年7月期の1株配当は10円、株価が仮に1,100円前後とすれば利回りは約0.9%程度にとどまります。これは「インカムゲイン重視型」よりも「成長を楽しむ長期ホールド型」に適した水準といえます。したがって、即時の高配当を求める層よりも、長期的に業績と配当の両方を伸ばしていく企業を保有したい人に向いています。
また、連続増配という観点では、完全な毎期増配型ではなく、業績や投資フェーズに応じて微調整を行っています。例えば2024年期には一時的に配当を8円に引き下げましたが、その翌期には再び10円に戻すなど、慎重ながらも安定性を優先する姿勢が見られます。これは企業の信頼性を損なうものではなく、むしろ内部留保を確保して事業基盤を強化する健全な経営判断といえます。
総合的に見て、楽待株式会社は「高収益・低負債・安定配当」の三拍子が揃った堅実な企業です。
短期の配当利回りは平均的ですが、長期的な増配余地と財務の安全性を踏まえると、長期投資による配当目的の保有先としては★4/5点の高評価が妥当です。
配当を“今”よりも“将来”の視点で見たい投資家に向いた、持続成長型の企業といえるでしょう。