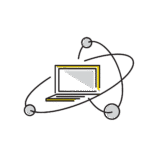企業概要
事業内容とリスク
テスホールディングス株式会社は、再生可能エネルギーや省エネルギー関連事業を軸に成長してきた企業です。グループ全体で22の連結子会社と4つの持分法適用関連会社を抱え、「Total Energy Saving & Solution」を経営理念に掲げています。
事業の二本柱
- エンジニアリング事業
工場や事業所向けに、省エネルギー設備や再生可能エネルギー発電システムの設計・施工・保守(EPC)を提供。特にコージェネレーションシステム(発電時の熱も利用する仕組み)や太陽光・バイオマス発電設備に強みがあります。 - エネルギーサプライ事業
自社保有の太陽光・バイオマス発電所を活用し、発電した電力を売電。小売電気事業者として法人顧客に電力を供給。バイオマス燃料の輸入販売や、発電所のO&M(運営・保守)も行い、安定的なストック収益を確保しています。
強み
- ストック型収益モデル:発電所や燃料供給は長期契約に基づくため、景気変動に左右されにくい
- 脱炭素ニーズの追い風:世界的なカーボンニュートラルの流れから、再エネ需要は今後も拡大
リスク
- 政策依存リスク:再エネ関連はFIT・FIP制度(固定価格買取制度や市場価格+プレミアム制度)に依存。制度変更が利益に直結する
- 燃料価格変動:バイオマス燃料(PKSなど)は国際市況に左右され、輸入コスト上昇が収益を圧迫
- 資金調達リスク:新規発電所開発には巨額投資が必要。借入依存度が高まりすぎると財務健全性を損なう可能性
- 利益変動の大きさ:売上は伸びても利益が赤字転落する年もあり、配当の安定性には課題
今までの業績
売上・利益推移
過去5年の連結売上高:
- 2021年6月期:3,424億円
- 2022年6月期:3,495億円
- 2023年6月期:3,441億円
- 2024年6月期:3,064億円
- 2025年6月期:3,668億円
売上は全体的に横ばい~微増傾向ですが、2024年には一時減収。ただし2025年には再び増収に転じました。
一方、利益面は波が激しく、
- 2023年:経常利益 55億円
- 2024年:経常利益 77億円
- 2025年:▲6億円(赤字)
と、2025年6月期には赤字に転落。純利益もわずか2億円にとどまりました。
財務体質
- 自己資本比率:2025年6月期で28.1%(前年34.8%から低下)
- 総資産:1,512億円と増加基調
- 現金残高:164億円と一定の流動性は確保
借入に依存しつつ資産規模を拡大しており、成長投資とリスクの両面が見えます。
配当実績
- 2021年:20.52円
- 2022年:21.00円
- 2023年:26.00円
- 2024年:16.00円
- 2025年:5.12円(予定)
利益水準の変動に伴い、配当額も大きく上下している点が特徴です。配当性向は2025年で69%と高水準ですが、安定配当とは言い難い状況です。
今後の業績
成長ドライバー
- 再生可能エネルギーの拡大
太陽光発電所を12拠点、バイオマス発電所を3拠点運営。今後も新規案件を積極的に開発・取得予定。 - オンサイトPPAモデル
工場や施設に自家消費型太陽光発電を設置し、長期契約で電力を供給。2025年6月末時点で51件(計57.8MW)の供給実績があり、安定収益化が進展。 - O&M事業の拡大
1,033件の設備に対する運用・保守契約を持ち、継続率94%と高い顧客満足度を維持。長期契約型のため将来の安定収益源として期待。 - 海外展開
インドネシアやシンガポールでのバイオマス燃料供給ビジネスを拡大。世界的な再エネ需要を取り込み、事業リスクを分散。
課題と不確実性
- 利益体質の改善:売上が伸びても赤字化する年度があるため、安定収益の仕組み強化が必要
- 政策動向:日本政府の再エネ支援策に依存する部分が大きい。補助や固定価格制度の縮小は逆風
- 株主還元の一貫性:配当額が大きく変動しているため、長期配当狙いの投資家には安心感が不足
株式関連指標の比較分析
1. 指標比較表
| 指標 | テスホールディングス(2025年6月期) | 建設業平均 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率 (ROE) | 0.49% | 10.26% | ▲9.77pt |
| 総資産経常利益率 | ▲0.42%(経常損失) | 6.19% | ▲6.61pt |
| 売上高営業利益率 | ▲1.7%(営業赤字想定) | 6.62% | ▲8.32pt |
| 自己資本比率 | 28.13% | 42.68% | ▲14.55pt |
| 配当性向 | 69.1% | 38.87% | +30.23pt |
| 純資産配当率 | 0.82% | 3.88% | ▲3.06pt |
2. コメント
(1) ROE(自己資本当期純利益率)
ROEとは、株主が投じた自己資本に対してどれだけの純利益を生み出したかを示す指標です。建設業平均が10.26%と、比較的高い水準を維持しているのに対し、テスホールディングスの2025年6月期ROEはわずか0.49%にとどまりました。これは、ほぼ利益を出せていない水準であり、株主資本を十分に活用できていないことを意味します。
背景には、売上は増加しているものの、事業投資やコスト増加により最終利益が低水準にとどまったことがあります。ROEは企業の資本効率を測る代表的な指標であり、この値が低いことは「資本を有効に使えていない」という市場からの評価につながります。長期的な投資対象として考える際、安定した配当を期待する投資家にとっては不安材料となるでしょう。
(2) 総資産経常利益率
総資産経常利益率は、企業が持つ全資産を使ってどれだけの経常利益を上げたかを示します。建設業の平均が6.19%と比較的高水準であるのに対し、テスホールディングスは2025年に経常赤字を計上しており、マイナス0.42%となっています。資産規模は拡大しているものの、それを活用して安定した利益を生み出す体制には至っていないことが分かります。
つまり「投資に見合ったリターンが出ていない」という状況です。再生可能エネルギー事業は長期的に見れば収益性が高まる可能性を秘めていますが、初期投資が大きく、短期的には赤字や収益変動が避けられない構造を持っています。特にバイオマス燃料の価格変動や発電所開発の資金負担が重荷となっている可能性があります。
(3) 売上高営業利益率
営業利益率は、売上に対する営業利益の割合を示す指標であり、企業の本業の稼ぐ力を表します。建設業平均が6.62%であるのに対し、テスホールディングスは営業赤字を計上しており、▲1.7%程度に留まりました。
これは、売上は増えても利益がついてこない状況を如実に示しています。再生可能エネルギー事業は、建設コストや燃料調達コストが大きく、価格競争や制度変更にも影響を受けやすいため、営業利益率が安定しにくい特徴があります。さらに、売電価格が固定されるFIT制度から、市場価格と連動するFIP制度への移行が進む中で、利益の変動幅が大きくなりやすい点もマイナス要因です。
(4) 自己資本比率
自己資本比率は財務の健全性を示す指標であり、建設業平均が42.68%であるのに対し、テスホールディングスは28.13%と低い水準です。これは、借入依存度が高く、財務の安定性が同業他社よりも弱いことを意味します。再生可能エネルギー事業は設備投資が巨額となるため、どうしても借入に頼らざるを得ません。
一方で、自己資本比率が30%前後であれば、極端に危険な水準とは言えません。しかし業種平均に比べて低いことは確かであり、金利上昇局面や金融機関の貸し出し姿勢が厳しくなる局面では資金繰りにリスクが生じる可能性があります。投資家の視点からは、今後の資本政策や財務健全性の改善策に注目すべきです。
(5) 配当性向
配当性向とは、当期純利益のうちどれだけを配当に回したかを示す指標です。建設業平均が38.87%であるのに対し、テスホールディングスは69.1%と非常に高い水準です。つまり、利益の大半を株主還元に充てていることになります。
一見すると株主思いの姿勢に見えますが、利益が低い中で高い配当を維持することは将来の成長投資余力を削ぐリスクがあります。特に2025年は純利益が2億円程度と低水準であるにもかかわらず配当を出しているため、財務負担が増し、持続可能性に疑問が生じます。投資家にとっては「減配リスクが高い」とも言え、長期的な配当収入を狙う上では安定性に欠ける印象を持たざるを得ません。
(6) 純資産配当率
純資産配当率は、株主が持つ純資産に対する配当の割合を示すもので、建設業平均が3.88%であるのに対し、テスホールディングスは0.82%にとどまります。これは、株主が持つ資産に対して配当リターンが小さいことを意味します。株主から見れば「資本を投じても十分なリターンが得られない」状況であり、魅力度が低下します。
特に配当金でFIREを目指す長期投資家にとっては、この指標が低いことは看過できないポイントです。業種平均に比べて大きく見劣りしており、資本効率の改善が急務であることを示しています。
テスホールディングス株式会社の配当方針と今後の見通し
1. 配当方針の概要
テスホールディングス株式会社は、有価証券報告書において以下の配当方針を掲げています。
- 基本方針
将来の事業展開や経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、株主への利益還元を重視。安定した配当を継続して実施することを基本とする。 - 配当性向
為替予約に係るデリバティブ評価損益の影響を除いた1株当たり連結当期純利益を基準に算出し、連結配当性向30%を目安に配当を実施。業績向上に応じて還元の拡充を図る方針。 - 内部留保の活用
内部留保資金は、事業開発・設備投資・人材育成の財源として活用。 - 配当の実施方法
原則として年1回(期末配当、基準日は6月30日)。ただし、定款に基づき12月31日を基準日とした中間配当や任意の基準日での配当も可能。決定機関は株主総会または取締役会。
2. 直近期の配当実績
- 2025年6月期
- 1株当たり配当:5.12円
- 総額:3億61百万円
- 決議予定:2025年9月26日定時株主総会
過去の推移をみると、2023年の26円から2024年の16円、そして2025年の5.12円へと減配傾向が続いています。これは利益水準の悪化が主因であり、基本方針の「安定配当」と現実との乖離が見える点です。
3. 今後の配当方針の見通し
(1) 業績回復と配当の関係
同社は中期経営計画「TX2030」において、ROEを2025年の0.5%から2030年に11.7%まで高める目標を掲げています。利益水準の改善が進めば、現行方針の「配当性向30%」が現実的に機能し、配当金の増額が期待されます。
(2) 内部留保とのバランス
再生可能エネルギーやバイオマス燃料事業は巨額投資を要するため、内部留保の確保が必須です。したがって、当面は大幅な増配よりも、内部留保を優先しつつ、最低限の株主還元を維持する方針が続くと考えられます。
(3) 減配リスクの現実性
2025年のように純利益が低水準にとどまる場合、配当性向30%の目安を超えて配当が実施される可能性もあります。しかしこれは「利益以上に配当を出している」状態を意味し、財務に負担をかけます。結果として、さらなる業績悪化時には減配や無配に踏み切るリスクもあります。
(4) 投資家へのメッセージ
- 短期的展望:減配リスクが高く、配当収益を狙う投資家には不安定な環境。
- 中長期的展望:2030年にかけてROE改善や利益成長が実現すれば、安定的かつ増加傾向の配当に転じる可能性。
レーティング評価
コメント
テスホールディングス株式会社を「長期投資による長期配当」という観点から評価すると、現時点ではおすすめ度は低めと判断せざるを得ません。理由は大きく三つに整理できます。
第一に、配当の安定性が欠けている点です。同社は「連結配当性向30%を目安に安定配当を実施する」と明確な方針を掲げていますが、実際には利益の変動が大きく、配当額も2023年の26円から2024年の16円、さらに2025年の5.12円へと減少しており、長期配当を狙う投資家にとって予測しにくい状況です。他の日本株、特に成熟したインフラ・電力関連株や生活必需品株などと比較すると、配当の安定性では大きく見劣りします。
第二に、財務体質の脆弱さと投資負担です。自己資本比率は28%と業種平均を下回り、借入依存度が高い状況です。再生可能エネルギー分野は将来性がある一方で、初期投資が巨額であり、短期的には利益を圧迫しやすい構造を持ちます。実際、2025年6月期は経常赤字に陥っており、利益を原資とする配当の持続可能性に疑問が残ります。他の安定配当株と比べると、投資家に安心感を与える水準には達していません。
第三に、将来性はあるが不確実性も大きい点です。同社は「TX2030」として、2030年にROEを11.7%まで引き上げるなど明確な成長戦略を掲げています。再エネ需要の拡大やO&M事業の安定収益化が進めば、将来的には安定配当株へと変貌する可能性も十分にあります。しかしこれはあくまで「将来の期待」であり、現状の利益変動や減配実績を踏まえると、すぐに長期配当を期待するのは難しいと考えられます。
総合すると、テスホールディングスは「将来性はあるが現状は安定性に欠ける銘柄」です。長期投資家が「配当収入の安定」を第一に重視する場合、他の日本株(例えば電力株、鉄道株、食品株、通信株など)と比較すると劣後します。そのため、レーティングは★2つとしました。ポートフォリオの一部に「将来の成長性に賭ける再エネ関連株」として組み込む価値はありますが、「長期配当狙いの主力銘柄」とするにはリスクが大きいと判断します。