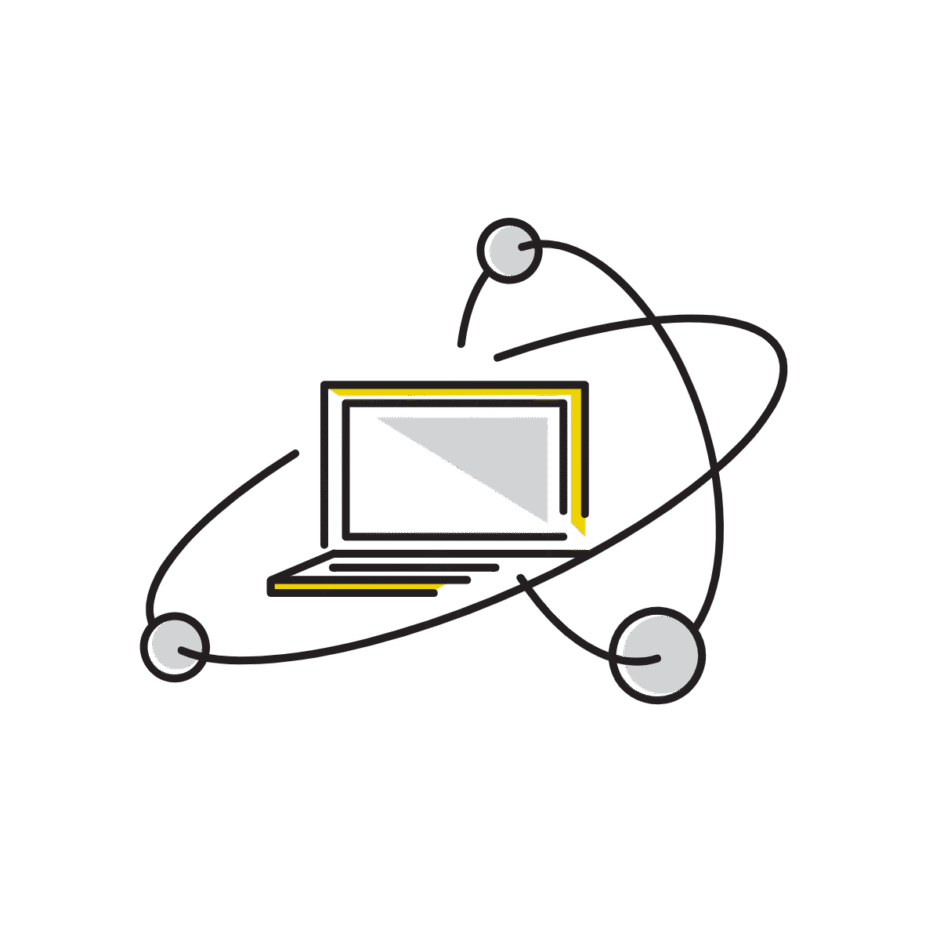企業概要
事業内容とリスク
株式会社トーシンホールディングス(以下、トーシンHD)は、名古屋を拠点とする持株会社であり、主に「移動体通信関連事業」「不動産事業」「リゾート事業」の3つを中心に展開しています。1988年の創業以来、通信販売から不動産、ゴルフ場運営まで事業の多角化を進めてきました。
まず、移動体通信関連事業では、子会社のトーシンモバイルを通じてソフトバンクやKDDI(au)と連携し、携帯電話ショップの運営や通信契約の取次業務を行っています。スマートフォンの普及や通信事業者のサービス拡張に支えられ、長期にわたり安定した収益基盤を築いてきました。しかし、通信市場の成熟や競争激化に伴い、販売奨励金や手数料体系の見直しが頻繁に発生しており、今後も利益率の圧迫が懸念されます。また、取引先である通信事業者の方針変更により、収益構造が影響を受けるリスクも存在します。
不動産事業では、名古屋市を中心に「さくらHills」シリーズなどの賃貸ビル・賃貸マンションを展開。長期的な安定収益の柱として機能しており、2025年7月には「さくらHills Rokuban Platinum Residence」が竣工しました。不動産販売や賃貸運営を通じて、堅実なキャッシュフローの確保に努めています。ただし、景気後退や金利上昇による空室率の上昇、また建築コストの増加など、外部要因によるリスクを常に内包しています。
リゾート事業は、ゴルフ場運営を中心に展開しており、岐阜・三重・愛知を中心に複数のコースを保有。「TOSHIN Golf Club」や「TOSHIN Princeville Golf Course」など、地域密着型のゴルフ場運営を行っています。近年は、団体コンペやイベント需要の回復が見られましたが、資源高や物価上昇の影響を受け、コスト負担が増加しています。ゴルフ場の整備やカート更新、システム導入など、顧客満足度向上への投資を継続している点が特徴です。
一方で、2025年度の有価証券報告書では「不適切会計処理」が明らかとなり、特別損失として4億86百万円を計上しました。この影響で継続企業の前提に重要な疑義が生じており、金融機関への返済延期や内部管理体制の改善が喫緊の課題となっています。財務面でのリスクは依然として高く、経営再建の進展が今後の投資判断に大きく関わる要素といえます。
今までの業績
トーシンHDの直近5年間の業績を見ると、売上高は約17億円前後で推移しており、全体的に安定的ではあるものの、収益性の面では大きな変動が見られます。
2021年度(第35期)には約21億円の売上を計上しましたが、その後の通信市場の競争激化や不動産投資の調整局面により、2023年度には約16億円まで減少。その後、2025年度には17億4,774万円とわずかに回復しました。
経常利益は2024年度に2億8,482万円の黒字を計上しましたが、2025年度は3,199万円の赤字転落。純利益も前年度の1億4,218万円黒字から、8,452万円の赤字へと悪化しました。主な要因は、前述の不適切会計問題に伴う特別損失の発生と、通信事業の利益率低下です。
セグメント別に見ると、最も売上比率の高い「移動体通信関連事業」が150億円超を占めていますが、セグメント利益は9,100万円の赤字。不動産事業は売上9億円、利益4億9,800万円と安定した黒字を維持し、グループ全体の収益を下支えしました。リゾート事業は売上14億円、利益2億2,300万円と堅調で、施設改善投資を進めながらも一定の利益水準を確保しています。
また、キャッシュ・フロー面では営業活動によるCFが2億8,178万円と堅調に推移。一方で投資活動によるCFは15億円のプラスと大幅な改善を見せました。これは保有資産の売却益が寄与した結果であり、資金繰りの安定化に貢献しています。しかし、財務活動によるCFはマイナス8億5,244万円であり、借入金返済や社債償還が資金流出要因となっています。
財務体質の面では、純資産が24億1,918万円、自己資本比率は9.74%と低下傾向にあります。金融機関からの借入が多く、レバレッジ型の経営構造となっているため、今後は資産売却や財務再構築による安定化が求められます。
今後の業績
今後のトーシンHDの業績見通しを考える上では、3つの柱である「通信」「不動産」「リゾート」のいずれもが再構築フェーズにあることがポイントです。
まず、通信事業では、ソフトバンクおよびKDDIの戦略に依存する構造からの脱却が課題です。スマホ販売だけにとどまらず、法人営業や金融・決済関連サービスを組み合わせた収益モデルへの転換が進められています。中長期的には店舗効率化や人件費抑制により黒字化を図る方針で、既存店のリニューアルや立地改善も進めていく見通しです。
不動産事業では、安定収益を生み出すコア事業としての位置づけがさらに強化されます。名古屋圏を中心に新規開発物件を増やしつつ、既存物件のリニューアルと入居率向上に注力。2025年に竣工した「さくらHills Rokuban Platinum Residence」など、高付加価値物件の開発が進められており、家賃水準の維持・上昇による収益改善が期待されます。
リゾート事業は、国内ゴルフ需要の安定化を背景に、引き続き堅調な推移が見込まれます。特にインバウンド観光の回復が進めば、海外利用者の増加も見込まれ、既存施設の改修投資によるサービス強化が鍵となります。一方で、物価上昇や燃料費の高止まりはコスト圧迫要因であり、効率的な運営体制の確立が重要です。
会社全体としては、内部統制強化を含む経営再建フェーズにあり、不適切会計問題によって毀損した信頼の回復が最優先課題です。金融機関からの支援継続を受けながら、資産売却を進めて債務圧縮を図る計画が示されています。
継続企業の前提に関する重要な疑義は依然として残りますが、内部管理体制の改善と収益性の高い事業への選択と集中により、中長期的には再び黒字基調への回復を目指す構えです。
業種平均の比較分析
指標比較表
| 指標 | 業種平均(情報・通信業) | トーシンホールディングス | 差異(ポイント) |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 10.68% | -3.39% | -14.07 |
| 総資産経常利益率 | 5.45% | -0.13% | -5.58 |
| 売上高営業利益率 | 11.36% | 0.25% | -11.11 |
| 自己資本比率 | 32.89% | 9.74% | -23.15 |
| 配当性向 | 37.14% | ―(赤字のため算出不可) | ― |
| 純資産配当率 | 3.45% | 約2.71%(10円配/純資産369.5円) | -0.74 |
コメント・詳細分析
① 自己資本当期純利益率(ROE)
ROE(Return on Equity)は、株主が投じた自己資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。業種平均の10.68%に対し、トーシンホールディングスは-3.39%と大きく下回っています。これは、当期純損失(約8,452万円)の発生により自己資本を活かしきれていないことを意味します。
背景として、2025年4月期に特別損失として「過年度決算訂正費用(約4億8,600万円)」を計上したことが大きく響いています。赤字計上により自己資本も2億円以上減少しており、株主資本の効率性が一時的に大きく悪化しました。
ROEの低下は一般的に「企業の収益性の低下」や「自己資本の過剰保有」などを示唆しますが、同社の場合は後者ではなく、特別損失による一時的要因が中心です。今後は、経常的な黒字回復と資産圧縮を通じた効率性改善が鍵となります。中期的にROEをプラス圏(3〜5%)へ戻すことが、株主還元余力を取り戻す第一歩になるでしょう。
② 総資産経常利益率(ROA)
ROA(Return on Assets)は、総資産に対してどれほど利益を生み出しているかを示す指標であり、企業の資産運用効率を測る尺度です。情報・通信業平均の5.45%に対し、トーシンホールディングスは-0.13%。資産の大きさに対して利益がほとんど出ていない状況です。
特に同社は、不動産やゴルフ場といった固定資産の比率が高く、総資産は約245億円にのぼる一方で、利益額はごく僅か。これによりROAが著しく低下しています。不動産業やリゾート事業は減価償却負担が重く、また資金調達に依存するため、資産回転率が低い構造的特徴があります。
今後の改善策としては、「資産のスリム化」と「収益資産への転換」が挙げられます。すでに報告書内でも、金融機関支援を受けつつ資産売却を進める方針が明示されており、これが実現すればROA改善につながる可能性があります。特に不採算ゴルフ場や遊休地の売却が実行されれば、利益率は中期的に1〜2%台まで回復する余地があります。
③ 売上高営業利益率
業種平均の11.36%に対し、トーシンHDの営業利益率は0.25%と非常に低い水準です。これは、売上総利益率が18.8%(前年23.5%)まで低下したことに加え、人件費や修繕費など固定費負担が重い構造に起因しています。
特に通信事業では、キャリアの手数料体系変更や販売奨励金減少の影響が大きく、従来の「量を追う販売モデル」が通用しにくくなっています。また、リゾート事業でも原材料費や燃料費の上昇が続いており、コスト構造全体が圧迫されています。
一方で、不動産事業は4億9,800万円のセグメント利益を確保しており、全体の営業黒字維持に寄与しています。中長期的には、不動産事業の安定利益と、リゾート事業の黒字体質化を両立させることで、営業利益率3〜5%の回復を目指すことが現実的なターゲットです。
④ 自己資本比率
情報・通信業の平均自己資本比率32.89%に対し、トーシンホールディングスは9.74%。これは平均の約3分の1の水準にとどまっています。財務の健全性という観点では、明確な課題が残ります。
自己資本比率の低さは、借入金依存度の高さを意味します。実際、同社は過去に名古屋市錦二丁目の大型ビル建設にあたり、5行によるシンジケーションローン(総額31億円)を締結しており、長期債務が財務を圧迫しています。この契約には「純資産維持率75%以上」「2期連続経常損失禁止」といった財務制限条項も含まれており、経営改善が急務です。
一方で、不動産資産は担保価値を有しているため、資金調達面での即時的なリスクは限定的と考えられます。ただし、今後も自己資本比率10%を下回る状態が続けば、追加融資や資本政策に制約が生じる可能性があります。資産売却や増資による自己資本の強化が望まれます。
⑤ 配当性向
情報・通信業平均の配当性向は37.14%であり、収益の約3分の1を配当として株主に還元している水準です。一方、トーシンHDは当期純損失を計上しているため配当性向は算出不可。実質的には「赤字でも配当を維持」している形で、財務的には慎重な判断が求められます。
2025年4月期の1株配当は10円(前期22円から減配)。それでも赤字下での配当維持は、株主への誠実な対応として評価できますが、長期的には財務負担となるリスクも伴います。
今後の利益回復を前提とすれば、黒字転換後に業種平均水準(30〜40%)の配当性向を回復することが期待されます。特に不動産・リゾート事業の安定化が進めば、再び配当余力を取り戻す可能性は十分あります。
⑥ 純資産配当率(DOE)
DOE(Dividend on Equity)は、企業が純資産に対してどれだけの割合で配当を支払っているかを示す指標です。トーシンHDの純資産配当率はおおよそ2.71%(10円配当 ÷ 1株当たり純資産369.5円)。業種平均の3.45%を約0.7ポイント下回っています。
これは、配当を維持している一方で純資産が減少しているため、相対的に低下している形です。ROEがマイナスの局面ではDOEの維持は難しく、配当継続は企業の信頼維持を優先した戦略的判断とみられます。
投資家目線では、DOEが安定して推移する企業は「中長期で株主重視の経営姿勢を持つ」と評価されやすく、トーシンHDも財務健全化と並行してDOEを再上昇させることが、今後の市場評価を左右する要因となります。
配当方針と今後の展望
これまでの配当実績と方針
有価証券報告書によると、トーシンHDは安定的かつ継続的な配当を重視する方針を掲げています。実際、過去の配当履歴をみると、業績に波がありながらも、赤字期を除き、毎期一定の配当を維持してきました。
直近の2025年4月期(第37期)においては、以下の通り2回の配当が実施されています。
| 決議日 | 株式の種類 | 1株当たり配当額 | 総額(千円) | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年6月9日 | 普通株式 | 12円 | 77,589 | 2023年7月14日 |
| 2023年12月8日 | 普通株式 | 12円 | 77,587 | 2024年1月19日 |
| 2024年6月10日(翌期配当) | 普通株式 | 10円 | 64,651 | 2024年7月12日 |
これらの数値からも分かるように、同社は当期赤字でありながらも、株主への還元を維持しています。2025年4月期の純損失は約8,400万円であり、財務上の厳しい局面にもかかわらず、配当継続を選択した点は、株主還元への強い意識を示すものといえます。
有価証券報告書では明確な文言として「安定配当を継続することを基本方針とし、業績や財務状況を総合的に勘案して決定する」と記載されています。このため、単年度赤字が生じた場合でも、財務健全性が許容範囲にある限りは、一定の配当を維持する方針であると解釈できます。
財務面から見た配当の持続可能性
自己資本比率は9.74%と低く、借入金依存度の高さが課題とされていますが、不動産やリゾート資産など現物価値を持つ保有資産が多く、債務超過には至っていません。また、2025年4月期には営業活動によるキャッシュ・フローが2億8,000万円のプラスを維持しており、一定の資金余力があります。
さらに、保有している不動産は収益物件として安定的なキャッシュフローを生み出しているため、短期的には配当支払いに必要な資金を確保できる見通しです。
ただし、報告書にも記載がある通り「継続企業の前提に重要な不確実性」が存在し、金融機関との融資条件や返済スケジュールの調整が必要な状況にあります。そのため、中長期的には「業績回復と自己資本強化」が配当維持の前提条件となるでしょう。
配当関連指標の現状
トーシンHDの2025年4月期における配当関連指標は次の通りです。
| 指標 | 数値 | コメント |
|---|---|---|
| 1株当たり配当金 | 10円 | 前期比 -12円(減配) |
| 配当性向 | ―(赤字のため算出不可) | 収益悪化により算出不能 |
| 純資産配当率(DOE) | 約2.7% | 業種平均(3.45%)をやや下回る |
| ROE | -3.39% | 利益減少の影響でマイナス転落 |
特筆すべきは、赤字期にもかかわらず配当を実施している点です。これは、株主への信頼維持を目的とした「戦略的配当」と位置づけられます。一方で、配当性向が算出不能となるほど業績が落ち込んでいるため、今後の継続性には経営再建の進展が不可欠です。
今後の配当方針の展望
今後のトーシンHDの配当方針は、以下の3つの要素によって大きく左右されると考えられます。
1. 不動産事業の収益回復
同社の中核事業である不動産セグメントは、2025年度に4億9,800万円の利益を計上しており、グループ全体の安定収益源となっています。この安定収益が継続すれば、少なくとも現行水準(10円程度)の配当維持は可能です。新規開発「さくらHills」シリーズの稼働率向上が鍵となります。
2. 通信事業の再構築
携帯販売代理事業では、KDDIやソフトバンクの手数料体系見直しにより収益が圧迫されています。しかし、同社は法人向け通信サービスやスマートデバイス販売への展開を進めており、黒字化に転じれば営業利益率の改善が見込まれます。これにより、配当余力が再拡大する可能性があります。
3. 財務再建とキャッシュ・フロー管理
報告書に記載の通り、継続企業の前提に不確実性がある状況では、金融機関との協議を継続しつつ、資産売却や借換えによる資金安定化が優先されます。財務改善が進めば、将来的に業種平均の配当性向(約37%)に近い水準への回帰も視野に入るでしょう。
予測される今後の配当方針
現状の財務体質を踏まえると、トーシンHDの短期的な配当方針は「減配を経て安定維持」、中期的には「業績回復に応じた漸進的な増配」になると見込まれます。すぐに高配当へ転換する可能性は低いものの、資産構成が安定しているため、無配転落のリスクも限定的です。
仮に2026年4月期で黒字回復が実現すれば、配当性向30%前後を目安にした復配方針が再確認される可能性があります。企業としても「株主との長期的信頼関係」を重視しているため、安定配当を軸にした経営姿勢は維持されるでしょう。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
トーシンホールディングス(東証スタンダード上場)は、通信代理店・不動産・リゾート事業を展開する企業で、株主還元に一定の実績を持ちますが、「長期配当を狙う投資先」としては総合的にみて厳しめの評価となります。
まず、配当利回りの観点から見ると、2025年4月期の年間配当は10円であり、株価(仮に500円前後と想定)を基準にした単純利回りは約2%程度にとどまります。日本株全体の平均配当利回り(約2.3〜2.5%)と比べるとやや低水準で、高配当株としての魅力は限定的です。特に、同業の通信関連銘柄(KDDI、NTT、伊藤忠テクノソリューションズなど)が3〜4%台の利回りを維持している点を考慮すると、相対的な見劣りは否めません。
次に、配当の持続性についてですが、ここが最も重要な評価要素です。2025年4月期は純損失約8,400万円を計上しており、配当性向の算出すらできない状況です。にもかかわらず10円の配当を維持した点は株主還元姿勢を示す一方で、財務的にはやや無理のある配当とも言えます。自己資本比率が9.7%と低く、有利子負債依存度も高いため、長期的に安定して配当を出し続けるには経営再建が前提条件です。つまり、「今後も減配リスクを内包している状態」と言えます。
連続増配の実績についてもマイナス要素です。直近では2024年度の22円から10円へと減配しており、減配が発生した銘柄は、投資家の信頼回復に時間がかかる傾向があります。過去には業績が安定していた時期に増配を行った実績もありますが、現時点では「連続増配銘柄」とは言えません。したがって、長期保有で配当金を積み上げていくスタイルの投資家には、ややリスクが高い位置づけとなります。
ただし、ポジティブな側面もあります。同社の不動産セグメントは毎期黒字を確保しており、賃貸収益による安定的なキャッシュフローがあります。また、リゾート事業も黒字を維持しており、これらの収益基盤が今後の配当原資を支える可能性はあります。将来的に経営再建が進み、自己資本比率が15〜20%台に回復すれば、再び配当性向30%台への回帰も視野に入るでしょう。
しかし、現段階では「業績安定・増配基調の長期投資向き銘柄」というよりも、「再建期にある中配当銘柄」に分類されます。配当を重視したポートフォリオを組む場合には、KDDI、オリックス、日本特殊陶業などの連続増配銘柄と比較すると、安定性・信頼性の面で差があります。よって、長期投資目的での評価は★2つが妥当と考えられます。
結論として、トーシンホールディングスは「中長期的な再成長を見守る段階」にある企業であり、安定配当株としての魅力は限定的です。高配当や連続増配を軸にFIREを目指す投資家にとっては、今後の業績回復と財務改善を確認してから検討するのが現実的でしょう。