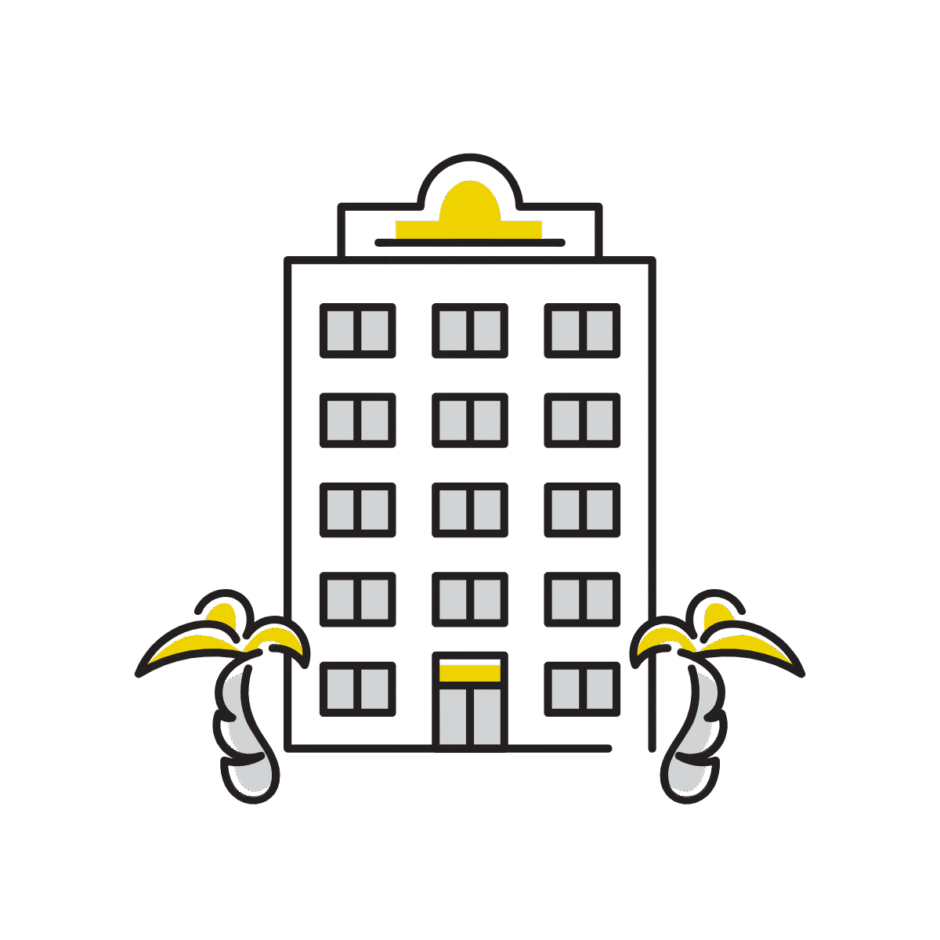企業概要
事業内容とリスク
株式会社メイホーホールディングスは、岐阜県を本拠地に「企業支援プラットフォーム」を掲げ、中小企業の成長を支援する持株会社です。グループは建設関連サービス事業、人材関連サービス事業、建設事業、介護事業の4つの事業セグメントで構成されています。
建設関連サービス事業では、主に国や地方公共団体を顧客に、測量・設計・施工管理といった建設コンサルタント業務を展開しています。公共事業の予算動向に大きく左右されるため、国や自治体の予算削減時には売上や利益に直結するリスクがあります。また、受注の大半が年度末に集中するため、業績に季節的変動が生じやすい点も特徴です。
人材関連サービス事業は、事務職派遣、技術者派遣、製造業派遣に加えて警備や海外アウトソーシングも手がけています。国内外での人材需要の増加に支えられていますが、派遣先企業の景況や労働関連法の改正などによって大きな影響を受ける可能性があります。
建設事業は、鉄道・道路・河川工事や法面工事を中心に、地域に根ざした公共工事を手掛けています。技術力とコスト競争力で強みを持つ一方、災害や事故による工事の瑕疵が発生した場合、行政処分などで事業継続に影響するリスクもあります。
介護事業は、デイサービスや住宅型有料老人ホームの運営を行い、地域密着型で差別化を図っています。高齢化社会の進展により需要は拡大傾向ですが、人材不足や物価高などの外部環境が不透明要因です。
今までの業績
直近5年間の連結売上高を見ると、2021年6月期の52億円から2025年6月期には130億円まで成長しており、拡大基調が続いています。一方で、経常利益は安定しつつも年度によって変動があり、特に2024年6月期には8,800万円まで落ち込みましたが、2025年6月期には4億4,400万円と回復しました。
純利益は2023年6月期に約2億7,000万円を計上しましたが、翌2024年6月期には赤字8,700万円に転落。それでも2025年6月期には1億6,800万円の黒字に戻しています。自己資本比率は一時26.5%まで落ち込みましたが、直近では33.1%まで改善。キャッシュフロー面では営業活動によるCFが安定してプラスを維持しており、財務基盤の強化が進んでいる点は評価できます。
株価指標を見ると、2025年6月期のPERは約22倍と成長企業に対する期待感が織り込まれています。過去には株式分割を実施しており、流動性の確保と株主還元に一定の配慮をしていることも窺えます。
今後の業績
今後の成長戦略の柱は「従業員承継型M&A」と「企業支援プラットフォーム」の拡充です。高齢化に伴い事業承継に悩む中小企業が増加しているなか、同社はグループ傘下に取り込み、経営支援を行うことで非連続的な成長を狙っています。
建設関連サービスや建設事業は、公共投資が底堅く推移する見込みのため、安定した需要が期待されます。一方で人材関連サービスは、労働人口減少を背景に今後も需要増加が見込まれ、特に外国人労働者やシニア人材の活用が鍵になります。介護事業については、要介護者数の増加により市場が拡大する見通しですが、人材確保が最大の課題となります。
財務面では、中期経営計画に基づき売上高1,000億円、営業利益100億円、グループ社員数1万人を目指す「100社・1000億・1万人」というビジョンを掲げています。個人投資家にとっては、短期的には業績の波やM&A資金調達のリスクを意識しつつも、長期的には配当や株主還元余地が広がる可能性があります。
同社の今後の成長は、中小企業支援プラットフォームとしての強みをどこまで活かせるか、またM&A後のシナジーをいかに早期に顕在化させられるかがポイントとなるでしょう。長期配当を狙う投資家にとっては、将来のキャッシュフロー創出力の強化に注目することが重要です。
業種平均の比較分析
以下は、株式会社メイホーホールディングス(2025年6月期)と、サービス業全体の業種平均を比較した表です。差異の欄には、企業の指標から業種平均を差し引いた値を記載しています。
| 指標 | 業種平均 | 企業値 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率 (ROE, %) | 7.34 | 8.00 | +0.66 |
| 総資産経常利益率 (%) | 0.89 | 6.73 | +5.84 |
| 売上高営業利益率 (%) | 5.75 | 3.41 | -2.34 |
| 自己資本比率 (%) | 6.68 | 33.14 | +26.46 |
| 配当性向 (%) | 41.33 | 0.00 | -41.33 |
| 純資産配当率 (%) | 2.37 | 0.00 | -2.37 |
コメント・詳細分析
1. 自己資本当期純利益率(ROE)
メイホーホールディングスのROEは8.00%で、業種平均の7.34%を上回っています。ROEは株主資本に対してどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標であり、この結果は株主資本を比較的有効に活用できていることを意味します。特に同社は直近で赤字から黒字へ回復したこともあり、資本効率が改善傾向にあると考えられます。ただし、ROEは一時的な利益変動に左右されやすいため、今後も安定的にこの水準を維持できるかが重要です。業種平均を上回った背景には、非連続的成長戦略であるM&Aの効果や、グループ全体の収益回復が寄与していると推察されます。
2. 総資産経常利益率
総資産経常利益率は6.73%と、業種平均の0.89%を大きく上回っています。この指標は総資産全体に対する利益率を示すもので、資産効率性を評価するうえで重要です。大幅なプラス差は、同社が総資産を活用して効率的に利益を生み出していることを示しています。2024年に一時的に総資産が大きく増加した一方で、2025年にはバランスシートが整理され、資産効率が向上した点が背景にあると考えられます。投資家から見ると、総資産の無駄が少なく、資産に対する収益性が高い企業であることは好材料です。
3. 売上高営業利益率
売上高営業利益率は3.41%で、業種平均の5.75%を下回っています。売上高に対してどれだけ営業利益を確保できているかを示すこの指標で劣後していることは、収益構造に課題があることを意味します。特に同社は公共事業や人材派遣など利益率が比較的低いビジネスモデルを展開しているため、営業利益率が圧迫されやすい構造にあります。また、M&Aに伴うのれん償却や人件費の増加が短期的に利益率を押し下げている可能性もあります。今後は、付加価値の高いサービスや効率的な経営管理による利益率改善が投資家から期待されるポイントです。
4. 自己資本比率
自己資本比率は33.14%で、業種平均の6.68%を大幅に上回っています。これは、財務健全性が業種水準と比較して格段に高いことを示しており、安定的な経営基盤を持っている点で投資家に安心感を与えます。同社は過去に自己資本比率が一時的に20%台に低下したものの、現在は改善傾向にあり、財務リスクは比較的低いと評価できます。M&A戦略を積極的に展開しているにもかかわらず、自己資本比率を高水準に維持できているのは、資金調達やキャッシュフロー管理が堅実である証拠です。
5. 配当性向
配当性向は0%であり、業種平均の41.33%を大きく下回っています。つまり、当期純利益を株主への配当に回さず、内部留保や成長投資に充てている状況です。長期配当を期待する投資家にとっては物足りなさを感じる一方で、成長企業であることを踏まえると、再投資を優先する姿勢として理解できる部分もあります。ただし、株主還元の観点からは、今後の利益安定化とともに配当開始を検討する必要があるでしょう。投資家は「成長優先か配当優先か」の経営方針を慎重に見極める必要があります。
6. 純資産配当率
純資産配当率も0%で、業種平均の2.37%を下回っています。純資産に対してどれだけ配当を行っているかを示すこの指標は、配当性向と同様に株主還元の姿勢を表します。現在は無配であるため数値はゼロですが、自己資本比率が高い同社にとっては、将来的に配当余力を生み出す余地は十分にあります。特にROEが業種平均を上回っている点を踏まえると、内部留保を一定水準確保したうえで配当を実施することは可能と考えられます。中長期的には、株主に安定した配当を還元できる体制整備が期待されます。
配当方針と今後の展望
株式会社メイホーホールディングスの有価証券報告書によると、同社は「株主への利益還元を重要な経営課題」と位置づけています。そのうえで、事業拡大や財務体質強化のために内部留保を確保しつつ、将来的には安定的かつ継続的な配当を実施する方針を掲げています。ただし、2017年2月に持株会社として設立されて以来、一度も配当を行っていないのが現状です。内部留保の充実度や事業環境の変化を見極めながら、将来の配当実施を検討していくとの記載があり、現時点で具体的な実施時期は未定です。
1. 現状の配当関連指標
有価証券報告書に記載された直近の財務指標からは、以下の点が読み取れます。
- 配当性向:0%(過去から現在まで無配当)
- 1株当たり配当額:0円
- 自己資本利益率(ROE):17.51%(直近年度)
- 自己資本比率:33.14%(財務健全性は比較的高い水準)
- 株主総利回り:株価上昇により高い数値を示しているが、これは株価変動に基づくもので、配当とは無関係
これらから分かるのは、同社は内部留保と成長投資を優先しており、配当による株主還元は行っていない一方で、財務基盤は改善しているという点です。
2. 今後の配当方針に関する考察
(1) 内部留保の重要性
同社はM&Aを軸とした「従業員承継型M&A」や「企業支援プラットフォーム」の拡大を戦略の柱としています。そのため、資金を配当に回すよりも内部留保を蓄積し、次の投資や買収に充てることを優先しています。今後もしばらくは内部留保の充実が最優先されると見られ、配当開始までには一定の時間が必要と考えられます。
(2) 配当開始のタイミング
配当開始の目安となるのは、営業利益と純利益が安定的に黒字を確保し、自己資本比率がさらに向上する時期です。現状でも自己資本比率は30%を超えており健全性は高いものの、まだ成長投資フェーズにあるため、短期的な配当開始は難しいと予測されます。中期的には「内部留保の充実状況に応じて配当実施」という文言から、3〜5年以内に初配当が実現する可能性があります。
(3) 想定される配当水準
業種平均の配当性向(41.33%)や純資産配当率(2.37%)と比較すると、現状は大きな乖離があります。ただし、同社が配当を開始する際には、まずは象徴的な水準、たとえば配当性向10〜20%程度でのスタートが現実的です。その後、業績の安定化に伴って徐々に業種水準に近づけていくと予想されます。
(4) 配当と株価の関係
現在は株価上昇によって投資家への還元が実現している形ですが、将来的に配当を組み合わせることで「株価上昇+安定配当」という二重のリターンが期待できます。特に個人投資家や長期投資家にとっては、配当の有無が投資判断の大きな要素になるため、配当開始は株主層の拡大にもつながるでしょう。
3. 投資家にとっての示唆
- 成長企業ゆえの無配当
今は配当を出さない代わりに、成長投資を優先している段階であり、将来の企業価値向上を狙った経営判断と捉えるべきです。 - 財務体質の改善が配当の前提条件
自己資本比率や利益水準は改善傾向にあり、配当開始の基盤は徐々に整いつつあります。今後の中期経営計画の進展が重要なポイントになります。 - 初配当は象徴的な位置づけに
業種平均並みの配当水準に一気に到達することは考えにくく、まずは低めの配当から開始し、段階的に引き上げていくシナリオが有力です。 - 長期投資家にとっての魅力
株価上昇に加え、将来的な配当開始によって株主還元が拡充すれば、FIREを目指す個人投資家にとって魅力的な投資対象になり得ます。
長期配当投資評価
レーティング評価:
評価コメント
株式会社メイホーホールディングスは、これまで一度も配当を行っていない無配当企業ですが、将来的には「安定的かつ継続的な配当を実施する」という方針を掲げています。ここで重要なのは、現在は成長投資を最優先に据えており、内部留保を積み上げる段階にあるという点です。中小企業支援やM&Aを軸にした成長戦略は独自性があり、今後の収益拡大の可能性は高いといえます。しかし、長期投資で配当を狙う投資家にとっては「現状で無配当」という事実が大きなマイナス材料です。
日本株市場全体を見渡すと、同じ成長企業であっても上場数年以内に象徴的な初配当を実施するケースは少なくありません。例えば、グロース市場の一部企業は早期に少額配当を始めることで株主還元姿勢を示し、長期投資家を取り込む戦略を取っています。それに比べると、同社は2017年の設立以来8年以上が経過しているにもかかわらず、配当が未定のままであることは「株主還元意識の弱さ」とも受け取られかねません。
ただし、財務基盤の強化や自己資本比率の改善が進んでいる点は評価できます。特に2025年6月期にはROEが17%超まで改善しており、資本効率性は業種平均を上回る水準に到達しました。このことは将来的なキャッシュフロー創出力を裏付けるものであり、内部留保が充実すれば配当を開始できる余地が十分にあると考えられます。さらに、中小企業承継という成長テーマは社会的需要も高く、長期的な成長期待は市場全体と比較しても強い部類に入ります。
結論として、「現時点では長期配当投資を目的とした銘柄としては不向きだが、中長期的に配当開始と増配が実現すれば有望銘柄へ成長し得る」という立ち位置です。よって、他の日本株(すでに配当実績があり、株主還元姿勢が明確な企業)と比較すると、レーティングは控えめにならざるを得ません。
- プラス面:ROEや財務健全性は改善傾向にあり、将来の配当実施余地は十分にある。成長テーマも独自性があり、長期的な潜在力は高い。
- マイナス面:設立以来8年経過しても無配のまま。配当開始時期が未定であり、長期配当投資を目的とする投資家にとっては現状では魅力に欠ける。
他の日本株と比較した場合、すでに配当実績を積み重ねている銘柄の方が安定的な長期投資対象としては優位性が高いため、星2つという評価となります。